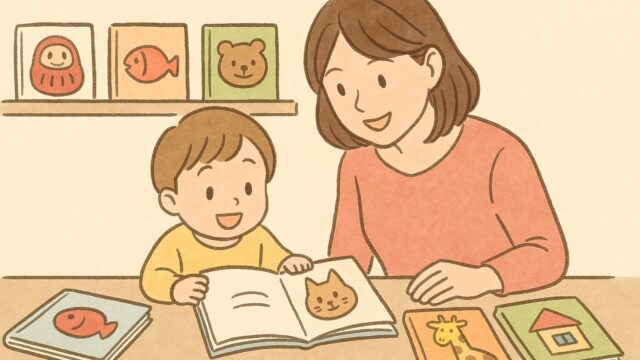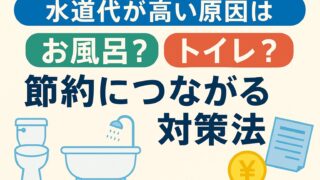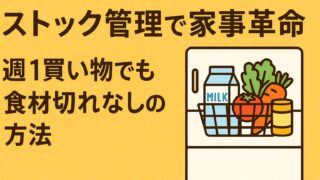親子で楽しく学べる!お金教育の始め方と初めの一歩ガイド

「お金ってどこからくるの?」「なんでカードでピッてすると買えるの?」
ある日、息子にそう聞かれて、ドキッとしました。
私は家計管理は得意だけど、「お金の仕組み」をどう説明すればいいかは迷いました。
でも、難しいことを覚えさせるより、まずは生活の中で「お金ってこういうものだよ」と感じてもらうことが大切なんだと気づいたんです。
今回は、私が実践している親子で楽しく学べるお金教育の始め方をお話しします。
お金教育はいつから始めるべき?
お金教育って、小学生になってからでいいのかなと思っていました。
でも、保育園児でも「これ買って」「お金ある?」って聞いてくるんですよね。
我が家でも、まだ数字もよくわからない頃から、お金という言葉だけはしっかり覚えていて驚きました。
我が家の場合|4歳から意識
うちの子が初めて「お金」について聞いてきたのは4歳のとき。
スーパーで「どうしてこのお菓子買えないの?」と泣かれて、つい「お金がないから」と答えたんですが、その一言に責任を感じました。
「じゃあお金があれば何でも買えるの?」と返されて、ハッとしたんです。
そのとき、私は言葉足らずだったことに気づきました。
帰り道、息子と二人で歩きながら
「お金ってね、ただあるだけじゃダメなんだよ。大事に使わないとすぐなくなるし、欲しいもの全部は買えないんだよ」
と話したら、じっと聞いていてくれました。
もちろん4歳なので、全部理解できたわけじゃないと思います。
でも、「お金=何でも買える魔法」ではなく、「必要なときに使うもの」と少しでも感じてくれたならいいなと思っています。
早ければ早いほど良い?
専門家も「お金教育は早ければ早いほど良い」と言いますが、私は「その子が興味を持ったタイミング」でいいと思っています。
うちの息子も、5歳になった今は
「お金ってどうやって作るの?」
「パパはどうしてお金もらえるの?」
と、より深いことを聞いてくるようになりました。
大切なのは、押し付けではなく、一緒に考えること。
「ママも詳しくはわからないから、一緒に調べてみようか」と答えると、息子も嬉しそうにしています。
お金の仕組みってどう説明する?
子どもにとって「お金=紙や硬貨」だけど、大人から見ると、銀行やクレジットカード、電子マネー…複雑ですよね。
スーパーのレジでピッとするだけで商品が買えたり、スマホ決済で一瞬で終わったり。
大人にとっては便利だけど、子どもから見たら「どうしてそんなことができるの?」と不思議でいっぱいだと思います。
まずは現金から教える
私はまず、現金で「モノと交換するもの」ということを教えました。
スーパーで一緒にレジに並ぶときには、必ずお金を出すところを見せるようにしています。
「今日は1,000円持ってるから、これとこれが買えるよ」
「でもこれを買うと、あっちは買えなくなるね」
と、なるべく具体的に話します。
ある日、お菓子売り場で息子が「全部買いたい!」と目をキラキラさせていたとき、
「もし全部買ったらどうなると思う?」と聞くと、しばらく考えて
「お金なくなる?」
と一言。
「そうだね、お金は無限じゃないから、必要なものを選ばないとね」と伝えると、渋々ながら2つに絞っていました(笑)。
こういう小さなやり取りの積み重ねが、お金の仕組みを理解する第一歩になるんだなと感じています。
クレジットカードは「後払い」
ある日、コンビニでクレジットカードを出したとき、息子に
「ママ、そのカードで払えばいいじゃん!」
と言われてギクッ(笑)。
子どもからしたら、カードは魔法の板にしか見えないですよね。
そこで、「このカードはね、魔法じゃなくて、あとで銀行からお金が出ていくんだよ」と説明しました。
「え、じゃあお金なくなるの?」と聞かれたので、
「そうだよ。今は払ってないけど、あとでママのお財布から出ていくんだよ」
と伝えたら、「ふーん…」とちょっと不思議そうな顔をしていました。
4歳にはまだピンとこない様子でしたが、「カード=魔法」ではなく、「あとで払うもの」と少しでも理解してくれたならいいなと思います。
お小遣い教育の始め方
お金教育の中で、やっぱりお小遣いは大事。
でも、渡し方ひとつで意味が変わるんですよね。
私も最初は、「まだ早いかな」「無駄遣いばかりしそう」と悩んでいました。
でも、お金は使ってみないとわからないことが多いし、早めに経験させるのもいいかもと思ったんです。
我が家のお小遣いルール
うちは年長さんになったタイミングでお小遣い制を始めました。
月に500円だけど、その中で好きなお菓子を買ったり、貯金箱に入れたりしています。
初めて渡した日は大喜びで、「これで恐竜のガチャガチャする!」と張り切っていました。
でも、そのあとスーパーで「これも買いたい!」とお菓子を手に取ったとき、
「じゃあ今月のお小遣いから出す?」
「来月まで待つ?」
と聞くと、しばらく考えて棚に戻していました。
「どうして戻したの?」と聞いたら、
「だってガチャガチャしたいし、お菓子は今度でいい」
と、5歳なりに計算しているようで感心しました。
その日の夜、「今日のお菓子我慢してえらかったね」と声をかけたら、照れくさそうに笑っていました。
お手伝い報酬はどうしてる?
お手伝い報酬をお小遣いにする家庭も多いですよね。
私も最初は「お手伝い=お金」というイメージがつくのはどうなんだろうと思っていました。
我が家では、基本のお手伝い(お皿運びや洗濯物たたみ)は無報酬にしています。
ただ、特別なお手伝い、たとえば玄関掃除や窓拭きなど、いつもより頑張ったことに対しては「ありがとう代」として10円渡すこともあります。
この前、玄関を雑巾でピカピカにしてくれたとき、「今日はありがとう代あげるね」と渡したら、
「えっ?いいの?やったー!」と大喜び。
そのあと、「ママ、またお手伝いするね!」と言ってくれました。
お金のためだけに動くのではなく、「ありがとう」という気持ちも一緒に伝えたいなと思っています。
こういう経験が、ただのお小遣い以上に、心の成長にもつながるんじゃないかなと感じています。
お金教育で気をつけたいこと
お金のことを教えるとき、気をつけたいのが「ネガティブワード」。
つい忙しいときやイライラしているときに、
「お金がないからダメ!」
「そんな無駄遣いして!」
ときつい言い方をしてしまうこと、ありませんか?
私も何度もあって、そのたびに「今の言い方、よくなかったな…」と反省します。
「お金がないからダメ」はNG?
私もよく言ってしまいますが、「お金がないから買えない」と言うと、お金=悪いものと感じてしまうことがあるそうです。
この前も、スーパーで息子に「今日アイス買って!」と言われて、「今日はお金がないからダメ」と答えてしまいました。
すると息子は、「じゃあ、お金いっぱいあったら何でも買えるの?」と聞いてきたんです。
その一言でハッとしました。
「お金がないからダメ」ではなく、
「今は別のことに使う予定だから今日は買わないよ」
と言い換えるだけで、印象が全然違うんだなと改めて思いました。
最近は、「お金はあるけど、今日は必要なものだけにしようね」と伝えるようにしています。
すると息子も、「じゃあ今度にする!」と納得してくれることが増えました。
お金は「ありがとう」の交換
最近は、「お金はありがとうの気持ちが形になったもの」と伝えるようにしています。
保育園で描いた絵を褒めたときに、息子が「これママにあげる!」と言ってくれました。
私は嬉しくて、「ママもすっごく嬉しいから、お礼に今日は大好きなプリン作ってあげるね」と返したら、ニコニコしながら
「ママ、ありがとうのお金くれたの?」
と聞いてきました。
「うーん、お金じゃなくて、ママのありがとうはプリンだったんだよ」
と話すと、ケラケラ笑っていました。
「誰かが頑張って作ったものにありがとうを伝えるためにお金を使うんだよ」と話すと、少しずつ理解してきたようです。
この前はスーパーで、
「このお菓子作った人にもありがとうって言うんだよね?」
と言っていて、思わず胸が熱くなりました。
親子で楽しく学べるお金遊び
難しい話ばかりだと、子どもも聞いてくれませんよね。
「お金ってこういうものだよ」とただ説明するよりも、遊びの中で自然と学べる方が子どもも楽しめます。
お店屋さんごっこ
うちはダイソーで買ったおもちゃのお金セットで「お店屋さんごっこ」をしています。
紙のお札や硬貨、おもちゃのレジまでついていて、これがかなり本格的。
ある日、息子が突然「いらっしゃいませー!今日は何を買いますか?」と店員さんになりきっていて、私が
「このリンゴください」
と言うと、
「はい、100円です!」
とレジをピッと鳴らして、おつりも渡してくれました。
「おつりは…500円渡したから、400円のお返しです!」
と、まだ計算は完璧じゃないけど、一生懸命考えている姿にキュンとしました。
「〇〇円です」「おつりです」とやり取りすることで、お金の流れを自然と覚えてくれるので助かっています。
この前は、レジ袋まで用意してくれて、「こちら袋いりますか?」と聞かれたときは思わず笑ってしまいました(笑)。
最近のレジ体験がしっかり身についているみたいです。
お買い物ミッション
スーパーに行くときは、「今日は500円以内でお菓子を2つ選んでね」というミッションを出しています。
最初は値段も見ずに好きなものをカゴに入れていて、「それだと600円になっちゃうよ」と伝えると、「えー?じゃあどうしたらいいの?」と困り顔。
一緒に棚を見ながら、「こっちは150円だから、2つで300円になるね」と計算してみせると、少しずつ値段を見るようになりました。
最近では、
「ママ、これとこれなら500円以内だよ!」
と自分で計算して報告してくれるようになり、成長を感じています。
まとめ|お金教育は日常からゆるっと始めよう
お金の仕組みを教えるって、改めて考えると難しいですよね。
でも、日常の中で「これっていくらかな?」「どうやって払うのかな?」と声をかけるだけでも、立派な教育になると思います。
我が家もまだまだ試行錯誤中ですが、子どもが「お金ってありがとうの気持ちだよね」と言ってくれたときは嬉しくて泣きそうになりました。
これからも無理なく、楽しく、親子でお金と向き合っていこうと思います。
ぜひ今日のお買い物から、小さな一歩を踏み出してみてください。