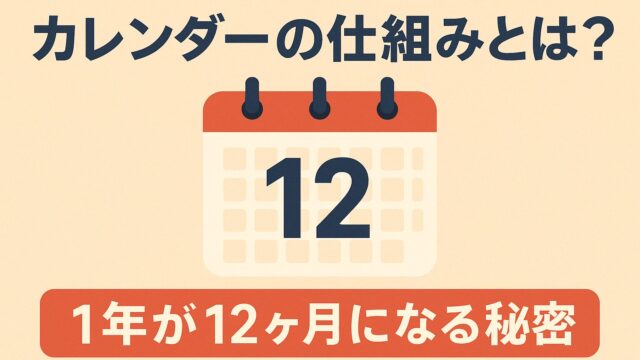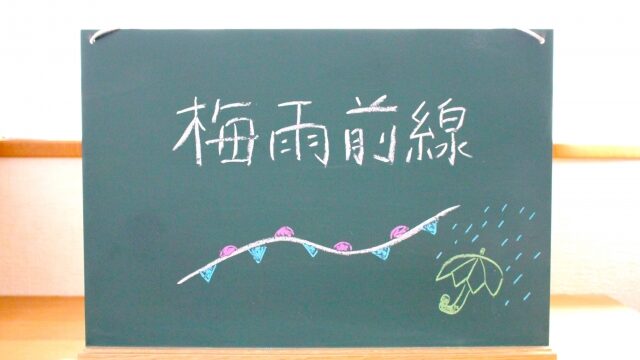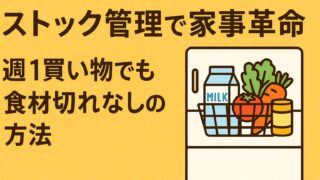東西南北の方角の由来とは?子どもに楽しく教える方法
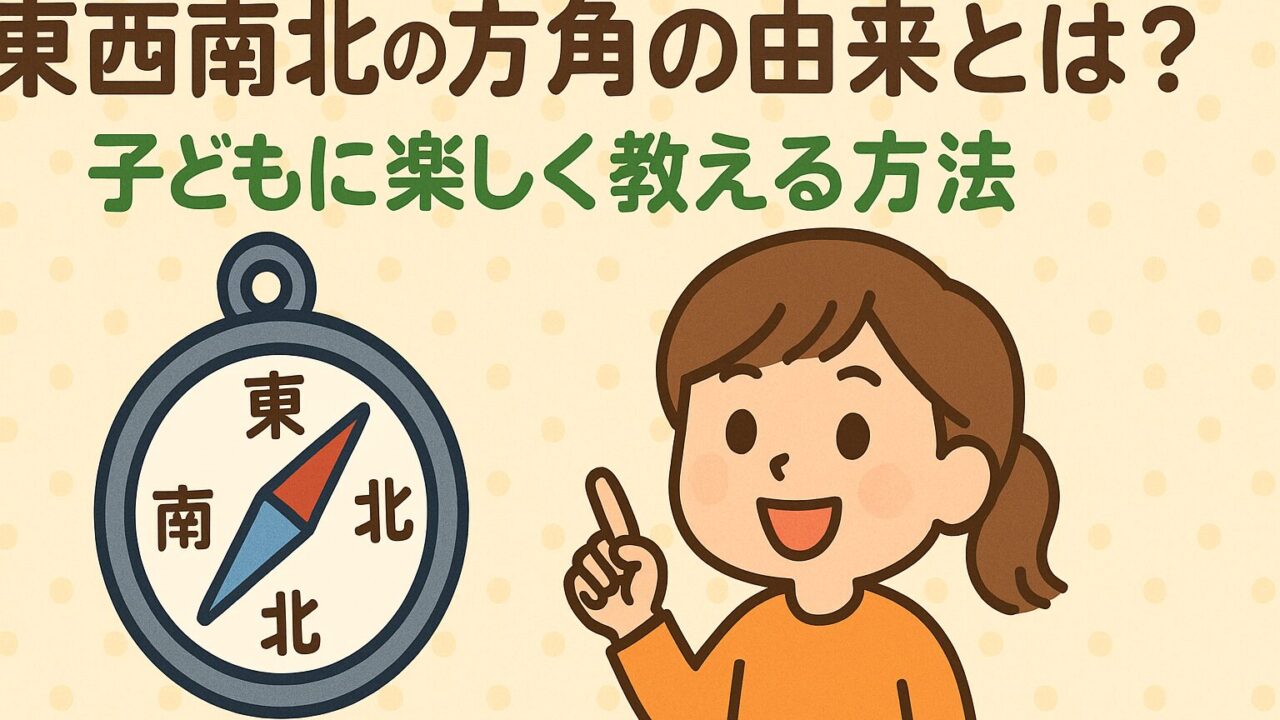
「ママ、東ってどっち?」
ある日、散歩中に息子に聞かれました。地図を見ながら「この道を東に進むよ」と言ったのですが、「東ってなに?」と。たしかに、普段から東西南北を意識して生活することって少ないですよね。
今回は、そんな子どもからの素朴な疑問に答えるべく、東西南北の意味や由来、わかりやすい教え方までまとめました。我が家で実践している方向感覚の育て方も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
東西南北ってどんな意味?
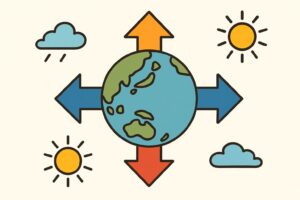
「東西南北」とは、私たちが暮らす地球上で方向を表す言葉です。
子どもにとってはまだピンとこない言葉かもしれませんが、日常生活でも役立つ大切な知識ですよね。
私も子どもに説明するとき、「東は太陽がのぼる方角だよ」と話しています。
でも最初は、「太陽が昇る?それってどこ?」とさらに質問攻めに。
そこで、毎日の生活の中で少しずつ覚えてもらうようにしています。
東=太陽が昇る方向
朝、カーテンを開けると差し込んでくる光。あれが東からの光です。
我が家では「おはようの光が来る方が東だよ」と教えています。
たとえば、朝食のときに「今日は東の空がきれいだね」と声をかけたり、休日の散歩でも「太陽が昇るほうが東なんだよ」と繰り返し伝えるようにしています。
息子も、「おはようの方が東なんだね!」と覚えてくれました。
西=太陽が沈む方向
夕方になると赤く染まる空。
「保育園のお迎えの帰り道、夕日が沈んでいく方向が西だよ」と言うと、息子も「あっちが西か!」と嬉しそうに。
最近では、「ママ、夕日きれいだね。あっちが西だよね?」と逆に確認してくれるようになりました。
夕方は子どもも一日の終わりを感じる時間帯なので、印象に残りやすいみたいです。
南=お日さまが高い場所
昼間、太陽が一番高くのぼる方向が南です。
冬場は南側に光が当たりやすいので、洗濯物を干すときも「南向きのベランダは乾きやすいね」と話題にしています。
また、我が家ではリビングが南向きなので、昼間はぽかぽか暖かく、「おひさまの方向が南なんだよ」と教えると、「じゃあおひさまは南にいるんだね!」と納得してくれました。
北=太陽が一番遠い場所
北は太陽があまり通らない方角です。
我が家の玄関が北向きなので、冬になると冷たい風が吹き込みやすく、「玄関が北だから寒いんだねー」と話しているうちに、北=寒いというイメージがついたようです。
また、冷蔵庫の設置場所や食品庫も北側にあるので、「涼しいから食べ物が痛みにくいんだよ」と教えると、「北って冷蔵庫の方向なんだ!」とさらに覚えやすくなったようです。
方角の由来ってどう決まったの?
私自身も「なんで東西南北ってこの漢字なんだろう」と思って調べてみたことがあります。
普段は何気なく使っているけど、漢字にはそれぞれ深い意味や昔の人の感覚が込められているんですね。
東の由来
「東」という漢字は、木の間から太陽が昇る様子を表した漢字だそうです。
「木」という字の真ん中に「日(太陽)」がある形から、「木の間から出るもの」という意味が生まれたといわれています。
昔の人は、太陽が昇る方向を特別に感じていたそうです。
たしかに、毎朝新しい一日が始まる東の空には、希望やパワーを感じますよね。
私は子どもに、「東は朝日が顔を出す特別な場所なんだよ」と教えています。
西の由来
「西」という字は、鳥の巣を表す漢字から来ているそうです。
夕方になると鳥たちは巣に帰りますよね。そのことから、日が沈む方向=西と結びついたとされています。
私は息子に、「夕方になると鳥さんたちが『ただいま』って巣に帰る方向が西だよ」と話しています。
すると、「じゃあ、鳥さんの家の方向が西だね!」と嬉しそうに言ってくれました。
南の由来
「南」はもともと、占いをするときに使う器具(音を測る楽器や鐘を吊るす台)を表していたといわれています。
その道具が南を向いて置かれていたことから、「南」という漢字で方角を表すようになったそうです。
また、太陽が一番高くなる方角を南と決めて、生活の中心としてきた歴史があります。
私は「おひさまが一番元気な場所が南だよ」と子どもに話しています。
南ってなんだかあたたかくて明るいイメージですよね。
北の由来
「北」は、二人の人が背中を向け合う形が元になっているそうです。
昔の字を見ると、背を向け合う人の形を表していて、そこから北風が冷たいこともあって、寒い地域では背中を丸めて北風に背を向けることが多かったことから「北」という意味になったともいわれています。
我が家では「北からは冷たい風が吹くんだよ」と教えています。
すると、「だから冬は北風が冷たいんだね!」と息子も納得した様子でした。
子どもに方向を教えるコツ
私も最初は「どうやって教えたらいいんだろう」と迷いました。
東西南北って、大人でも普段意識しないことが多いですよね。
でも、日常生活の中で少しずつ教えると、子どもも自然に覚えてくれます。
太陽の動きと結びつける
まず一番わかりやすいのが、太陽の動きと方角を結びつけること。
「朝日が昇る方が東、沈む方が西だよ」と何度も言ううちに、息子は東西を覚えました。
朝、登園前に外へ出たときも「今日もおひさまが東から出てきたね」と話しかけたり、
夕方の買い物帰りには「西の空が赤くなってるね、日が沈む方向だよ」と声をかけています。
最初は「ふーん」という感じだった息子も、最近では「ママ!今日は東の空ピンクだよ!」と自分から教えてくれるようになりました。
家の中で場所を決める
我が家では、「おもちゃ棚は北側」「窓際は南側」と言いながら、家の中でも方角を意識させています。
たとえば、
「お昼寝マットは南側に敷くとぽかぽかするね」
「このおもちゃ箱は北側の壁に置こうね」
など、方角と日常動作をセットにして声かけをしています。
洗濯物を干すときも「南向きのベランダだからよく乾くね」と言うと、「南はおひさまがあたる方だよね!」と誇らしげに答えてくれます。
散歩やドライブでクイズ
散歩中や車で移動しているときには、「今歩いてる方向はどっちだと思う?」とクイズ形式にすると楽しみながら学んでくれます。
我が家ではよく、
「今から公園に行くけど、東と西どっちかな?」
「スーパーは南側だよね?じゃあ帰りはどっちに進む?」
といった質問をしています。
方角を知るとどんないいことがある?
子どもが方角を覚えると、想像以上に世界が広がります。
私自身、息子が少しずつ東西南北を理解していく姿を見て、「これは一生モノの知識だな」と感じました。
地図が読めるようになる
東西南北がわかると、地図を見たときの理解度がぐんと上がります。
以前は地図を見せても「これどこ?」という感じだった息子ですが、最近では
「公園はこっちの東側だね!」
「スーパーは西にあるから帰りは夕日が見えるね」
と、地図を読みながら案内してくれるようになりました。
私も一緒に歩きながら「今、東に向かってるよ」「あっちが北だから寒い風が吹くね」と話しかけることで、息子の記憶にも残りやすくなっているようです。
理科や社会の勉強に役立つ
太陽の動き、地球の自転、公転など、方向感覚があると理科の理解が深まります。
授業で「太陽は東から昇って西に沈む」と習ったときも、「あ、それ知ってる!」と嬉しそうに話してくれました。
また、社会科でも地図記号や地形図を読むときに、方角がわかるだけでスムーズに問題が解けるようになります。
私自身も、方角が苦手だった頃は地図を見るたびに混乱していたので、早いうちから身につけておくと学校生活でも役立つと感じます。
災害時にも役立つ
地震や災害のとき、避難所や自宅の方角を把握しておくと安心ですよね。
先日、学校の避難訓練で「南側の校庭に避難してください」と先生に言われたときも、「南ってこっちだよ!」と友達に教えてあげたそうです。
まとめ|日常会話で東西南北を楽しく学ぼう
東西南北って、言葉では簡単だけど、実際に覚えるのは意外と難しいもの。
でも、毎日の生活の中で「朝日が昇る方が東だよ」「この道は南に向かってるね」と会話に取り入れるだけで、子どもは自然と方向感覚を身につけてくれます。
ぜひ今日から、散歩やドライブのときに方角クイズをしてみてください。
きっと、「ママ、東ってこっちだよね!」と得意げに教えてくれる日が来ますよ。