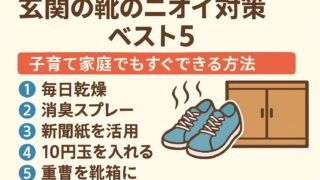風ってどこから来るの?親子で学ぶ風が生まれる本当の理由

「ママ、風ってどこから来るの?」
ある日、保育園から帰る道で息子がふいに聞いてきました。確かに、風って当たり前に吹いているけれど、どこから来るのかちゃんと説明したことってないなぁ…と気づかされました。
今回は、そんな子どもの“なぜ?”に答えるために、風がどこから来るのか、わかりやすく解説していきます。おうちでの会話がもっと楽しくなるヒントになれば嬉しいです。
風ってそもそも何?

「風って何?」と聞かれたとき、私は「空気が動いてることだよ」と答えました。
でも、息子は「え?空気が動くってどういうこと?」と不思議そう。
風とは、簡単に言えば空気の流れのこと。
私たちの周りにはいつも空気がありますが、温度や気圧の差でその空気が動き出すと「風」になるんです。
例えば、冷たい空気は重くて下に溜まり、温かい空気は軽くて上にあがる性質があります。この空気の動きが風になるんですね。
実際、私も子どもの頃は「風って見えないけど、どうやってできるんだろう?」と疑問に思っていました。
息子も同じように、「じゃあ、扇風機の風は?外の風と何が違うの?」と聞いてきます。
扇風機の風も、仕組みは同じ。
羽が回って空気を押し出すことで、空気が動いて風になるんです。
外で吹いている風は、自然にできた温度差や気圧差で空気が動く風。
扇風機は人が作った機械で無理やり空気を動かして風を作っているんですね。
「じゃあママ、僕が走ったときに顔に当たる風は?」と聞かれたこともあります。
これも面白いですよね。
実は、自分が走ると空気にぶつかって、その空気が顔に当たるから風を感じるんです。
息子には「走ったら空気とぶつかるから、風が来るみたいに感じるんだよ」と話したら、「そっか、僕が速いから風が来るんだ!」とニコニコしていました。
こうして、日常の中で当たり前に感じている風も、子どもに説明しようと思うと、改めて自然の不思議さや面白さに気づかされます。
私も息子と一緒に、「風って奥が深いなぁ」と感じる時間でした。
どうして風が吹くの?
太陽の力が関係している
ある日、息子と一緒にベランダで風を感じていたとき、「太陽のおかげで風が吹くんだよ」と話しました。
すると、「太陽と風って関係あるの?」とびっくりした顔。
太陽が地面や海をあたためると、そこから温められた空気が軽くなって上にのぼっていきます。
このとき、温かい空気が上にあがると、その場所に空気が少なくなるんですね。
すると周りから新しい空気が流れ込んできて、その動きが風になるんです。
私は息子に「太陽が地面をあたためて、あったかくなった空気がふわーっと上にいくと、そのあとを追いかけるようにして空気が流れ込むんだよ」と手振りを交えて説明しました。
息子も「そっか!じゃあ太陽ってすごいんだね」と空を見上げていました。
温度差で風が生まれる
例えば、海と陸ではあたたまり方が違いますよね。
昼間は陸地が太陽にあたためられてどんどん熱くなるけど、海はゆっくりしかあたたまりません。
逆に夜になると、陸地はすぐに冷えるけど、海は昼間ためた熱であたたかさを保っています。
この昼と夜の温度差、海と陸の温度差が、風を生む大きな理由なんです。
息子には「お風呂のお湯と水のところが混ざると流れができるでしょ?あれと同じだよ」と説明しました。
すると、「なるほど!お風呂で混ぜるとグルグルなるもんね!」と、得意げに話してくれました。
風が吹くときの身近な例え
さらに、「アイスが溶けるのも太陽の力だよね?でも風は溶けないの?」と聞かれたこともあります。
私は「アイスはあたためられると溶けるけど、風はあたためられた空気が動くことでできるから、溶けるものじゃないんだよ」と話すと、「ふーん…風って難しいけど面白いね!」とつぶやいていました。
こうして一つひとつの疑問に答えていくと、私自身も改めて自然の仕組みを学び直す機会になっています。
子どもの「なんで?」って、本当に大事な学びの種ですね。
風はどこからどこへ吹いているの?

高いところから低いところへ
風は「気圧が高いところから低いところへ向かって吹く」という性質があります。
気圧って難しい言葉ですが、簡単に言えば空気の重さや押す力のこと。
空気は目に見えませんが、実は私たちの体にもずっと圧力をかけているんですよね。
私も昔は、天気予報で「高気圧」「低気圧」と聞いても、「なんだか難しそう…」と思っていました。
でも、あるとき気象予報士さんが「高気圧は空気がたくさん集まっているところ、低気圧は空気が少なくなっているところ」と説明しているのを聞いて、とても腑に落ちました。
気圧が高い場所には空気がぎゅっと詰まっていて、その空気が押し出されるようにして、気圧が低い場所へ向かって流れていきます。
これが風になるんですね。
息子には、「高気圧はお友だちがいっぱい集まってるところで、ぎゅうぎゅうだから空いてるところ(低気圧)に移動したくなるんだよ」と話したら、「ぎゅうぎゅうはいやだもんね!」と笑っていました。
日本で吹く風の向き
春や夏は南風、冬は北風が多いのも、この温度差と気圧の違いによるものです。
たとえば、夏は南から暖かい空気が入ってくるので南風が吹きますし、冬はシベリア方面から冷たい空気が流れ込むので北風が強くなります。
この前、外を歩いているときに息子が「今日は風があったかいね」と言ったので、「南の国から来た風だから、あったかいんだよ」と話すと、「じゃあ北風は寒いんだね!北風小僧の寒太郎だ!」と嬉しそうに歌いだしました。
風向きで季節を感じる
私自身も、小さい頃に祖父が「今日は南風が吹いてるから、春が近いぞ」と教えてくれたことを思い出します。
風向きひとつで季節を感じるなんて、なんだか素敵ですよね。
こうして子どもと風の向きを感じながら歩くと、ただのお散歩も自然の授業に変わります。
風がどこから吹いて、どこへ向かっているのか知るだけで、世界が少し広く感じられる気がします。
おうちでできる風の実験
子どもと一緒に楽しめる、簡単な風の実験を紹介します。
「風って目に見えないけど、本当にあるんだね!」と子どもの目が輝く瞬間が見られますよ。
うちわで風を感じる
うちわをパタパタ仰いで、「空気が動くと風になるんだよ」と実感させてあげるとわかりやすいです。
息子も「僕が風を作れるんだ!」と得意げでした。
うちではさらに、風が当たる部分と当たらない部分でどう違うか比べたり、
「うちわを早く動かすと風は強くなるかな?ゆっくりだとどうかな?」と質問して実験しました。
すると息子は、ゆっくり仰いだときと勢いよく仰いだときの風の強さの違いに大興奮。
「わー!強い風は冷たいね!」と大喜びで何度も試していました。
ドライヤーで風の流れを見てみよう
ドライヤーの風をティッシュに当てて、空気が動くと物が動くことを見せるのもおすすめです。
ただし熱風には注意してくださいね。冷風モードで試すと安心です。
ティッシュがふわっと浮かぶのを見て、「ドライヤーの風で飛んだ!」と息子も嬉しそう。
さらに「この風も空気が動いてるんだよ」と教えると、「じゃあ、外の風もドライヤーみたいに空気が動いてるんだね!」と納得していました。
ストローで風を作ってみる
もうひとつ簡単な実験は、ストローで息を吹くこと。
「このストローから息を出すと、ここに風がくるよ」と吹いて見せると、息子はストローを持って自分でも「ふーっ」と風を作って楽しんでいました。
ティッシュや小さな紙を置いて、「どこまで飛ばせるかな?」とゲーム感覚で遊ぶのも盛り上がります。
風があるから助かること

洗濯物が乾く
「風があると洗濯物がすぐ乾くね」と息子に言うと、「じゃあ風って便利なんだね!」と嬉しそうでした。
実際、洗濯物を干すときって、風があるかないかで乾き具合が全然違いますよね。
我が家では、朝から曇りの日でも少し風が吹いていると「今日は乾きそうだな」とちょっと安心します。
この前も、保育園のお迎え帰りに「今日は風が強いから、タオル乾いてるかもね」と話したら、息子が「風さんありがとうって言わなきゃね!」とニコニコ。
そんな何気ない会話に、私までほっこりした気持ちになりました。
暑い日に涼しくしてくれる
夏の公園でも、風が吹くと一気に過ごしやすくなりますよね。
じりじり照りつける日差しの中、木陰で風が吹いてくると「生き返る〜!」と心の中で叫びたくなります。
私は汗だくになりながら遊ぶ息子を見て、「ちょっとでも風があると助かるなぁ」といつも思っています。
息子も、滑り台を何度も滑って暑くなったときに風が吹くと、「あっ、涼しい風きた!」と大喜び。
火を使うときも役立つ
他にも、キャンプで炭をおこすときなんかも、風があると火がつきやすくなりますよね。
うちではまだキャンプデビューしていませんが、BBQをするときに風のおかげで火がついて「風ってすごいね!」と感動したことがあります。
風で遊べる楽しさも
そして何より、風があると外遊びが楽しくなります。
シャボン玉を吹くと、風に乗ってふわふわ飛んでいったり、凧揚げをしても高く上がったり。
息子は凧揚げが大好きで、「今日は風あるかな?」と冬になると毎日のように聞いてきます。
まとめ|風のひみつを知って親子で自然を楽しもう
風は、太陽の光であたためられた空気と、冷たい空気の温度差から生まれる自然の恵み。
子どもに「風ってどこから来るの?」と聞かれたら、「太陽があたためてくれるからだよ」と答えてあげてください。
自然のしくみを知ると、毎日の景色が少し違って見えてきます。
ぜひ今日から、子どもと一緒に風を感じながら、おうち時間やお散歩をもっと楽しんでみてください。