子どもにわかりやすい!時計の読み方を家庭で楽しく学ぶコツ
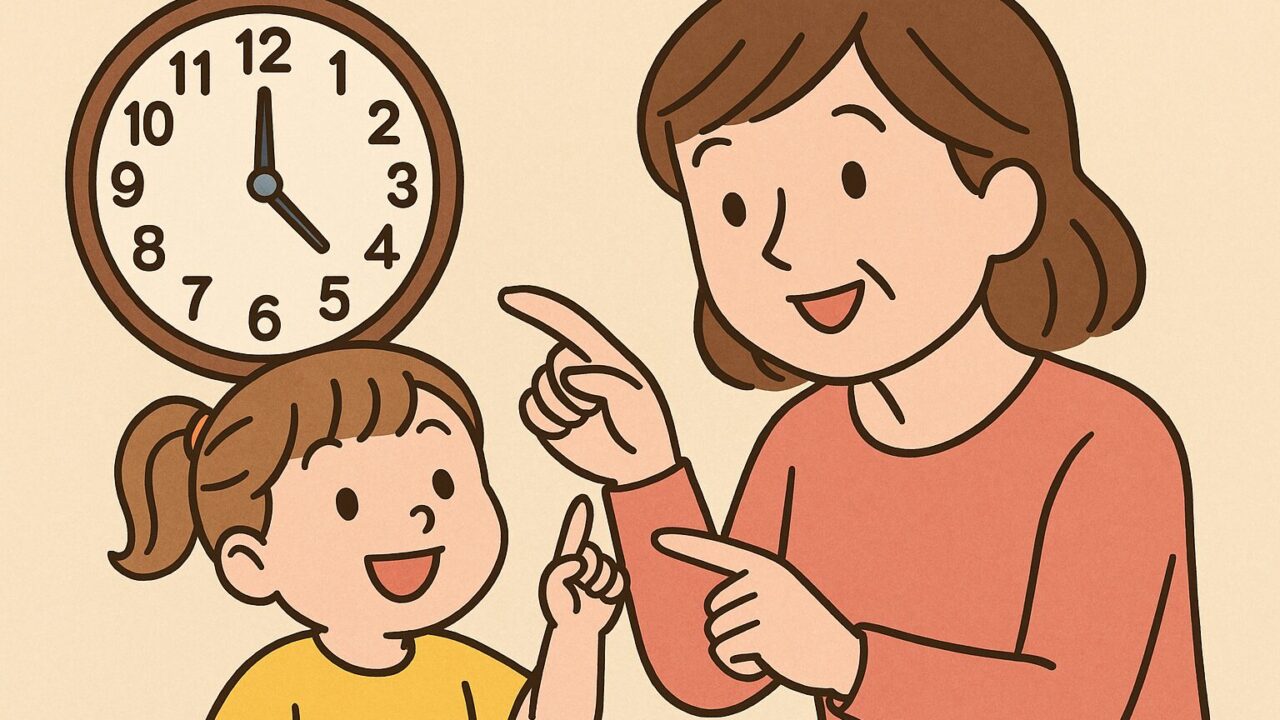
子どもが成長していく中で「時計の読み方」は必ず通る道ですよね。私の娘も、4歳を過ぎたころから「ママ、いま何時?」とよく聞いてくるようになりました。最初は数字を読むだけで精一杯でしたが、針の意味や「○時半」「○時15分」といった表現になると混乱してしまうことも。私自身も「どうやって教えるのが一番わかりやすいんだろう?」と悩んだ時期がありました。
この記事では、子どもが時計をスムーズに読めるようになるための工夫や、家庭でできる練習のコツをまとめます。私が実際に試して効果を感じた方法を中心に紹介するので、同じように悩んでいるご家庭の参考になれば嬉しいです。
時計の読み方を教える前に知っておきたいこと

時計の読み方を教えるときにまず意識したいのは、「子どもがどの段階まで理解できているか」を確認することです。年齢や性格によっても理解の進み方は異なり、焦らずその子のペースに合わせることが大切です。
数字を理解できているかを確認する
時計を読むには、まず数字をきちんと認識できることが前提になります。1から12までを見てすぐに読めるようになっていないと、針の位置と結びつけるのは難しく感じてしまうのです。
我が家では、数字の絵本や数字カルタを繰り返し使って遊びながら、数字に親しませました。数字を単に暗記させるのではなく、「5が出たらジャンプ!」「7を見つけたら clap!」といった体を動かす遊びと組み合わせると、楽しみながら自然に覚えられます。
さらに「時計は1から12までの数字が順番に並んでいるんだよ」と説明し、日常生活で「いまは8だから、ご飯の時間だね」などと声かけすることで、数字と生活をリンクさせました。こうした積み重ねが、時計の読み方を理解する土台になります。
時間の感覚を生活に結びつける
子どもにとって時間はとても抽象的な概念です。大人が「あと5分ね」と言っても、子どもは「5分ってどのくらい?」とピンとこないことが多いのです。
そこで私は「あと5分=アンパンマンの歌が1回分終わるくらい」など、子どもが体感できる出来事に置き換えて説明しました。すると「なるほど、5分ってこれくらいなんだ」と少しずつ感覚をつかんでいきました。
また、「もうすぐ夜ご飯」「そろそろお風呂」など、毎日のルーティンと時計を結びつけて伝えるのも効果的です。たとえば「長い針が6にきたらお風呂ね」と声かけすると、子どもは生活の流れの中で時間を実感できます。
生活習慣と時計の動きを関連づけてあげると、時計がただの数字の集まりではなく「次の行動を教えてくれる便利なもの」だと気づけます。この気づきが、時計を読むモチベーションにもつながるのです。
このように「数字を理解しているか」「時間を生活に結びつけられているか」を確認し、しっかりと基礎を固めることで、次のステップである「時」「半」「分」などの読み方をスムーズに教えられるようになります。
時計の基本的な読み方の教え方

ここからは、子どもが実際に時計を読めるようになるためのステップを紹介します。焦らず段階を追って教えることで、混乱せずに理解を深めていけます。
まずは「○時」を理解する
最初に覚えるべきは「時」の読み方です。短い針(時針)に注目させ、「いまは3時!」と、1時間単位で伝えるところから始めます。
我が家では「おやつは3時」と決めていたので、「短い針が3を指したらおやつね」と声をかけました。すると娘も「針が3になったら楽しい時間!」と自然に覚えることができました。「子どもが楽しみにしている時間と結びつける」ことが、学びやすさの大きなポイントです。
また、いきなりすべての時間を教えるのではなく、「朝ごはんは7時」「寝る時間は9時」など、生活習慣とセットで特定の時刻を繰り返し伝えることで、子どもの中で時計と生活が結びついていきます。
「○時半」を教えるコツ
「○時半」の概念は、子どもにとって少し難しく感じるステップです。短い針が数字と数字の間にあるときに「半」になるため、最初は混乱してしまうことが多いのです。
私は実際の時計を一緒に見ながら、「6を指したら半分の合図だよ」と説明しました。数字の「6」を「半分のしるし」として覚えさせると、子どもにとって理解しやすくなります。
さらに、日常生活に取り入れる工夫も効果的です。たとえば「6を指したらお風呂に入ろう」「6を指したらテレビを消そう」というように、生活リズムと結びつけると自然と「半=30分」という認識が定着していきます。
分の読み方に進む
「15分」や「45分」といった分の表現は、難易度がぐっと上がるステップです。長い針(分針)が指す位置によって意味が変わるため、子どもは混乱しやすいのです。
そこで我が家では、アナログ時計の文字盤に小さな色付きシールを貼りました。「3=15分」「6=30分」「9=45分」というように、区切りごとに目印をつけることで、子どもが視覚的に理解できるようにしたのです。
特に「3」と「9」の位置は混乱しやすいので、違う色のシールを貼ると「これは15分、こっちは45分」とわかりやすくなりました。視覚的に区切りを示す工夫は、抽象的な概念を具体的に見える形にしてあげることにつながります。
最初は「5分ごと」に読み進めるくらいでも十分です。「1は5分」「2は10分」と少しずつ教えることで、「分」という考え方に慣れていきます。
このように「時」→「半」→「分」と段階を踏んで進めると、子どもは無理なく時計の読み方を習得できます。特に生活習慣とリンクさせたり、視覚的にサポートする工夫を加えることで、理解のスピードが大きく変わると感じました。
楽しく学べる家庭での工夫

時計の読み方は「勉強」よりも「遊び」に寄せた方が続きます。ポイントは、短い時間でいいので毎日触れることと、生活の出来事にくっつけること。遊び×短時間×毎日少しずつを合言葉にすると、子どもが自然と時計好きになります。
遊びを取り入れる
クイズを生活に差し込む
例「今からお風呂に入るのは何時」「長い針が6になったら片づけ開始」「短い針が7に来たら朝ごはん」など、行動のきっかけを時計にします。正解したらシールを1枚貼るなど、達成感を見える化すると意欲が続きます。
ミニ会話の例
親「長い針が3を指したね。何分」
子「15分」
親「すごい。じゃあ短い針が5の少し手前なら何時くらい」針合わせゲーム
おもちゃ時計や手作り時計で、親が言った時刻に子どもが針を合わせます。最初は「3時」「7時」など丸い時だけ。慣れたら「4時半」「7時15分」へ。兄弟がいるなら交代で「先生役」と「生徒役」をやると盛り上がります。タイマー・ミッション
キッチンタイマーを5分に設定し「タイマーが鳴る前にパジャマに着替える」「15分で宿題を終える」などの時間挑戦。終わったら時計を見て「何分使った」を声に出して確認します。時間の長さを体で覚えられます。読み上げリレー
紙にいくつかの時刻を書いて山札にし、1枚めくって声に出して読むだけのシンプルな遊び。最初は「○時」だけ、次に「○時半」、仕上げに「○時○分」。テンポよく回すのがコツです。おでかけスタンプ
出発や到着の時刻を自分で読み上げてノートに記録。週末に見返して「一番早起きした日は」「一番遅く帰った日は」と会話すると、時間が生活の記録に変わります。
絵本やおもちゃを活用
針が連動するおもちゃ時計
長い針を動かすと短い針も少し動くタイプがおすすめ。実物に近い動きを体験でき、「半」や「25分」のイメージがつきます。DIY 紙皿時計
紙皿に1〜12を書き、外周に0・5・10…を小さく記入。色つきピンで長短2本の針を留め、0・15・30・45分の位置にシールを貼ります。自分で作ると愛着がわき、練習の回数も増えます。絵本の読み方のコツ
時計が出てきたページで必ず一時停止し「この場面は何時かな」と問いかけます。物語の流れに「時間」を絡めることで、理解がストーリーに乗って定着します。ロールプレイ
子どもが店員、親が客になり「11時開店です」「12時半に休憩です」など、時間表現を使うごっこ遊びをします。声に出すことで、読み方が話し言葉に落ちます。
デジタル時計との違いを教える
見比べ学習
同じ場所にアナログとデジタルを並べ、朝と夜に「同じ時刻を2つの見た目で確認」します。
例「07:30=短い針が7と8の間、長い針が6」「19:30=夜でも短い針の位置は同じ」変換ゲーム
親がデジタルで「16:45」と言ったら、子どもはアナログに針を合わせる。逆に、アナログを見てデジタルで言い当てる。慣れたら24時間表記も少しずつ。午後と午前の混乱対策
「17時は午後5時」のように、家の出来事と結びつけます。たとえば「保育園のお迎えは16時台」「お風呂は19時台」など、家庭のルーティンを軸に整理すると混乱が減ります。デジタル偏重を防ぐ
家の中で一日に一度はアナログを読む時間を作ります。たとえば夕食前の「時刻読み当番」を子どもが担当すると、自然にアナログに触れられます。
この3本柱を回すと、子どもの「できた」が増えます。うまくいかない日は無理をせず、次の日に1問だけでも OK。小さな成功を積み重ねるほど、時計はぐっと身近になります。
よくあるつまずきと対応方法

時計の読み方を練習していると、必ず「ここでつまずくな…」という場面があります。子どもにとって時計は「数字」「針」「時間」という抽象的な要素が重なっているため、一度に理解するのは難しいのです。そこで、よくあるつまずきと、そのときに家庭でできる工夫を整理しました。
短い針と長い針の混同
最も多いのは、「どっちが時でどっちが分?」という混乱です。特に最初のうちは針の長さを気にせず、指している数字だけを読んでしまいがちです。
私は「短い針=ゆっくり進む」「長い針=早く進む」と説明しました。動きの速さを比喩にすることで、「短い針は1時間かけて1つ進む」「長い針は1時間で1周する」という違いが感覚的に理解できます。
さらに、実際に時計を見せて「長い針はあっという間に進むけど、短い針は少しずつしか動かないね」と声をかけると、子どもも違いを体で感じられました。「動きの速さ」に注目させるのは、針の役割を区別する大事なポイントです。
「○時半」と「○時30分」の混乱
もう一つの壁は「半」と「30分」のつながりです。大人にとっては同じ意味でも、子どもにとっては「半分」と「30」という数字がなかなか結びつきません。
私は「ピザを半分に切ると30分だよ」と食べ物で例えたり、紙皿に針を描いて「半分=6に来たとき」と視覚的に示しました。繰り返すことで少しずつ「半=30分」というイメージが定着していきます。
また、「○時半」という表現をよく使う生活場面(例:夕飯の準備は6時半)を意識的に取り入れるのも効果的でした。実際の生活とつながると理解が早まります。
分単位の細かい読み方
「1分刻みで読む」ことは、大人が思う以上に子どもには難しい課題です。最初から完璧を求めると嫌になってしまうので、私は「まずは5分単位で読めれば大丈夫」と割り切りました。
時計の文字盤には「1=5分」「2=10分」と、5分ごとの目盛りがあります。これを一緒に数えながら確認することで、数字と分が結びついていきます。5分ごとの区切りをマスターすれば、細かい読み方への土台ができるので、焦らず進めることが大切です。
さらに遊び感覚で「針が3を指したら15分」「針が6を指したら30分」という練習を繰り返すと、自然と「分」の感覚も定着していきました。
このように、時計の読み方でのつまずきは「抽象的な概念をどう具体化するか」がカギになります。比喩や遊び、生活習慣に結びつけることで、子どもは少しずつ混乱を乗り越えていけます。
家族で取り組むと効果的な方法

時計の読み方は、子どもひとりで練習するよりも、家族みんなで取り組んだ方が身につきやすくなります。日常のあちこちで時計を意識できる環境を作ると、自然に「時間を読む習慣」が根づいていくのです。
声かけを意識する
時計の読み方は、机に向かって練習するだけではなかなか定着しません。日常生活の中で「声かけ」を意識することが効果的です。
たとえば、パパやママが「今は何時かな?」と尋ねたり、「ごはんは7時だから、短い針が7を指したら教えてね」とお願いしたりすると、子どもは「時計を見ること」が当たり前になります。
我が家でも、夫が「長い針が12になったら出発だよ」と声をかけてくれるようになってから、娘は時計を自分から確認する回数がぐっと増えました。家族全員が時計を意識した言葉を使うことが、子どもにとって自然な学びのチャンスになるのだと実感しました。
習慣化していく
毎日の生活リズムを時計と結びつけることが、読み方習得の一番の近道です。
・「寝る時間は9時」
・「お風呂は7時半」
・「保育園のお迎えは4時」
このように、いつもの行動と時刻をセットにして伝えると、子どもは「時計を見ると次の行動がわかる」と理解できるようになります。
また、日常の繰り返しこそが一番の練習になります。夜寝る前に「今日は9時に寝たね」と一緒に時計を確認したり、朝の登園時に「今は8時、もうすぐ出発だね」と声をかけたりするだけでも習慣化に繋がります。
習慣化のポイントは「特別な練習時間を作らない」こと。遊びや家事の流れの中で時計を意識させると、子どもは無理なく学びを積み重ねていきます。
このように、家族で一緒に時計を意識する工夫を取り入れると、子どもの「時計を見る力」は驚くほど早く育っていきます。何より大切なのは、家庭の中で時計をポジティブに扱う雰囲気を作ることです。
まとめ|時計の読み方は生活に結びつけるのがカギ
時計の読み方は、一度に完璧を求めると親も子も疲れてしまいます。まずは「時」を読むことから始めて、「半」や「分」へと少しずつステップアップしていくのがポイントです。そして何より大切なのは、勉強というより生活の中で自然に身につけること。遊びや日常の声かけを取り入れると、子どもにとっても楽しく学べる時間になります。
「まだ覚えられない」と焦らず、毎日の中で少しずつ時計と仲良くなれる工夫をしてみてください。気づけば自分から「今は何時?」と得意げに教えてくれる日がきっと来ますよ。














