春分の日ってどんな日?意味とお彼岸のつながりをわかりやすく解説
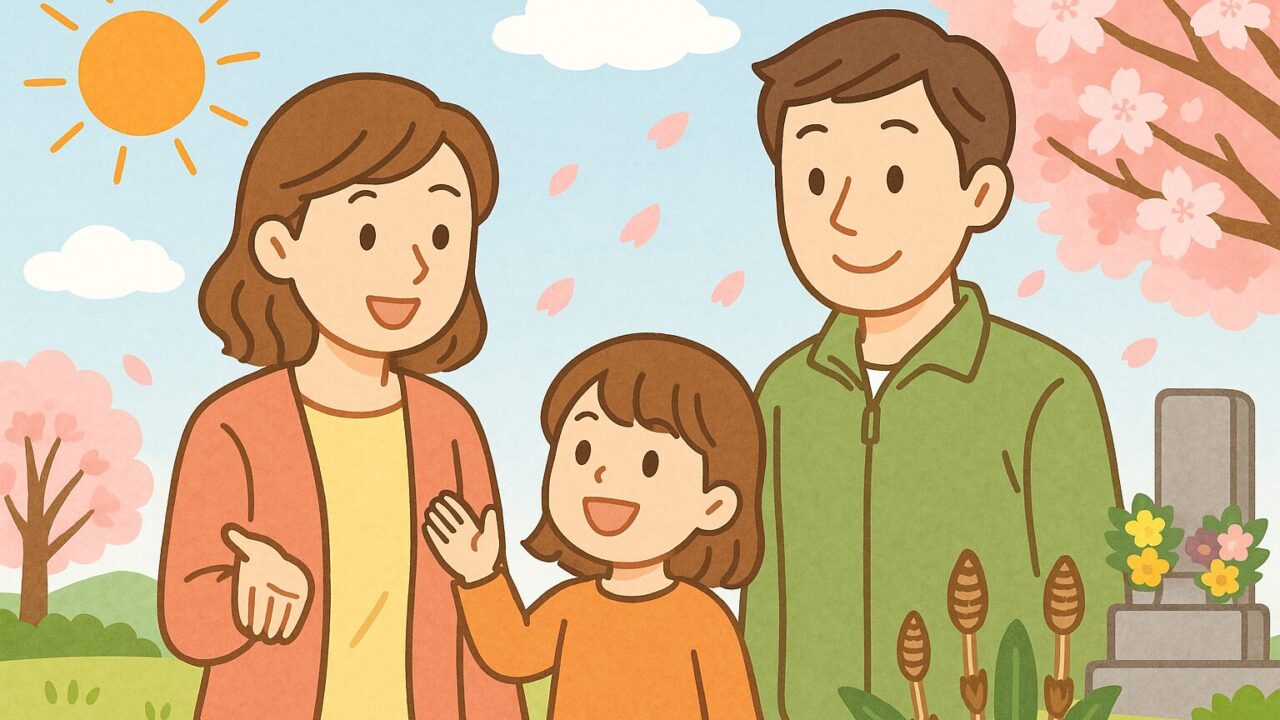
春が近づいてくると、カレンダーに「春分の日」という祝日があることに気づきます。でも、子どもに「何の日なの?」と聞かれて、うまく説明できなかった私。春分って、何を基準に決まってるの?どうしてお彼岸と関係してるの?
今回は、春分の日の意味や由来を、家庭や季節の暮らしとあわせてわかりやすくまとめました。
私自身、「なるほど!」と納得できたことがたくさんあったので、子どもにも伝えやすくなりました。行事の背景を知ると、季節の楽しみ方も少し変わりますよ。
春分の日っていつ?どんな意味があるの?

春分の日は、毎年だいたい3月20日ごろにあたる祝日です。でも、「春分の日って、なんで毎年同じ日じゃないの?」と不思議に思ったことはありませんか?
実はこの日は、天文学的な観測によって決まっていて、年によって3月19日〜21日の間で変動するんです。国立天文台が毎年発表する暦をもとに、翌年の春分の日が決定されるという仕組みになっています。
私も最初は「カレンダーで毎年ちょっと違うのはなぜ?」と思っていたのですが、太陽の動きと地球の位置が関係していると知ってから、なんだかこの日が特別に感じられるようになりました。
春分の日は「昼と夜の長さがほぼ同じ」日
この日のいちばんの特徴は、昼と夜の長さがほぼ同じになるということ。
具体的には、太陽が真東から昇り、真西に沈むことで、日中と夜の時間がほぼ半々になります。ちょうど「バランスが取れた日」というわけです。
自然のリズムに目を向けると、「このあたりから日が長くなってきたな」と感じる方も多いのではないでしょうか?私も毎年、夕方の明るさに「あれ?この時間でもまだ明るいね〜」なんて話すのが、春の訪れを実感する瞬間です。
そして、植物も一斉に動き出す時期。梅が咲いて、桜のつぼみがふくらみ、つくしやふきのとうなどの春の野草も顔を出します。
「春分の日」は、冬から春へと移り変わる“節目”のような日なんですね。
我が家の「春分あるある」会話
毎年、わが家ではこんな会話が定番です。
「春分すぎたら、もう冬服しまっていいよね?」
「うん、ヒートテックはもう暑いかもね〜」
「子どもの上着、そろそろ薄手のに替えようか」
こうした何気ない会話の中に、「季節が動いてるな〜」という感覚が自然と育まれている気がします。季節の変化を家族で感じられるって、なんだか嬉しいものですね。
祝日としての意味は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」
春分の日は、国民の祝日として、「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」と定められています。
ちょっと抽象的で難しそうな言葉ですが、私はこう解釈しています。
「自然のめぐみに感謝して、春の始まりを祝う日」
寒い冬を越え、ようやく暖かい陽ざしに包まれるこの季節。花が咲き、虫たちが動き出し、鳥の声が戻ってきて…自然界すべてが「春が来たよ!」と教えてくれるようです。
だからこそ、この祝日は「ただの休日」として過ごすのではなく、自然や季節に目を向ける“きっかけの日”として過ごせたらいいなと思っています。
子どもと一緒に「春が来たね」と外に出て、つくしを探したり、ふきのとうの天ぷらを味わったり。そんな時間が、春分の日を特別な日にしてくれるのかもしれません。
このように「天文学的な意味」と「生活の中での感覚」が結びつくことで、春分の日がぐっと身近に感じられるようになりますね。
春分の日と「お彼岸」の関係って?

春分の日を調べていると、セットのように出てくるのが「お彼岸」という言葉。でも正直、私は最初「お彼岸って春分とどう関係あるの?」と思っていました。
子どもの頃は「お墓参りに行く日」というイメージしかなかったのですが、きちんと意味を知ると、春分の日とお彼岸には深くて美しいつながりがあることに気づきました。
お彼岸は「春分・秋分」を中日とした1週間
まず「お彼岸」というのは、春と秋、それぞれ年に2回ある仏教の行事です。
春分の日を中心に前後3日をあわせた7日間が「春のお彼岸」
秋分の日を中心に前後3日をあわせた7日間が「秋のお彼岸」
この1週間は、ご先祖さまに感謝の気持ちを伝える期間とされていて、日本では昔からとても大切にされてきました。
我が家でも、春のお彼岸には家族そろってお墓参りに行きます。お花を手に持って、子どもたちと一緒にお線香をあげると、空気がふっと変わる感じがして。「今ある暮らしを大切にしよう」って、自然と思えてくるんです。
子どもにとっても、「春分の日=ご先祖さまに会いに行く日」というイメージがしっかりついていて、仏壇に手を合わせる姿にも成長を感じます。
「彼岸」と「此岸(しがん)」の意味
そもそも「彼岸」ってどんな意味?と気になって調べてみると、仏教の教えに深く関係していることがわかりました。
仏教では、
今、私たちが生きている迷いや欲に満ちた世界を「此岸(しがん)」
その先にある悟りの世界、穏やかで苦しみのない世界を「彼岸(ひがん)」
と呼びます。
つまり、「彼岸」は仏の世界であり、亡くなった人が安らかに過ごすとされる場所なんですね。
ここで春分との関係が出てきます。春分の日には、太陽が真東から昇り、真西に沈むという特徴があります。
仏教では「西の方角に極楽浄土がある」と考えられていたため、太陽が真西に沈む春分の日は、彼岸に心を向けやすい特別な日とされてきたのです。
自然の動きと信仰の考え方が重なり合って、お彼岸という風習が生まれたと思うと、なんだかとても奥深いですよね。
家族で過ごす「お彼岸」の時間が、心の豊かさに
お彼岸の期間にお墓参りや仏壇に手を合わせることで、ふと立ち止まって“今ここ”を見つめ直すきっかけになります。
「忙しさで忘れかけていたけど、大事にしたいものがあったな」
「子どもがこうして手を合わせる姿、ちゃんと見せておいてよかったな」
そんなふうに感じた春分の日もありました。
昔ながらの行事を“なんとなく”で終わらせず、その意味を子どもと一緒に知ることで、行事がもっと身近に、心に残るものになる気がしています。
春分の日に食べる「ぼたもち」とは?

「お彼岸といえば、ぼたもち!」
この組み合わせ、なんとなく聞いたことはあっても、実はその意味まで知らない…という方も多いのではないでしょうか?私もその一人でした。
けれど、いざ調べてみると、季節や日本語の美しさ、そして昔ながらの知恵が詰まっていることがわかり、感動すら覚えたんです。
春のお彼岸=「ぼたもち」、秋のお彼岸=「おはぎ」
まず知っておきたいのが、春と秋で呼び名が違うこと。
春(牡丹の季節):ぼたもち
秋(萩の季節):おはぎ
でも実は、材料も作り方もほとんど同じ。「呼び方」が季節の花にちなんで変わるだけなんです。
この由来を知ったとき、私はなんだかとってもあたたかい気持ちになりました。言葉の背景にある日本人の感性って、すごく繊細でやさしいですよね。
子どもに話すと、「春はぼたん、秋ははぎ!季節で名前変わるの面白いね!」としっかり覚えてくれました。こういう“知って得する豆知識”って、親子で共有できると嬉しいものです。
わが家の春分恒例「手作りぼたもち」
春分の日が近づくと、我が家では「今年もぼたもち作る?」が合言葉のようになっています。
もち米を炊いて、すりごまをまぶしたり、あんこを包んだり。手がべたべたになりながらも、家族で丸める作業がまるでイベントのようで楽しいんです。
子どもたちには、あんこを包むのがちょっと難しいようで、毎年「あ!はみ出た〜」「これ、まんまるにならない〜」と笑いながら作っています。でも、その不揃いなかたちも、手作りの味って感じで愛おしいんですよね。
「なんでお彼岸にぼたもち食べるの?」と聞かれたときには、こう答えました。
「それはね、ご先祖さまにも“春が来たよ”って伝えるために、甘いぼたもちをお供えするんだよ」
あんこに込められた意味とは?
実は、ぼたもちに使われているあんこ(小豆)には、魔よけの意味があるってご存じでしたか?
昔から、赤い色には「邪気を払う力がある」と信じられており、小豆の赤は“厄除け”や“災いを遠ざける”色として特別視されてきました。
そのため、祝い事や節目の行事、特にご先祖さまに手を合わせるタイミングには、小豆を使った料理を供えることが多いんですね。
「甘いだけじゃなくて、ちゃんと意味があるんだよ」と伝えると、子どもたちもなんだか神妙な顔をして食べていたのが、ちょっと可愛かったです。
行事食を囲む時間が、心の記憶になる
手作りのぼたもちを囲んで、「今日って春分の日なんだね」「また春が来たね」と話すひととき。そんな時間が、子どもにとっても“季節を感じる記憶”として残っていく気がします。
ぼたもちの意味や名前の由来を知ったことで、ただのおやつではなく、「家族で味わう春のしるし」になった気がしています。
春分の日をきっかけに「季節を感じる暮らし」へ

日々の生活に追われていると、どうしても季節の行事が「気づけば終わってた…」なんてことになりがちですよね。私自身も、子どもが生まれるまでは、春分の日がただの祝日になっていた時期がありました。
でも、ある年に子どもが「今日は何の日?」と聞いてきたことがきっかけで、「あ、こういう日にこそ季節を伝えるチャンスなんだな」と気づいたんです。
春分の日は、暮らしの中に季節を取り戻す“きっかけ”になる日。小さなことでも、意識して取り入れていくことで、家族の会話や時間の流れが少しずつ変わっていきました。
我が家の「春分の日ルーティン」
春分の日は、1年の中でも特に「自然とつながっている」ことを意識できる日。わが家では、特別なことはしませんが、毎年のルーティンのようになっていることがあります。
■ 朝の会話で「自然のリズム」を伝える
「今日は昼と夜の長さが同じ日なんだよ」
朝ごはんのときに、こんな話題を出すだけで、子どもたちは「へえ〜!じゃあ明日から昼の方が長くなるの?」と興味津々。“自然のリズムを知る”第一歩になっている気がします。
■ ご先祖さまに手を合わせる時間
お墓参りに行くのが難しい年は、仏壇に家族みんなで手を合わせるだけでも大切な時間。子どもが「ありがとう」ってつぶやいたとき、思わず胸が熱くなりました。
季節と祖先を結びつけて感じる機会って、現代ではなかなか少ないからこそ、大事にしたいと思っています。
■ 家族みんなで「ぼたもちづくり」
毎年恒例の手作りぼたもちは、我が家の春分イベントのハイライト。もち米を炊いている間から「今年はきなこも作る?」と話が弾みます。
丸めながらの会話も楽しくて、「去年はもっと上手にできたよね〜」「これ、顔みたいになった!」と笑いが絶えません。
手を動かしながら季節を感じられる食卓のひとときは、思い出にも記憶にも残ります。
■ 「春らしさ探し」で自然にふれる
午後には「春を見つけに行こう」と言って、近所の散歩へ。つくしやタンポポ、桜のつぼみを見つけると、「あ!春だ!」と子どもが駆け寄って教えてくれます。
「今日は春分の日だし、春を見つける日なんだよ」と言うと、ただの散歩がちょっと特別な時間になります。
季節を“感じる心”を、暮らしの中で育てていく
春分の日を境に、どんどん春らしくなっていく日本の気候。だからこそ、「今日は春分の日だね」と口にするだけで、季節を意識するスイッチが入る気がします。
そしてそれは、子どもにとっても同じ。親が季節を楽しむ姿を見せることで、自然と“感じる心”が育っていくんだと思います。
忙しい日々の中でも、春分の日という節目に、少し立ち止まって自然に目を向けてみる。
それだけで、毎日の景色がちょっと違って見えるかもしれません。
春分の日にまつわる豆知識

春分の日には、知っておくとちょっと誰かに話したくなるような面白い豆知識がいくつかあります。ここでは、そんなトピックを2つご紹介します。
春分の日が「年によって変わる」理由
「春分の日って、だいたい3月20日だよね?」
そう思っていた私ですが、ある年にカレンダーを見て、「あれ?今年は3月21日になってる!」と気づいて不思議に思ったことがありました。
その理由は、春分の日が天文学的な観測をもとに決められているからなんです。
春分の日というのは、地球が太陽のまわりを一周する公転運動の中で、太陽が真東から昇って真西に沈む「春分点」を通過する日。それをもとに、国立天文台が毎年その年の“春分日”を発表し、政府が正式に祝日として定めているんです。
つまり、「毎年同じ日」ではないのは当然のこと。地球の動きって、私たちの感覚よりもずっと繊細で正確なんですね。
この話を子どもにすると、「へぇ〜!宇宙で決まるの!?すごっ」と目を輝かせていました。“祝日=宇宙のリズム”という視点は、なんだかロマンがありますよね。
「暑さ寒さも彼岸まで」のことわざ
「暑さ寒さも彼岸まで」ということわざ、どこかで耳にしたことはありませんか?
これは、春分・秋分を中日としたお彼岸を境に、季節の厳しさがやわらぎ始めることを表しています。
寒さが長引く冬も、「春のお彼岸」をすぎればぽかぽか陽気が戻ってくる
暑さが続く夏も、「秋のお彼岸」が終わると涼しくなってくる
昔の人たちは、こんなふうに自然のサイクルを体感しながら暮らしていたんですね。
我が家でもこのことわざを話すと、「じゃあもうすぐ寒くなくなるね!」と、子どもたちも春が近いことにわくわく。季節を前向きに感じられる言葉って、日々の中にそっと寄り添ってくれる気がします。
「季節を肌で感じる」感覚を、ことわざから学べるのも日本のよさだなと実感しています。
これらの豆知識は、ちょっとした会話のタネになるだけでなく、春分の日がどれほど自然や暮らしに根ざした日なのかを改めて教えてくれますね。
まとめ|春分の日を、家族で季節を感じる日に
春分の日は、自然のめぐみに感謝し、ご先祖さまを敬い、春の訪れを感じる大切な日。
「祝日だから休み〜」で終わるのはもったいない!
家庭でできる小さな行動だけでも、子どもにとっては立派な季節の学びになります。
ぼたもちを一緒に作る
「昼と夜が同じなんだよ」と伝えてみる
お墓参りに出かけて、先祖に感謝する
そんなふうに、「行事を暮らしに取り入れること」で、毎年の春分の日がちょっと特別なものになりますよ。













