合格祈願の絵馬はこう書く!例文付きでわかる願いが叶う書き方完全ガイド
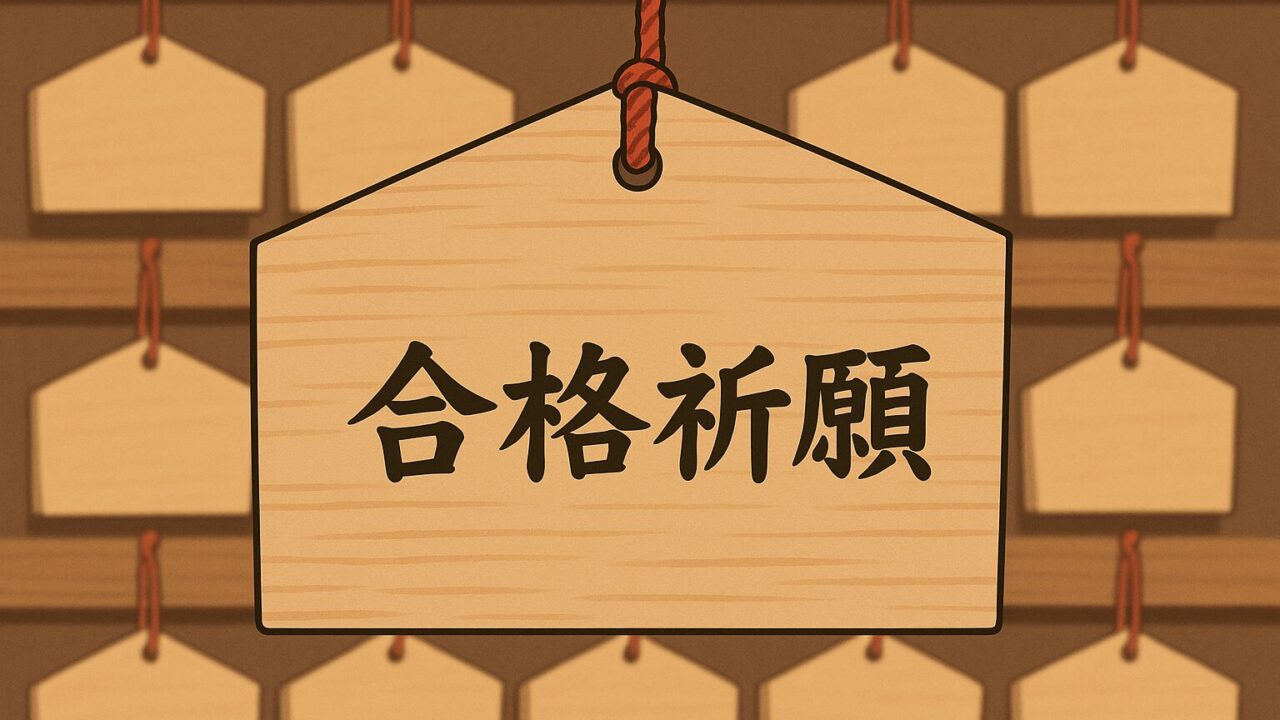
受験シーズンになると、神社の絵馬掛け所にずらりと並ぶ「合格祈願」の文字。
「うちの子も書かせてあげたいけれど、どんな書き方がいいんだろう?」と迷った経験はありませんか?
私も娘の高校受験のとき、書き方ひとつで気持ちが伝わるかどうか悩みました。
この記事では、「合格祈願の絵馬」を正しく・心を込めて書く方法を、わが家の体験を交えながらわかりやすく紹介します。
親子で一緒に願いを形にできるよう、例文もたっぷり載せています。
絵馬の意味と「合格祈願」に込める想い
絵馬は、神社に参拝するときによく見かけるおなじみの存在ですが、実はとても深い意味があります。
もともとは、「神様に感謝や願いを伝えるための神聖な手段」として使われていました。昔の人々は、祈願成就のお礼や新たな願いを込めて、本物の馬を神様に奉納していたのです。馬は「神様の乗り物」と考えられていたため、願いを届ける象徴的な存在でした。
しかし、時代の流れとともに本物の馬を奉納するのは難しくなり、代わりに木の板に馬の絵を描いたものを奉納するようになりました。これが「絵馬」と呼ばれるようになった由来です。今では、馬の絵に限らず、干支や祈願内容をモチーフにした絵馬も多く見られます。
受験シーズンになると、神社の絵馬掛け所には、びっしりと「合格祈願」と書かれた絵馬が並びます。
「○○高校に合格しますように」「第一志望の大学に受かりますように」と書かれた板には、それぞれの家族の想いと努力が込められています。
そして、絵馬は単なる“お願いのメモ”ではなく、「神様への約束」であり、自分自身への誓いでもあります。
「努力を続けます」「最後まであきらめません」という想いを言葉にして残すことで、気持ちが整理され、目標がより明確になるのです。
私も娘の受験の際、初めて一緒に絵馬を奉納しました。娘が震える手で「合格できますように」と書く姿を見て、思わず胸が熱くなったのを覚えています。
願いを言葉にすることで、“合格したい”という気持ちがより現実的に感じられたようでした。
絵馬は神様に願うだけでなく、これまでの努力を形にして「ここからが本番」と気を引き締めるための儀式。
その一枚に込めた想いが、これからの自信や希望を後押ししてくれるのです。
合格祈願の絵馬を書くときの基本ルール
字はていねいに、心を込めて
墨や油性ペンは、最初の一画が太く出やすいので、ゆっくり筆圧を一定に。書く前に深呼吸をして、願いを一度声に出すと気持ちが整います。
にじみを防ぐため、板目の流れ(木目)に合わせて横画はスッと、縦画はまっすぐ。書き終えたら数十秒乾かしてから触れると安心です。
私は娘と書いたとき、緊張で手が冷たくなっていたので、手を温めてからスタート。途中で「上手く書けない〜」と笑う娘に、「この気持ちが届けばいいね」と声をかけると、表情がふっとやわらぎ、最後まで丁寧に書けました。
願いごとは具体的に書く
「合格できますように」でも十分ですが、誰が・どこへ・どんな状態でを具体化すると、自分の目標もクリアになります。
例)「2026年度 ○○高校 普通科に合格し、充実した高校生活を送れますように」
受験番号や模試名などの個人情報は書かなくてOK。迷ったら「学校名+合格+前向きな一言(努力・健康・当日落ち着く)」の三点セットに。
家族で複数書く場合も、文言はコピペせず、その子の口調で短く言い切ると良いです。**「私は最後まで落ち着いて解けます。○○高校に合格します」**のように、宣言形は背中を押してくれます。
名前を書く位置
一般的には表面に願意、裏面に「住所(市区町村までで可)・氏名・日付」。フルネームが基本ですが、プライバシーが気になる場合は「県名+名字+イニシャル」でも問題ありません(神社の案内があれば従うのが最優先)。
家族で一枚に書くなら、主語は受験する本人に揃え、裏面の名前欄は「願主:本人名/保護者名」を並べると整理されます。
ペンは神社に備え付けがあればそれを使用。持参するなら油性細字〜中字が扱いやすく、にじみにくい油性ペンを一本だけに絞ると見た目が統一されます。
親が書く?本人が書く?ベストなタイミング
本人が書くのが基本
合格祈願の絵馬は、受験する本人が「努力して合格したい」という気持ちを神様に伝えるためのものです。
だからこそ、本人の手で書くことが一番の意味を持ちます。
字の上手・下手ではなく、その子の気持ちが込められていることが大切です。
中学生や高校生であれば、自分の言葉で一文を書くだけでも十分。
「○○高校に合格できますように」など、短い言葉でも“自分の願い”として書いた瞬間に、自然と心が引き締まります。
また、本人が自ら絵馬を奉納することで「お願いをした=もう後はやるしかない」という気持ちに切り替えられるのも大きな効果です。
一方で、小学生などまだ字が不安な場合は、親が代筆しても構いません。
その際は、親が一方的に書くのではなく、「ここに『がんばる』って書こうか」「どんな気持ちを込めたい?」と、一緒に言葉を選ぶ時間を持つことが大切です。
子どもが「自分の気持ちを形にできた」と思える体験こそが、絵馬の本当の意味につながります。
家族で書くのもおすすめ
本人の絵馬とは別に、家族がそっと想いを込めて書くのも素敵です。
私の家では、娘が自分の分を書いたあと、私ももう一枚絵馬を購入して「努力が実りますように」と書きました。
書いているとき、娘は少し照れくさそうに笑っていましたが、その表情には「応援されている」という安心感がにじんでいました。
合格祈願の絵馬は、家族にとっても“応援の証”。
お守りを買うのとは違い、書くという行為そのものに「見守っている」「信じている」というメッセージが込められます。
また、神社に一緒に行く時間も思い出になります。冷たい空気の中で手を合わせながら、「あと少し、一緒に頑張ろうね」と声をかけると、不思議と親子の距離がぐっと近づくものです。
合格祈願は、家族の絆を再確認できる時間でもあります。
「本人が書く」ことを中心にしつつも、親がサポートしたり、一緒に祈ったりすることで、子どもにとって忘れられない受験のワンシーンになるでしょう。
合格祈願絵馬の例文集
絵馬に書く言葉は、長文でなくても構いません。
大切なのは「自分の気持ちをまっすぐ表すこと」。
誰かに見せるためではなく、神様と自分との約束として心を込めることが一番です。
ここでは、シーン別に使える例文と、それに込める意味を紹介します。
シンプルな例文
シンプルな言葉ほど、心にすっと響くもの。
余計な飾りをつけず、思いを一文に込めるのがポイントです。
第一志望の高校に合格できますように
無事に試験を乗り越えられますように
今までの努力が実を結びますように
こうした短い言葉でも、書く瞬間に「これまで頑張ってきた日々」を自然と思い出します。
家族で一緒に絵馬を掛ける場合は、本人が書いた後に「がんばったね」と声をかけてあげると、より気持ちが込められます。
「短くても心をこめる」ことが、最も力強い祈りになります。
親から子への願い
受験は、子どもだけでなく家族全員の大きな節目でもあります。
親としては「何もしてあげられないけど、せめて祈りたい」という気持ちになりますよね。
そんなときの言葉には、努力を認めるメッセージを添えると温かみが増します。
○○が自分の力を信じて、笑顔で春を迎えられますように
緊張せずに、いつも通りの力を発揮できますように
これまで頑張ってきた努力が報われますように
たとえば、試験前に「がんばれ」ではなく「見守っているよ」と伝えるだけで、子どもは心強く感じます。
親が書く絵馬は、結果を求めるよりも「あなたの努力を信じている」というメッセージにするのが理想的です。
親の願いは、子どもにとって“背中をそっと押すエール”になります。
子ども自身が書く場合
本人が書く場合は、「どうなりたいか」をイメージできる言葉を使うと良いでしょう。
“合格”という目標の先にある希望を描くことで、気持ちが前向きになります。
○○高校に合格して、大好きな部活を続けたい!
応援してくれた家族にうれしい報告ができますように
最後まであきらめずに、全力を出し切れますように!
目標を「合格」だけにせず、「その先の楽しみ」や「感謝の気持ち」を入れると、より自然で明るい言葉になります。
自分自身に対するメッセージとして、「やればできる」「落ち着いて解ける」といった“自己暗示”を加えてもOK。
絵馬は神様へのお願いであると同時に、“自分自身への励まし”でもあります。
願いを書いたあと、読み返した瞬間に「よし、がんばろう」と思える言葉を選びましょう。
絵馬を奉納したあとの過ごし方
絵馬を掛け終えたあと、多くの人が「これで一安心」と思いがちです。
けれども、本当の“合格祈願”は絵馬を奉納した瞬間から始まるといっても過言ではありません。
神社で絵馬を掛ける行為は、「神様にお願いする」だけでなく、「自分の覚悟を形にする」ことでもあります。
つまり、あとは“行動で見せる”時間。
「神様が見ていてくれる」という気持ちを支えに、日々の勉強や生活の中で努力を重ねていくことが大切です。
奉納後の気持ちの整え方
絵馬を掛けたあと、「お願いしたからもう大丈夫」と気を抜くのではなく、「願いを託したからこそ、もう一度頑張ろう」と前を向きましょう。
神社をあとにする瞬間、空を見上げたり、深呼吸をしたりするだけでも気持ちが切り替わります。
「神様に見守られている」と感じることで、不思議と安心感が生まれ、勉強に集中できるようになるはずです。
また、時々その神社の近くを通るときに、「あの絵馬、まだ掛かってるかな」と思い出してみるのもおすすめです。
その瞬間、自分の中に小さな“やる気のスイッチ”が入ることがあります。
願いを思い出すことで、初心に戻るきっかけになるのです。
家族の声かけも大切に
我が家では、娘と一緒に絵馬を奉納したあと、「よし、あと少し頑張ろうね」と握手をしました。
たったそれだけのことなのに、娘の表情が一気に明るくなり、翌日から机に向かう姿勢が変わりました。
親が見守ってくれているという安心感が、子どもの努力を支える力になるのだと改めて感じました。
絵馬を奉納したあとも、神様に託した願いを“家族みんなで育てていく”気持ちが大切です。
「お参りしたから終わり」ではなく、「お参りしたからこそ、ここからがスタート」と思えたら、受験期の不安も前向きなエネルギーに変わります。
願いを込めたあの日の気持ちを胸に、日々の小さな積み重ねを大切にしていきましょう。
そうして迎える合格発表の日、絵馬に書いた言葉が現実となった瞬間、努力と祈りの意味をきっと実感できるはずです。
まとめ|願いを込めた絵馬で“心の準備”を整えよう
絵馬は単なる「お願いごと」ではなく、家族みんなの想いを形にする特別な儀式です。
大切なのは、誰が書くかよりも「どんな気持ちで書くか」。
願いを込めた絵馬を手にした瞬間から、受験への心構えが自然と整っていきます。
神社へ行く日を、親子での「気持ちをひとつにする日」として、ぜひ大切にしてみてください。














