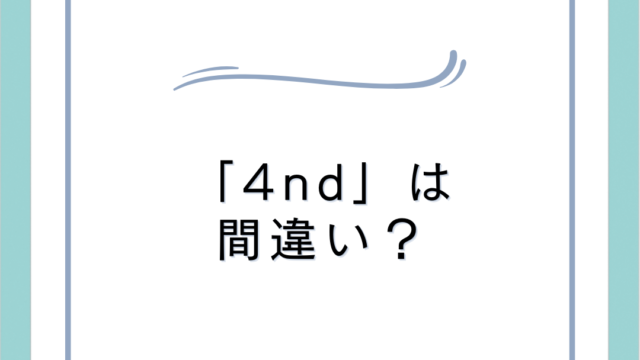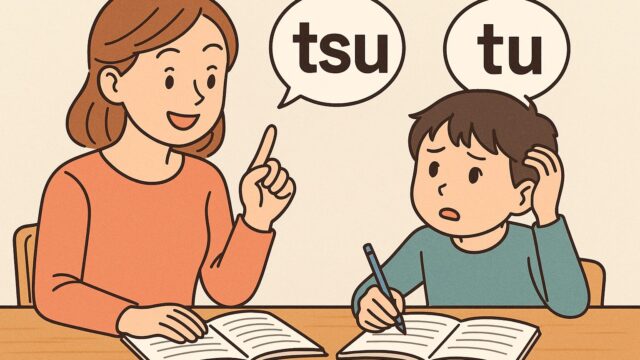七転八倒と七転び八起きの違いから考える、ママが笑顔でいられる人生の選び方

子育てをしていると、「思い通りにいかないこと」の連続ですよね。
夜泣き、反抗期、体調不良、仕事との両立……。まさに“七転八倒”、転んでばかりの毎日。
でも、ふと気づいたんです。大切なのは「倒れないこと」ではなく、倒れても起き上がる力を育てていくことなのだと。
この記事では、「七転八倒」と「七転び八起き」という二つの言葉を通して、私たちの生き方や心の持ち方を見つめ直していきます。
少し立ち止まって、「私はどんな生き方を選びたいか」を一緒に考えてみませんか?
七転八倒とは?
「七転八倒(しちてんばっとう)」は、苦しみや痛みにのたうち回るような様子を表す言葉です。
もともとは仏教用語で、「地獄での苦しみの姿」を意味していました。そこから転じて、「どうにもならないほどの苦しみ」や「心身ともに追い詰められた状態」を表す言葉として、私たちの暮らしにも使われるようになりました。
子育てをしていると、「七転八倒」という表現がまさにぴったりだと思う瞬間がいくつもあります。
たとえば、子どもが突然の発熱で夜通し看病が続いたり、仕事の締め切りと学校行事が重なって時間も心も余裕がなくなったり。
「どこから手をつけたらいいの?」「私、一体どうしたらいいの?」と頭の中がぐるぐるして、心が折れそうになる。そんなとき、まさに“のたうち回るような苦しさ”を感じますよね。
体験談|私も“七転八倒”だった夜
娘が1歳のころ、夜泣きがひどくて、1時間おきに泣き声で起こされていました。
授乳して、寝かしつけて、また起きて…を朝まで繰り返し、夜が明けるころには私もフラフラ。
それでも朝になれば、洗濯、朝ごはん、掃除。積み上がった家事を前に、
「もう無理…」「なんで私ばっかり…」と、涙がこぼれたこともあります。
そんなある朝、座り込んで動けなくなっていた私に、夫が静かに「無理しないで」と声をかけてくれました。
そのひとことにハッとして、「そうか、私は全部ひとりで背負おうとしてたんだ」と気づいたんです。
母親だから頑張らなきゃ、泣いちゃいけない、弱音を吐いちゃいけない。
そう思って、誰にも頼らず、ただひたすら「ちゃんとしよう」としていた。
でも、本当に苦しいときこそ、「ひとりで抱え込まないこと」が何より大切なんですよね。
今振り返ると、あの“七転八倒”の夜は、私にとって「頑張りすぎない練習」を教えてくれた時間でした。
泣いてもいい、休んでもいい、助けを求めてもいい。
そう思えるようになったことで、心の中に少しだけ“ゆとり”が生まれたのです。
七転び八起きとは?
一方、「七転び八起き(ななころびやおき)」は、“何度転んでも立ち上がる”という意味を持つことわざです。
同じ「転ぶ」でも、「七転八倒」が“苦しみに打ちのめされる様子”を表すのに対し、こちらは「立ち上がる力」に焦点を当てています。
つまり、「失敗や挫折も経験のうち。そこから学んで次へ進もう」という前向きな考え方を伝える言葉。
何かに挑戦してつまずいたり、思い通りにいかないことが続いたとしても、「また起き上がって前を向けば大丈夫」と、自分自身を励ますメッセージでもあります。
子育てや家事、仕事に追われる毎日の中で、完璧を目指して頑張りすぎてしまうこと、ありますよね。
でも、少し肩の力を抜いて、「転ぶことも、立ち上がるための一歩」と捉えるだけで、心がすっと軽くなります。
体験談|家族との会話から気づいた「立ち上がる力」
ある日、娘が縄跳びの練習をしていて、「できない!」「もうやだ!」と泣き出しました。
最初のうちは「もう一回やってごらん」と声をかけていた私も、だんだん焦りやイライラが顔に出ていたと思います。
でも、ふと立ち止まって、「そういえば、私も失敗を繰り返してるな」と気づいたんです。
ブログを書いていても、何度もリライトを重ねたり、思ったようにアクセスが伸びなかったり。
それでも諦めずに続けてきたから、少しずつ成果が出てきた。
そこで私は娘にこう言いました。
「何回か失敗してもいいんだよ。ママもブログで何度も書き直してるよ」
すると娘が涙を拭いて、「じゃあ、あと1回だけやってみる!」と笑顔で縄を持ち直しました。
その姿を見て、「ああ、子どもはちゃんと親の言葉を聞いているし、行動を見ているんだ」と胸が熱くなりました。
その瞬間、私の中でもスイッチが入りました。
「うまくいかないからって落ち込むより、もう一度やってみよう」
そう思える心の切り替えこそ、“立ち上がる力”を育てる第一歩なんですよね。
「七転び八起き」は、転ばないことを目指す言葉ではありません。
むしろ、「転ぶことが前提」であり、「そのたびにどう立ち上がるか」を教えてくれる言葉です。
子どもの挑戦を見守る中で、私たち親もまた、“起き上がる背中”を見せることが求められているのかもしれません。
転ぶたびに、少しずつ強く、やさしくなっていく。
その繰り返しこそが、家族の成長の証なのだと思います。
七転八倒と七転び八起きの違いを整理
この二つの言葉は、どちらも「転ぶ」ことを表していますが、その意味や心の向きがまったく異なります。
まずは、下の表で整理してみましょう。
| 比較項目 | 七転八倒 | 七転び八起き |
|---|---|---|
| 意味 | 苦しみや痛みにのたうつ様子 | 何度転んでも立ち上がる |
| 感情 | 絶望・混乱・苦悩 | 希望・再起・成長 |
| 視点 | 「今の苦しみ」に注目 | 「未来への回復力」に注目 |
| メッセージ | つらいときがあることを認める | つらくても前を向く |
「七転八倒」は、まさに“今この瞬間の痛み”をありのままに描いた言葉。
それに対して「七転び八起き」は、“その先の未来に向かう力”を信じる言葉です。
つまり、「七転八倒」は感情の爆発を、「七転び八起き」は感情の整理と再生を表しています。
どちらも人間らしい姿であり、どちらが正しい・間違っているということはありません。
自分を知るきっかけとしての「違い」
私たちは日々、心の中でこの二つを行き来しているのかもしれません。
たとえば、子育てや仕事、人間関係に追われて「もうどうしたらいいの…」と涙があふれるとき、
それはまさに「七転八倒」の状態。
無理に元気を出そうとせず、「つらい」と感じている自分をまず受け止めることが大切です。
そして、少し落ち着いたら「この経験から何が学べるだろう」「どう立ち上がろうか」と考える。
そうやって、「七転八倒」から「七転び八起き」へと心を切り替えるプロセスこそ、人生を前へ進める力になります。
「今の自分はどちら?」を問いかけてみる
子育て中の私たちは、日々いろんな出来事に揺さぶられます。
うまくいかない日もあれば、思いがけない喜びに包まれる日もある。
そんな中で、「今の自分はどちらの状態かな?」と少し立ち止まって考えてみると、
心の整理がしやすくなります。
「今日は七転八倒かも…」と思えたら、それは“苦しみを認めた”サイン。
「じゃあ、次は七転び八起きでいこう」と思えたら、それは“立ち上がる準備ができた”サインです。
自分の心の状態を見つめ、受け入れることこそが、前を向く第一歩。
七転八倒の時期があるからこそ、七転び八起きの力が育ちます。
この二つの言葉は、「落ち込むことも、立ち直ることも、どちらも大切」という人生の真理を教えてくれているのです。
七転び八起き」な生き方を選ぶために
「七転び八起き」という言葉は、ただの“前向きスローガン”ではなく、日々の暮らしの中で少しずつ実践できる「生き方」そのものだと感じています。
私が特に意識しているのは、家庭という小さな社会の中で、“起き上がる力”を一緒に育てていくこと。
子どもも、夫も、そして私自身も、転びながら成長していく。そんな空気を家の中に広げていくことを心がけています。
1. 失敗を「経験」として語る
子どもが失敗したとき、つい「どうしてできないの?」「気をつけてって言ったでしょ」と言いたくなる瞬間、ありますよね。
でも、そんなときこそ深呼吸をして、私はこう言うようにしています。
「ママも昔、同じことしたよ」
自分の失敗談を笑って話すと、子どもは「失敗=悪いこと」ではなく、「誰にでもあること」と受け止めやすくなります。
そして、「ママも失敗してるんだ」と思えた瞬間、子どもの中に小さな安心感が生まれるんです。
その積み重ねが、挑戦を恐れない気持ちへとつながります。
「失敗しても大丈夫」――そう思える環境こそ、挑戦する勇気を育てる一番の土台です。
2. 「完璧よりも継続」を合言葉に
家事も育児も、仕事も、どれも中途半端に感じて「私ってダメだな」と落ち込むこと、ありませんか?
私も以前は、「家をもっときれいにしなきゃ」「毎日ちゃんと料理しなきゃ」「子どもともっと向き合わなきゃ」と、いつも“ねばならない”で自分を追い込んでいました。
でも、あるとき気づいたんです。
「昨日より少しマシなら、それで十分」
その一歩を積み重ねることこそが、本当の“継続”なんですよね。
毎日100点を取ろうとするのではなく、70点を積み上げるイメージ。
そうすると、疲れすぎず、自分を責めずに続けられるようになりました。
「完璧じゃなくていい。続けることが力になる」――この言葉が、私の小さな合言葉です。
3. 夫婦で支え合う
「七転び八起き」は、ひとりではなく“誰かと一緒に”実践すると、より心強くなります。
特に家庭の中では、夫婦の関係がその土台になります。
夫婦の会話で意識しているのは、「責める」より「労う」こと。
「どうしてやってくれなかったの?」ではなく、「忙しいのにありがとう」「今日もお疲れさま」と声をかけるだけで、空気がやわらかく変わります。
人は、責められるより、認められるほうが“立ち上がる力”を取り戻せるんです。
お互いの頑張りを言葉にすることで、「次もがんばろう」というエネルギーが湧いてくる。
「支え合いの言葉」は、家族の中に小さな“再起の灯”をともす魔法だと感じています。
七転び八起きな生き方は、特別なことではありません。
失敗を笑い合い、昨日より少し前へ進み、感謝の言葉を交わす――その繰り返しが、家族全体の「起き上がる力」を育てていくのだと思います。
ことわざから学ぶ“転んでも起きる”心
昔から伝わることわざには、時代を越えても変わらない「人としての生き方のヒント」が詰まっています。
その中でも「七転び八起き」は、人生の浮き沈みをまるごと受け入れるような、やさしく力強い言葉です。
このことわざが伝えているのは、「転ばない人生なんてない」という大前提。
完璧に生きることを目指すよりも、転んだあとにどう立ち上がるか――そこにこそ、人としての強さや温かさが宿るという考え方です。
私たちの暮らしも、まさにその繰り返しですよね。
子どもが泣いて思うように家事が進まない日もあれば、頑張って作ったごはんを「いらない」と言われる日もある。
仕事でミスして落ち込むこともあれば、家族の体調不良が重なって自分の時間が持てないことも。
そんなとき、「なんでうまくいかないの?」と責めたくなる気持ちは自然なこと。
でも、「転ぶことも人生の一部」と考えられるようになると、心の持ち方が少しずつ変わってきます。
子育ての中にある“七転び八起き”
子育ては、まさに“七転び八起き”の連続です。
叱りすぎた、うまく向き合えなかった、イライラしてしまった――そんな後悔を繰り返しながらも、次の日には「よし、もう一度」とやり直す。
その姿を、子どもはしっかり見ています。
失敗しても、謝って、やり直す。
その一連の流れが、子どもにとっての「生きる力の教材」になっているのです。
「ママだって転ぶけど、ちゃんと起き上がってる」
そんな背中を見せることが、言葉以上の教育になる。
だからこそ、私たち親も完璧を目指すより、“転びながら進む”ことを恐れずにいたいですね。
家族の絆を深める“転倒”の瞬間
家族の中でも、意見がぶつかったり、気持ちがすれ違ったりすることはあります。
それもまた、一度転んで立ち上がるためのチャンス。
喧嘩したあとに「ごめんね」「ありがとう」と言葉を交わせたら、それは立派な“八起き”です。
転ばない関係ではなく、「転んでもまた手を取り合える関係」が、本当に強い絆を育てていくのだと思います。
振り返れば、私自身、「思い通りにいかない毎日」こそが、家族を深く結びつけてくれていました。
つまずきながら、何度も話し合い、助け合う中で、「一緒に成長していく家族」になっていく。
だから今では、完璧に進まない日も「これも大事な1ページ」と思えるようになりました。
転んでも起きる心。それは、強さではなく、やさしさのかたち。
そして、そのやさしさが、子どもにも「自分を信じて立ち上がる力」を伝えていくのです。
まとめ|転んでも起きる姿を、子どもと一緒に見せよう
七転八倒のように苦しむ日も、七転び八起きのように立ち上がる日も、どちらも「私の人生」。
大切なのは、転んだあとにどう立ち上がるか。
子どもは、親の背中を見て「生き方」を学びます。
今日も転んだなら、笑って「よし、もう一回!」と立ち上がってみましょう。
その姿が、きっと子どもの心に「起き上がる力」を灯してくれます。