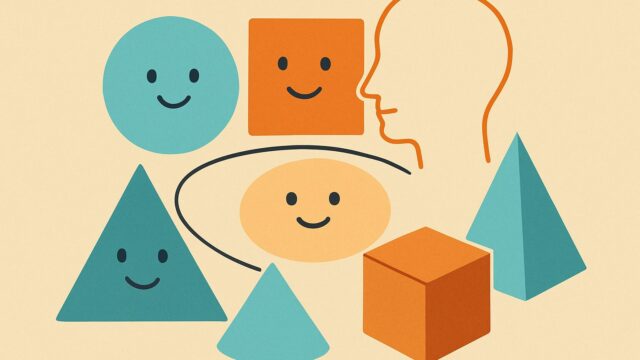影ってなぜできるの?子どもと試す簡単な観察あそび

「ママ、どうして影ができるの?」
ある日、夕方の公園で息子に聞かれたひとこと。そういえば私も子どものころ、長〜くのびた影が不思議で仕方なかったなぁ、なんて思い出しました。
日常のなかにある“当たり前”の現象も、子どもにとっては発見の連続。
この記事では、「影ってなぜできるの?」という素朴な疑問に、親子で楽しく向き合うためのヒントをまとめました。
難しい言葉は使わず、身近な例や簡単な実験を通して、「光と影のふしぎ」をわかりやすく解説していきます。
光があると、影ができる理由

子どもに「影ってなに?」と聞かれたとき、すぐに答えられそうでいて、意外とむずかしいものですよね。
私も最初は「うーん…黒い形ができるんだよ」と曖昧な説明しかできなくて、息子の「なんで?」が止まりませんでした。
でも、ある日一緒に実験をしてみたら、その疑問がパッと晴れたように理解してくれたんです。
やっぱり、“見てわかる”ってすごい力なんだなと感じました。
光をさえぎると、そこに影ができる
影ができる一番の理由は、「光をさえぎるものがあるから」です。
光はまっすぐ進む性質があるので、その途中に何か物があると、その背後には光が届きません。
たとえば、晴れた日の地面に注ぐ太陽の光。
その途中に人が立てば、その人の背中側には光が届かず、地面に人型の影ができます。
「光が止められて、その向こうが暗くなるんだよ」と伝えてもピンと来なかった息子に、懐中電灯とぬいぐるみを使って実演してみました。
ぬいぐるみの背後にくっきり映った黒い影を見た瞬間、「うわー!ほんとだ!ここ、光が届いてない!」と目をキラキラさせていました。
手のひらやコップ、積み木でもすぐに影が作れるので、ちょっとした“おうちサイエンス”にもぴったりです。
太陽はとっても強い“ライト”
「お日さまって、すごいライトみたいだね」と話すと、息子は「ぼくたちを照らしてるんだね!」と得意気に言ってくれました。
確かに、部屋の照明でも影はできますが、太陽の光は比べものにならないくらいパワフル。
そのぶん、できる影もくっきりはっきりとしています。
特に晴れた日の午前中や夕方、公園や道ばたを歩いていると、地面に自分の影が大きく伸びていたり、何かの形にそっくりな影が落ちていたり…。
「なんで今は長いの?」「あれは木の影だ!」と、歩くだけで発見がたくさんあります。
公園のすべり台の影が滑り台とまったく同じ形をしているのを見て、「すべり台の影だ〜!」と駆け寄った息子の姿がとても印象的でした。
影の形や大きさが変わるのはなぜ?
「さっきより影が長くなってる!」
夕方の帰り道、息子がふとつぶやいたひと言に、私は思わずハッとしました。
大人になると当たり前に感じてしまうこういう変化も、子どもにとっては大発見。
「気づけたことがすごいね」と声をかけたら、少し照れくさそうに笑っていました。
影はいつも同じ形ではありません。
実は、時間帯や光の当たり方によって、影の“長さ”や“向き”はどんどん変わっていくんです。
太陽の位置が変わるから
朝と夕方は影が長く、昼になると影が短くなる。
これは、太陽の高さ(角度)が関係しています。
地平線近くの低い位置から光が差すと、物の後ろに長く伸びる影ができます。
逆に、真上から光が当たるお昼時には、影は真下に小さく縮こまるように見えるんです。
「朝はお日さまが横のほうにあるから、影がなが〜くなるんだよ」
そう伝えると、息子は地面にできた自分の影をじーっと見つめていました。
数日かけて「朝・昼・夕」でそれぞれ影の写真を撮って、アルバムに並べてみたところ、「わ!全然ちがう!」と目をまるくしていました。
それからは毎朝、「今の影はどんなかな?」と自分の足元を見るのが習慣に。
ちょっとした日常の観察が、自然と学びにつながるんだなと、私もあらためて気づかされました。
光の角度で影はのびたりちぢんだり
この「影の変化」は、太陽じゃなくても体験できます。
わが家では、懐中電灯とおもちゃを使って、室内での“影あそび実験”もしました。
おもちゃに対してライトをいろんな角度から当てると、影の伸び方や向きが変わります。
上から照らすと、影は下に
横から照らすと、影は反対側に長くのびる
少し離れた場所から斜めに当てると、影の形がゆがむ
息子が「上からだと小さいけど、横からだとびよーんってなる!」と叫んだときには、私も「そうそう、それが太陽と同じ仕組みなんだよ」と思わず拍手。
実験中は「影がびっくりして逃げてるのかな?」なんて空想の世界に入って大笑いしていましたが、終わったあとに「だから夕方は影が長いのか〜」とぽつり。
子どもなりに、自分の言葉で納得している様子に成長を感じました。
影ってどんなところにできる?探してみよう

「ねぇ、影っておうちの中にもあるの?」
ある日、息子がそんなふうに聞いてきました。
たしかに、太陽の下でできる影にはよく気づくけれど、室内の影って意識して見ることは少ないかもしれません。
でも実は、よく見てみると…あるある!思わぬところにたくさんの影があったんです。
「よし、今日は“影探偵”になってみよう!」と声をかけて、影探しゲームがスタートしました。
家の中の影
まずはリビングからスタート。
・カーテン越しの光でできる家具の影
午後のやわらかい日差しが入ると、棚や椅子の影が床にぼんやり映っていました。
・洗濯物にできる小さな影
干してある靴下やシャツが風に揺れるたびに、壁に映る影もゆらゆら。息子は「影も踊ってる〜!」と笑っていました。
・机に当たるスタンドライトの影
夜に宿題をしていると、手やノートが光をさえぎって机の上に影ができていることに気づきました。
寝室のベッドフレーム、キッチンのやかん、冷蔵庫の扉…よく見ると、家じゅうのあちこちに“影のヒント”が散らばっていることに私も驚きました。
「ここにも!」「あっちにも!」と指さしながら歩く姿は、まさに小さな影探偵(笑)
ふだん見過ごしていた風景が、なんだかワクワクした探検の舞台に変わった気がしました。
外で見つける影
家の中に続いて、今度はお散歩しながら影を探すことに。
外には光と影の世界が広がっていて、まさに“影の宝庫”でした。
・木の影が風でゆれている
葉っぱの形がそのまま地面に映っていて、風に吹かれてチラチラ動くのをじっと見ていた息子。「木の手がいっぱいあるみたい!」と大興奮。
・すべり台の影が長く伸びている
公園に行くと、大きなすべり台の影が地面にぴったり同じ形で伸びていて、「すべり台がもうひとつあるみたい」と喜んでいました。
・犬や自転車の影まで!
犬のしっぽが影の中でぴょこぴょこ動いたり、自転車の車輪のスポークまで影に映っているのを発見。「こんなところまで映るの!?」とびっくりしていました。
途中で「人が通ったら、影が消えた!」とか、「この影は誰の?」とクイズを出したりして、ただのお散歩がすっかり“影の冒険”に。
「今日はどんな影に会えるかな?」と影を探すこと自体が、日々の楽しみのひとつになりました。
親子でできる!影の観察あそび
「影ってなぜできるの?」
そんな子どもの素朴な疑問に、言葉だけで説明しようとすると、ちょっとむずかしかったりしますよね。
わが家でも、最初は「光をさえぎると…」なんて一生懸命説明していたのですが、あまりピンとこない様子。
でも、実際に目の前で影を見せてあげた瞬間、「あ、わかった!」と表情がぱっと明るくなったんです。
やっぱり、子どもには“体感”がいちばん。
そこで、わが家では「遊びながら学ぶ」影あそびをたくさん取り入れています。
おうちでできる簡単実験
準備するのは、懐中電灯やスマホのライト、ぬいぐるみ、コップ、積み木など、家にあるものでOK。
暗めの部屋で壁に向かってライトを当てると、身近な物たちが次々と影絵の主役になります。
いろんな角度や距離から光を当てると、影の形がぐにゃっと変わったり、小さくなったり大きくなったり。
「さっきよりのびた!」「頭がないみたいに見える!」「影が2個あるー!」と、子どもの反応がとにかくおもしろい(笑)
観察のポイントは、「形・大きさ・向き」の変化に気づくこと。
ライトを近づけると影が大きくなり、遠ざけると小さくなる。
上から、横から、下から…角度を変えるたびに「影が逃げた!」「後ろにのびた!」と、まるで生き物を観察しているかのよう。
「影の世界っておもしろいね〜」と、親の私までつい夢中になってしまいました。
実験の後は、「光の強さを変えたらどうなる?」「2つのライトを当てたら影はどうなる?」など、ちょっと難しいテーマにも自然と関心が広がっていきます。
影あてクイズ
もうひとつ、盛り上がったのが「影だけで当てるクイズあそび」です。
ぬいぐるみやおもちゃなど、いろんな形のものを用意して、ライトで壁に影を映します。
子どもは影だけを見て「これはなーんだ?」と当てるゲーム。
はじめは簡単なものから、「クマ」「スプーン」「人の手」などを出していきます。
慣れてくると、似た形のもの(スプーンとフォーク、おさるのぬいぐるみとうさぎなど)を出して、「どっちだろう?」と難易度アップ!
息子は「うさぎだと思ったのに、おさるだった〜!」と悔しそうにしていましたが、そこから「耳の形の違い」をじっくり観察するようになって、「今度は絶対当てる!」とリベンジ。
影の形から本体を想像する力=“想像力”や“観察力”を自然と養うことができるのが、このあそびの魅力です。
さらに、「自分で出題してみよう!」と交代すると、どれを選んでどんなふうに映すか工夫するようになって、主体的な学びにもつながります。
少し電気を暗くして、影と光の関係を観察していると、なんだか秘密基地にいるみたいなワクワク感も。
親子の距離もぐっと近くなる、楽しい知育タイムになりますよ。
光と影の不思議をもっと楽しむヒント

影の仕組みがわかると、今まで当たり前に思っていた風景が、ちょっと違って見えてくるから不思議です。
「影があるってことは、そこに光があるんだね」
そんなふうに、子どもがポロッと口にした一言に、私自身もハッとさせられることがあります。
「なんで?」「どうして?」と一緒に考える時間は、何よりも貴重で、かけがえのないもの。
ここでは、光と影をもっと楽しく、もっと深く味わうための小さなヒントをご紹介します。
曇りの日には影がない?
ある日、「今日は影がないよ!」と息子が不思議そうにしていました。
外はどんより曇り空。たしかに、足元にはいつも見えていた自分の影が、まったく見当たりません。
「あれ?どうしてだろう?」と一緒に考えてみると、自然と空を見上げていました。
「実はね、太陽の光が雲にさえぎられて、いろんな方向にバラバラに散っちゃうんだよ。だから影がはっきり見えないの」
そう伝えると、「太陽が弱い日には、影もおやすみなんだね!」と可愛い解釈。
そこから「今日は影が休んでる日だね〜」「明日は戻ってくるかな?」と、曇り空もなんだか楽しいものに思えてきました。
天気と影の関係に気づくことで、自然現象にも関心が向いていくのを感じました。
影絵遊びで夜も楽しむ
「光がないと影はできない」
この大原則を、夜の遊びにも活かせるのが影絵あそびです。
電気を消して、小さなライトを壁に向けて手をかざすだけで、そこにはいろんな形の影が現れます。
まずは定番の「うさぎ」「鳥」「カニ」など、手で作る影絵を楽しんでみました。
慣れてくると、息子は「おばけ〜!」と自分で新しい影を生み出したり、おもちゃを使って動物の形を作ってみたり。
「いらっしゃいませ〜!影の世界へようこそ〜!」と、自分で影の世界の案内役になって、お話をつけてくれたことも(笑)
おやすみ前の時間に、電気を少し暗くして「影ショー」をすると、興奮しすぎずリラックスしながら過ごせて、寝かしつけにもぴったりです。
ライトの位置を少しずつ動かして、影の大きさが変わる様子を見せると、「おおきくなった!」「ちっちゃくなった!」と大盛り上がり。
ただの“遊び”が、立派な“学びの時間”になっているんだなと実感します。
ちょっとしたきっかけで、身のまわりの“ふしぎ”が、子どもにとっては大きな発見に。
そんな瞬間に立ち会えることが、親としては何より嬉しい時間です。
光と影――そのシンプルな関係が、親子の会話や遊びをこんなにも豊かにしてくれるなんて、私自身も驚いています。
まとめ|影は“光のふしぎ”を感じる入り口
子どもに「影ってなんでできるの?」と聞かれたとき、ちょっと難しそう…と感じるかもしれません。
でも実際は、光をさえぎることでできる“当たり前の現象”なんですよね。
むずかしく教えなくても、「一緒に見て、試して、考える」だけで十分。
親子で影を見つけたり、実験して笑ったりする時間が、きっと子どもの心に残るはずです。
今日の帰り道、ちょっとだけ足元の影を見てみませんか?
「光があるって、ありがたいことなんだなぁ」なんて、大人の私も感じるようになりました。