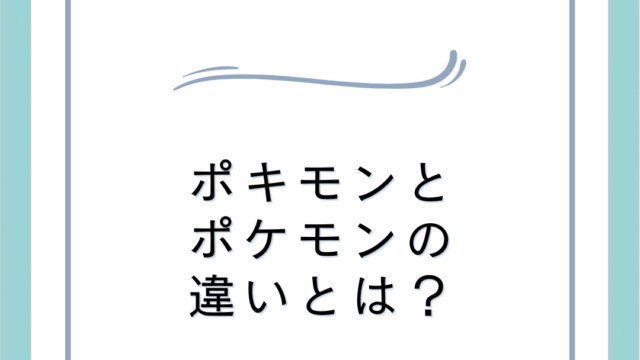音ってどうやって耳に届くの?親子で学ぶ耳の仕組み

「ねえママ、どうして声が聞こえるの?」
ある日、息子が突然こんな質問をしてきました。私も一瞬「え…どうだったっけ?」と答えに詰まってしまいました。
普段当たり前に聞いている音。でも、どうやって耳まで届いているのか、子どもに説明するとなると意外と難しいですよね。
今回は、親子で一緒に学べるように、音が聞こえる仕組みをわかりやすくまとめました。お風呂タイムや寝る前の会話ネタにもおすすめです。
音ってそもそも何?

空気が震えることで音になる
「音ってね、空気がブルブル震えることなんだよ。」
私が息子に説明すると、「えっ、空気が震えるの?!」と目を丸くしていました。
たとえば太鼓を叩くと「ドン!」と音がしますよね。このとき太鼓の皮が震えて、その震えが空気を伝わっていきます。その震えが耳に届くから、私たちは音として聞こえるんです。
息子はしばらく考えて、「じゃあ、太鼓が震えなかったら音しないの?」と聞いてきました。その通り。震えないと音は生まれないんですよね。
この話をしていると、息子は不思議そうに部屋の中を見回して、「じゃあ、このテレビの音も?ママの声も?冷蔵庫のブーンって音も?」と次々に質問してきました。
私は「そうだよ、全部空気が震えてるんだよ」と答えながら、改めて日常の音って全部空気の動きなんだなと実感しました。
そして息子は、「じゃあ僕がおならしたときの音も空気が震えてるの?」と一言。
「そうだね…あれも空気が震えてる音だね」と答えると、二人で笑ってしまいました。
おうちでできる簡単実験
我が家では、もっとわかりやすくするために、ラップをピンと張ったボウルの上に少し米粒を乗せて、近くで「わーーー!」と声をかける実験をしました。
すると、米粒がピョンピョンと跳ねて息子は大喜び。「空気が本当に動いてる!」と興奮していました。
さらに、太鼓の代わりに段ボール箱を叩いてみたり、スピーカーの前にティッシュを垂らして音楽をかけてみたり、いろんな方法で音が空気を震わせる様子を観察しました。
特にスピーカーの前にティッシュを近づけたとき、低音が鳴るとティッシュがふわふわ揺れるのを見て、「おおー!!」と目を輝かせていました。
この実験は準備も片付けも簡単なので、休日のちょっとした理科遊びにぴったりです。
私も「今日はどんな音の実験をしようかな」と考えるのが楽しみになっています。
耳の役割って何してるの?

音をキャッチする耳の仕組み
耳は、音の震えをキャッチするアンテナのようなもの。
外から入ってきた空気の震え(音)は、まず耳の外側(外耳)で集められ、耳の穴を通って鼓膜に届きます。
私も子どもの頃、「耳たぶって意味あるのかな?ただの飾りじゃないの?」と思っていましたが、耳の形ってとてもよくできていて、音を集めやすいようにカーブしているんですよね。
特に、耳たぶの上のほう(耳介)は、音を後ろからも前からも集めやすい形をしています。だから、私たちはいろんな方向から来る音を聞き分けることができるんです。
息子には「耳って、音を集めるじょうご(漏斗)みたいなんだよ」と説明すると、「じゃあママの耳は音じょうごだね!」と笑っていました。
鼓膜が震えるとどうなるの?
音の震えが鼓膜をブルブルと揺らすと、その奥にある小さな骨(耳小骨)も一緒に動きます。この耳小骨はとても小さいけれど、音をさらに増幅して奥へ伝える重要な働きをしているんです。
耳小骨は「ツチ骨」「キヌタ骨」「アブミ骨」という3つの骨でできていて、それぞれがリレーのように震えを渡していきます。
息子には「太鼓がブルブル震えて、その震えが小さな骨に伝わるんだよ」と話したら、「耳の中に骨があるの?!」とびっくりしていました。
「ツチとキヌタとアブミって、どれが一番強いの?」と聞かれて、「どれも強くて大事だけど、アブミ骨が一番小さいんだよ」と伝えると、「アブミって馬の足に履くやつでしょ?なんで耳の中にあるの?」と疑問が止まらない様子でした。
実際、アブミ骨は馬具のあぶみに形が似ているからそう呼ばれているそうです。
こういう雑学も一緒に伝えると、子どもの興味がぐんと広がっていきますよね。
音が聞こえないときはどうなるの?

音の通り道に問題がある場合
たとえば風邪をひいたときや、鼻が詰まっているとき、なんとなく耳が詰まったように感じることってありますよね。
これは、耳と鼻をつないでいる「耳管(じかん)」という管がうまく開かず、空気の流れが悪くなってしまうからなんです。
私も飛行機に乗ったときに耳が詰まった感覚になり、「ポーン」となるまで不快だった経験があります。
息子にも飛行機で耳が痛くならないように、飴を舐めさせたり、水を飲ませたりして予防しています。
また、子どもがよくかかる中耳炎も、音の通り道に影響を与える病気の一つです。
息子も保育園の年少さんのときに中耳炎になり、「ママの声が小さい…」と不安そうにしていたことがありました。
熱は下がっていても、耳の奥に水が残って聞こえにくい状態が続くこともあるため、ちゃんと耳鼻科で診てもらうことが大切だと感じました。
加齢や病気による難聴
大人になると、耳の中の細胞が減ったり弱ったりして、少しずつ聞こえづらくなることがあります。
特に高い音から聞こえにくくなることが多く、最初は「テレビの音が小さいな」と感じる程度でも、だんだん会話にも支障が出るようになる場合があります。
私の父も数年前から補聴器を使うようになりました。最初は「年寄りみたいで嫌だな」と言っていましたが、いざ使ってみると、「孫の声がよく聞こえる!」ととても嬉しそうでした。
補聴器をつけることで、家族との会話がスムーズになり、父の表情も明るくなったように感じます。
耳は一度悪くすると完全に戻ることが難しい器官だからこそ、日頃から大きな音を避けるなど、大切にしていきたいですね。
親子で耳を大切にするために

大きすぎる音に注意
子どもはタブレットやスマホで動画を見たり、ゲームをしたりすることが増えていますよね。
イヤホンで音を聞くと、周りの音が聞こえにくくなるのでついつい音量を上げがちです。
我が家でも、イヤホンを使うときは必ずボリュームをチェックしてから渡しています。
「大きな音は耳がびっくりしちゃうからね」と伝えると、「じゃあちょっと小さくする!」と自分で調整するようになりました。
一度イヤホンを耳に当ててみて、周りの人にも聞こえるくらい大きいときは要注意だそうです。
長時間聴き続けないよう、30分に一度は外して耳を休めるよう声かけもしています。
定期的な耳掃除よりも自然に任せる
私自身、小さい頃は母に耳掃除をしてもらうのが好きでした。
「ゴソゴソ…」という音や感触が気持ちよくて、寝てしまいそうになることもありました。
でも、耳鼻科の先生に「耳掃除はやりすぎると逆効果ですよ」と言われて驚いたことがあります。
耳の中はとても繊細なので、綿棒で掃除しすぎると傷がついてしまったり、逆に耳垢を奥へ押し込んでしまったりすることがあるそうです。
耳垢はもともと、外に押し出される仕組みになっているので、無理に掃除する必要はなく、気になるときだけ軽く入り口を拭き取る程度で十分とのこと。
それ以来、私も息子の耳掃除は「どうしても気になるときだけ」に変えました。
それでも最初は「ママ、今日は耳掃除しないの?」と少し寂しそうにしていましたが、耳を守るためだと説明すると納得してくれました。
音のある暮らしを楽しむ
最近は息子と一緒に、「今、どんな音が聞こえるかな?」と耳を澄ます時間を作っています。
家の中にいても、冷蔵庫の音や時計の針の音、遠くで聞こえる車の走る音など、意外とたくさんの音があることに気づきます。
夕方になると、庭の木にとまった鳥の声もよく聞こえて、「ママ、あの鳥の声、かわいいね!」と息子も音に興味を持つようになりました。
公園でも、「風で木がザワザワしてるね」「飛行機の音がするよ」と、ただ遊ぶだけじゃなく周りの音に耳を傾けることで、自然と集中力や感受性が育っているように感じます。
私自身も、音を意識するようになってから、日常が少し豊かになった気がします。
忙しい毎日だからこそ、こういう「音に耳を澄ます時間」を大切にしていきたいですね。
おうちでできる音の実験アイデア

コップと糸の電話
昔ながらの遊びですが、紙コップと毛糸で作る糸電話は、音の仕組みを学ぶのにぴったりです。
コップに小さな穴を開けて毛糸を通し、結び目を作って抜けないようにしたら完成。毛糸をピンと張って、お互いのコップに向かって「もしもしー!」と話してみましょう。
声を出すと、コップの底が震えて、その震えが糸を伝わってもう一方のコップに届きます。糸を伝わった震えは再びコップの底を震わせて、耳で音として聞こえる仕組みです。
息子も大喜びで、何度も「ママ、次は僕が言う番ね!」と遊んでいました。
途中で毛糸をたるませると声が聞こえなくなることに気づき、「ピンと張らないとダメなんだ!」と実験を通して学んでいました。
この遊びは家にあるもので簡単にできるので、雨の日のおうち時間や、理科の予習にもおすすめです。
水の中で声を出してみる
お風呂に入ったとき、水に顔をつけて「あーー」と声を出してみてください。
普段と違う、くぐもったような響き方がして、「うわっ、変な声!」と子どもは大笑いするはずです。
これは、水の中では空気中と音の伝わり方が違うために起こる現象です。
水のほうが空気よりも分子がぎゅっと詰まっているので、音の速さも早くなると言われています。ただ、私たちの耳は水の中の音をそのまま感じるのが難しいため、こもったように聞こえるんですね。
息子はこの実験が気に入ったようで、「お風呂でカエルの声みたいにしゃべれる!」と、毎晩お風呂が楽しい遊び場になっています。
こういった日常の中でできる簡単な実験は、子どもの「なんで?どうして?」を育てる最高のきっかけになると感じます。
まとめ|親子で音の不思議を楽しもう
音がどうやって耳に届くのかを知ると、毎日の生活がちょっと楽しくなりますよね。
私も息子と「今この音、空気が震えてるんだね!」と話すようになってから、虫の声や風の音に耳を澄ます時間が増えました。
ぜひ今日のお風呂や寝る前の時間に、子どもと一緒に「音ってどうやって聞こえるんだろうね?」と話してみてください。
きっと、日常の音がもっと特別なものに感じられるはずです。