義父母との関係づくりで変化!“ありがとう”が自然に増えた私の工夫
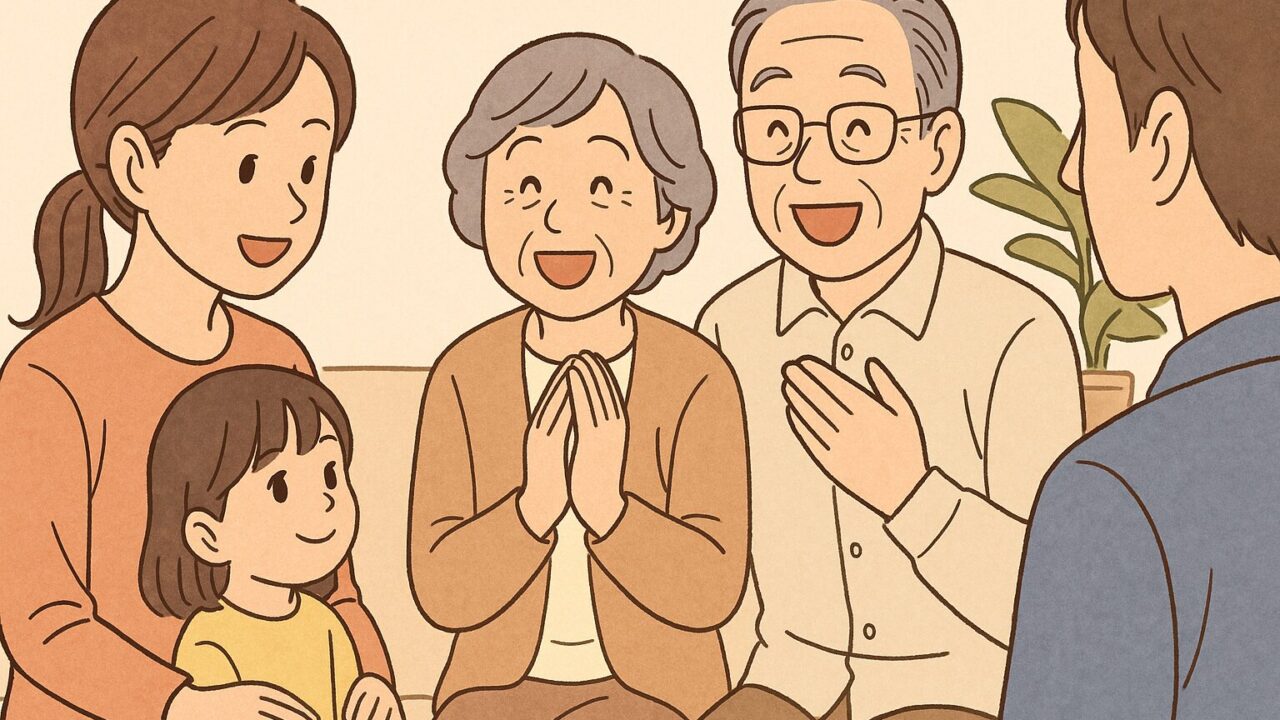
義父母との関係って、思った以上に難しくて、気を使いすぎたり、逆にモヤモヤが溜まったり…私もずっと「どうしたらうまく付き合えるんだろう?」と悩んでいました。
でも、あるきっかけを境に「ありがとう」と自然に言い合えるようになって、関係がすごくラクになったんです。
この記事では、私が義父母との関係を見つめ直し、少しずつ心地よい距離感を作っていけた体験をもとに、具体的な工夫や考え方をお伝えします。
義実家との距離感に悩んでいる方のヒントになれば嬉しいです。
義父母との関係に悩んでいた頃の私

私たちが結婚したのは、まだ20代の頃。義父母との関係は、正直「うまくいけばラッキー」くらいの気持ちで、深く考えていませんでした。
義実家には年に数回帰省し、形式的な会話を交わす程度。でもそれなりに穏やかに過ごせていて、「このまま距離を保ちながら付き合っていけば大丈夫だろう」と思っていたんです。
でも、子どもが生まれてから一気に関係が変わりました。
育児に口を出されてモヤモヤ
「まだ抱っこしすぎじゃない?」
「そんなに甘やかして大丈夫?」
「夜泣きのときは放っておいたほうがいいのよ」
初めての育児で毎日いっぱいいっぱいだった私にとって、義母の何気ないひと言が、まるで“ダメ出し”のように聞こえてしまったんです。
きっと悪気はなかったんだと思います。でも、その“正論”が苦しくて、「なんで私ばっかり責められるような気がするんだろう…」と涙が出そうになることもありました。
夫に相談してみても、「ああいう人だから気にしなくていいよ」「悪気はないんだって」と言われるだけで、私の気持ちが整理されるわけではありませんでした。
むしろ、「私の気持ちをわかってくれない」と、夫との間にまで距離を感じてしまうことも。
感謝の気持ちよりも、ストレスが先に立つ日々
本当は、孫をかわいがってくれている義父母には「ありがとう」って言いたい気持ちもあるんです。
おもちゃを買ってくれたり、会えば抱っこしてくれたり、離乳食の時期には手作りのスープを持ってきてくれたり…。ありがたいことをたくさんしてくれているのに、素直に受け取れない自分がいました。
「また何か言われるかも」
「こうしておいた方が喜ばれるかな?」
「でもそれって私のやり方じゃない…」
そんな風に、感謝よりも“先回りした不安”のほうが大きくなっていたんです。
次第に、「もうあまり関わらないほうが楽かも」と思うようになって、義実家に行くことも減り、連絡も必要最低限に。
でも、心のどこかでは「このままでいいのかな」とモヤモヤが残り続けていました。
私が変わるきっかけになった出来事
義父母との関係にずっとモヤモヤしていた私にとって、ある日のできごとが大きな転機になりました。
それは、娘の保育園の発表会の日のこと。初めての大舞台に向けて一生懸命練習していた娘の姿に、「せっかくだし、おじいちゃんおばあちゃんにも見てもらおうかな」と思い、義父母を招待することにしたんです。
正直なところ、「また何か言われるかもしれない」という不安はありました。でもそれよりも、「娘の成長を一緒に見届けたい」という気持ちが勝って、勇気を出して声をかけてみました。
義母の「ありがとう」にハッとした
当日は、おそろいのニコニコ顔で会場に現れた義父母。前列でスマホ片手に一生懸命撮影しながら、娘の出番には目を潤ませているようにも見えました。
発表会が終わって帰り際、私が「来てくださってありがとうございました」と何気なく声をかけたとき、義母がぽつりとこう言ったんです。
「呼んでくれてありがとう。ほんとに嬉しかったわ」
私は、その言葉に一瞬返事ができませんでした。
「ありがとう」と言うのは、いつも私の方じゃないといけないと思っていたし、義母は“する側”で私は“される側”だと思い込んでいたんです。
でもそのとき初めて、「義母も“ありがとう”を伝えたいと思ってくれてたんだ」と感じました。
思えば、義母だって気を使っていたのかもしれません。
どこまで口を出していいのか、どこまで踏み込んでいいのか、遠慮と心配のはざまで悩んでいたのかもしれない。私と同じように、どう接すればいいのか迷っていたのかもしれない。
そんなふうに思えた瞬間、それまで心の中にあった“壁”が、少しだけ取り払われたような気がしたんです。
「関係を変えてみよう」と思えるようになった
それまでは、「義母がこうしてくれたらいいのに」「言い方に気をつけてくれたらいいのに」と、どこか受け身だった私。
でも、発表会のあとから少しずつ、「私の方から関係を動かしてみようかな」と思えるようになりました。
完璧に仲良くなる必要なんてない。
でも、「ありがとう」を自然に言い合える関係になれたら、それだけでだいぶラクになるんじゃないか。
そんな風に考えられるようになってから、私自身の気持ちがすごく軽くなったのを覚えています。
うまく付き合うために工夫したこと

義父母との関係は、何かひとつのことで劇的に変わるわけではありませんでした。
少しずつ、試行錯誤しながら距離を縮めていった――そんな日々の中で、私なりに効果があったと感じる“関係づくりのコツ”をご紹介します。
1.「頼る」と「任せる」を意識してみた
今までは、「義父母に頼ると口を出される」「何か言われるのが怖い」という気持ちが強く、つい全部自分で抱え込んでいました。
でも、あるとき娘が熱を出し、保育園をお休みしなければならなくなったんです。私も夫も仕事を休めない状況で、本当に困ってしまって…。
思い切って義母に「今日、お願いできますか?」と連絡すると、即答で「もちろん!任せて!」と言ってくれました。
そのときの義母の声が、本当に嬉しそうだったんです。
心配はありました。おやつは何を出されるんだろう、テレビばっかり見せるんじゃ…って。でも、あえて“口を出さずに任せてみた”ことで、逆に義母の出しゃばりも減ったんです。
「信頼してくれてるって思うと、ちゃんとしなきゃって思うのよ」
あとからそう言ってくれた義母の言葉が、すごく印象的でした。
頼ること=負け じゃない。
頼ることって、相手との信頼を育てる一歩なんだなと感じました。
2. 夫を「通訳」としてうまく活用
義父母にどうしても直接言いづらいこと、ありませんか?
私の場合、たとえば「子どもに勝手に甘いものをあげてほしくない」とか、「帰省中は少しゆっくり寝たい」といった、ちょっとしたけど言いにくい要望が山ほどありました。
以前は我慢していたけれど、やっぱりモヤモヤが募ってしまう…。そんなときは、夫に“通訳役”をお願いするようにしたんです。
「私が言うと角が立つから、〇〇って伝えてもらえない?」と頼むと、夫は義母との関係をうまくわかっているので、柔らかく・やんわりと伝えてくれました。
たとえば、「〇〇(私)が疲れてるみたいで、少しゆっくりしたいって」とか、「あんまりお菓子食べさせると夕飯食べなくなるから、ちょっと控えめにしてもらえる?」など。
夫が“ワンクッション”になってくれるだけで、空気がピリつかなくなるんです。
私が直接言っていたら、もしかしたら関係が悪化していたかも…と思うようなことも、夫を通すことでスムーズに伝わり、義母の反応も全然違いました。
「家族だけど、やっぱり義理の関係って気をつかうよね」と夫と話しながら、ふたりで“どう関係をつくっていくか”を考えること自体が、夫婦にとってもプラスになったと思います。
3.「共通の話題」を育てていった
義父母との会話って、子どもがいるとどうしても「孫の話」中心になりがちですよね。
もちろんそれも大切なんだけど、子どもがいない場面では話題が途切れてしまう…そんな状況に、なんとなく気まずさを感じていました。
そんなとき、ふとしたきっかけで「共通の趣味」を育ててみようと思ったんです。
私が料理が好きだと知っていた義母が、「このレシピ、美味しかったのよ〜」と、切り抜いた料理記事を渡してくれたことがありました。
そのレシピを試して「すごく美味しかったです!」とLINEで報告したら、「ほんと?嬉しい!」とすぐに返事が来て、そこから食材の話や料理道具の話でやりとりが続くように。
LINEで写真を送り合ったり、おすすめの調味料を教え合ったり、“嫁と姑”という関係ではなく、“料理好き同士”としての関係ができはじめたんです。
共通の話題ができると、それが“接点”になって距離が一気に縮まります。
無理せず、でも諦めずに向き合うコツ
義父母との関係は、正直なところ、簡単なものではありませんでした。
「こうしたら仲良くなれる」といった明確な答えがあるわけでもなく、気をつかいすぎて疲れてしまったり、距離を取りすぎて罪悪感を感じたり…。感情の揺れがたくさんあるからこそ、“ちょうどいい距離感”を探るのに時間がかかるのだと思います。
でもだからこそ、私は思うようになりました。
無理はしなくていい。でも、完全に諦めるのはもったいない。
そんなふうに、肩の力を抜いてゆるやかに付き合うことが、長い目で見て一番ラクな関係づくりにつながるのではないかと感じています。
自分の「譲れないライン」も大切に
「仲良くしよう」と思うあまり、相手のやり方に全部合わせたり、なんでもかんでも我慢してしまうと、自分の気持ちが置き去りになってしまうんですよね。
私も最初は、義父母の意見を優先することが“良い嫁”だと思って、できるだけ波風を立てないようにしていました。でも、その積み重ねが、自分の中でモヤモヤや不満になっていたことに気づいたんです。
たとえば——
「子どもにスマホ動画を長時間見せるのはやめてほしい」
「家では21時には寝かせたいから、夜の予定は控えてほしい」
「お菓子の量はできるだけ管理したい」
これは“わがまま”ではなく、私たち夫婦が大切にしている育児の軸。だから、夫としっかり共有して、「ここは譲れないね」というラインを確認しあいました。
夫が理解してくれることで、義父母に伝えるときも「夫婦で決めたことなんです」と言えるようになり、心にブレがなくなった気がします。
自分を守ることは、相手を否定することではありません。
ちゃんと伝えることで、むしろ信頼関係が築けることもあるのだと、経験を通じて学びました。
“完璧な嫁”を目指さなくていい
結婚当初の私は、正直「いいお嫁さんと思われたい」「ちゃんとしてるって思われたい」と、かなり無理をしていたと思います。
義実家に行くたびに緊張して、食事の準備や片付けは率先してやらなきゃ…と気を張って、家に帰るとぐったりしていたのを覚えています。
でもあるとき、義母にこう言われたんです。
「そんなに頑張らなくていいのよ。疲れちゃうでしょう?」
そのときの私は、驚きと同時にちょっと涙が出そうになりました。
ああ、ちゃんと見てくれてたんだ。気づいてくれてたんだ――って。
それをきっかけに、少しずつ“がんばりすぎない自分”を出せるようになりました。
たとえば、「今日はちょっと体調が悪いので、少し横になりますね」と言ってみたり、「子どもが機嫌悪くて…すみません」と弱音をこぼせるようになったり。
すると、義母の方も「私も昔そうだったわよ」と共感してくれる場面が増えて、本音で話せる関係に近づいていった気がします。
関係が変わると「ありがとう」が自然に増えていく

気づけば最近、義父母に「ありがとう」と言う機会が増えていました。
以前は、どんなに助けてもらっても「何か言われるかもしれない」「また距離が縮まりすぎてしまうかも」と、どこかで“感謝の言葉”すら飲み込んでいた私。
でも、関係が少しずつ変わってきたことで、その「ありがとう」が自然と口から出るようになったんです。
小さな“ありがとう”が積み重なっていった
たとえば…
保育園のお迎えを頼んだとき
→「本当に助かりました、ありがとうございます」と素直に伝えられるようになった。ごはんやお惣菜を持たせてくれたとき
→「わぁ、うれしい!今日すごく助かります」と喜びを込めて伝えられた。子どもの成長を見て「大きくなったね」「頑張ってるね」と言ってくれたとき
→「そうなんです、最近ちょっとずつできることが増えてきて…」と、笑顔で会話が弾むようになった。
どれも、特別な場面ではありません。
でも、以前の私ならどこか身構えていたような瞬間に、「ありがとう」の気持ちをちゃんと伝えられるようになったことが、自分でも嬉しかったんです。
感謝の言葉が、関係の“空気”をやわらかくしてくれた
不思議なもので、「ありがとう」って、自分のためにもなる言葉なんだなと感じています。
感謝の気持ちを伝えると、義母はいつも照れたように「いいのよ〜」と返してくれます。
義父も「そんなこと言われるなんて久しぶりやな」と嬉しそうに笑ってくれたこともありました。
感謝されると、人ってやっぱり嬉しいんですよね。
そしてその表情を見た私も、「ああ、伝えてよかった」とあたたかい気持ちになる。
「ありがとう」がひとつ増えるだけで、場の空気がふっとやわらかくなる。
関係が良くなるって、こういう積み重ねなんだなと実感しています。
感謝は、完璧な関係じゃなくてもできること
正直、今でもすべてがうまくいっているわけではありません。
意見の違いもあるし、考え方にギャップを感じることもあります。
でも、それでも「ありがとう」と伝えられる場面を逃さずに言葉にする。
たったそれだけのことが、義父母との関係をより穏やかに、心地よくしてくれると感じています。
完璧じゃなくていい。だけど、丁寧に関わろうとする気持ちがあれば、関係はちゃんと育っていく。
それを教えてくれたのは、毎日の中で少しずつ重ねてきた「ありがとう」だったのかもしれません。
まとめ|義父母との関係は“育てるもの”
義父母との関係づくりは、スタート地点がどんなにぎこちなくても、「こうなりたい」という気持ちがあれば、少しずつ変えていけるものだと思います。
私自身、「苦手かも…」と思っていた関係が、今では「頼れる存在」に変わりました。
完璧じゃなくていい。
でも、ちょっとだけ踏み出してみる。
その積み重ねが、“ありがとう”のある関係につながっていくと、心から感じています。
もし今、義父母との関係で悩んでいるなら、まずは小さな「ありがとう」を伝えることから始めてみてください。
きっと、少しずつ風向きが変わっていくはずです。














