家計簿が続かない理由と私の解決策|三日坊主でも続いたシンプル習慣

「今年こそ家計簿を続けるぞ!」と意気込んだものの、気づけば数日でストップ…。
私は何度も同じことを繰り返してきました。
家計簿アプリを入れてみたり、ノートを可愛くデコったりもしたけれど、続かない理由はそれだけじゃなかったみたいです。
でも、あるとき気づいたんです。
「完璧を目指すより、“ざっくり”のほうがうまくいく」ってことに。
この記事では、私がどうして家計簿を続けられなかったのか、その理由と向き合いながら、「やっと続けられた工夫」についてお話しします。
子育てや仕事に追われながらでも、ムリなく続けられる方法を探している方の参考になれば嬉しいです。
家計簿が続かない理由って?

時間が取れない・後回しになる
仕事に家事に育児…。
朝起きた瞬間からバタバタで、気づけばもう夕方。
子どもを寝かせてホッと一息ついたころには、自分もクタクタ。
「今から家計簿?いや、今日はやめておこう…」
そんな日が続いて、あっという間にレシートが山積みに。
週末にまとめてつけようと思っても、今度は家族の予定や買い物、掃除や作り置きでまたバタバタ。
「時間ができたらやろう」なんて言ってる間に、レシートの日付が一週間以上前になっていることもよくありました。
そして、こうなるともうやる気が失せてしまって…。
「いったんリセットして来月からまたやろう」と思うけど、翌月も同じことの繰り返し。
家計簿って“時間がある人”だけのものなの?
そんな風に感じて、どんどん遠ざかっていきました。
細かく書こうとしすぎて疲れる
最初はモチベーションもあって、「今回はちゃんと続けよう!」と意気込んでいました。
食費、日用品、外食、レジャー…細かく項目分け
クレジットと現金を分けて記録
ポイント支払いも書き足して
1円単位で電卓を叩いて…
自分でもよく頑張ってたと思います(笑)。
でも、それができるのってせいぜい3日。
そのうち、1つ1つの記録がどんどん面倒になっていって。
「買ったものの内訳をどう分けるか悩む」
「アプリのカテゴリーが多すぎて選ぶのに疲れる」
「結局、何のためにつけてるんだっけ?」
家計簿が“お金を管理するための道具”じゃなくて、
“数字を正確に並べるための作業”になっていたんですよね。
私の場合、「ちゃんとやろう」と思いすぎるほど、続かなくなっていくという悪循環に陥っていました。
家族の出費が見えづらくてモヤモヤ
うちの家計は「共有財布」でも「完全に分ける」でもなく、なんとなく“曖昧な管理”。
たとえば、
スーパーの買い物は私が現金で払うことが多い
日用品は夫がAmazonでまとめ買い
外食はその場のノリで「今日はどっちが出す?」みたいな感じ
こんなふうにルールが定まっていないから、家計簿をつけようとすると混乱するんです。
「この支出って、家計として記録していいの?それとも夫の個人出費?」
「夫が買った日用品って何だったっけ?またティッシュ10箱セットとか?」
「クレカの明細に“Amazon”ってあるけど…これ何だっけ?」
聞こうと思っても、タイミングが合わなかったり、「なんでそんな細かく?」って空気になってしまったり。
家計簿って、本当は「家族の支出を見える化するツール」なのに、
我が家では逆に「見えないことにイライラする原因」になっていたんです。
結果、「正確に記録できないなら、もうやらなくていいか…」という気持ちに。
そんな風に、だんだん家計簿から気持ちが離れていってしまいました。
私が“家計簿”を続けられるようになった3つの工夫
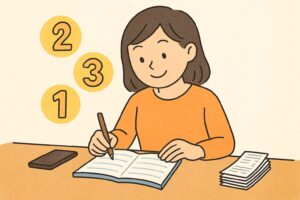
1. 書くのは「お金を使ったとき」だけにした
家計簿をつけるとき、「給料日」「カードの引き落とし」「ポイント払い」などもすべて書こうと頑張っていた時期がありました。
でも、そうすると記録の量がどんどん膨れ上がって、家計簿が「手間のかかる作業」になってしまうんですよね。
しかも、記録するたびに「まだやってない」「あれも書かなきゃ」と頭の片隅で気になって、心の負担にもなっていました。
そこで私は思いきって、“支出だけ記録するスタイル”に切り替えました。
たとえば、
スーパーで2,000円使ったら、買い物袋を下ろす前にスマホにメモ
Amazonで買い物したら、注文完了画面をスクショして「買った日・金額・目的」を簡単にメモ帳へ
自販機でジュースを買ったら「120円・飲み物」とメモするだけ
とにかく、「使った瞬間に1アクション」がルールです。
収入や引き落としの管理は別にアプリで確認すればいいので、無理に家計簿に全部まとめようとしなくていい。
この割り切りが、私にとってはとても大きな転機になりました。
“全部記録しよう”をやめたことで、気持ちが一気にラクになったんです。
2. 1週間単位で“ざっくり集計”
毎日コツコツつけられたら理想だけど、現実的には難しい…。
子どもの寝かしつけで一緒に寝落ちしてしまう日もあるし、残業でバタバタした日はレシートを出すのすら面倒に感じることも。
だから私は、「週に一度だけまとめて振り返る」方法にしました。
平日はとにかくざっくりと
スマホのメモ帳に「7/3 スーパー 2,134円」「7/5 コンビニ 380円」みたいに金額だけ記録
レシートは財布に入れておくだけ(整理しなくてOK)
そして週末、ちょっとゆっくりできる時間に
ノートに1週間分を書き出して、「食費」「日用品」「その他」の3つに分けて集計
大きく使った項目にマーカーを引いて、来週気をつけたい点を一言メモ
たとえば、
「今週はお菓子に1,200円も使ってた。平日は買わないようにしよう」
「日用品が少なくて済んだから、来週はちょっと余裕があるかも」
こんなふうに、“数字を振り返る時間”が持てると、家計を整える意識が自然と高まります。
完璧に記録することより、週に一度の「自分チェックタイム」が大切でした。
3. 「予算」より「気づき」を大事にした
家計簿といえば、「月5万円以内に食費をおさえる」など、予算を立てて管理するイメージがありますよね。
私も最初はそうしていました。
でも、何度やってもうまくいかなくて、予算を超えるたびにガッカリしていました。
たとえば、予定外の来客があってお惣菜を多めに買った日や、子どもの誕生日でプレゼント代がかさんだ月。
それだけで「今月も赤字…」と落ち込み、続けるのがイヤになってしまったんです。
だから、今は「予算を守ること」より「気づきを得ること」を目的に切り替えました。
具体的には、
お菓子やジュースにいくら使ったか見て、「ちょっと多いな」と気づければOK
コンビニ利用が増えていたら、「今週は疲れてたな…」と振り返る
無駄づかいに気づけたら、「次はやめよう」と意識するだけでも十分
数字に追われるんじゃなく、暮らしを見つめる道具として家計簿を使えるようになったのは、この考え方のおかげです。
家計簿を「自分の味方」にするために意識したこと

比べない、落ち込まない
家計管理を頑張っていると、ついつい周りの情報に目がいってしまうことってありませんか?
私もよくSNSで、
「今月は支出を2万円に抑えました!」
「ついに貯金100万円達成!」
「家計簿で夫婦のお金の使い方が改善!」
…なんて投稿を見ては、「私もちゃんとやらなきゃ」「なんでうちはうまくいかないんだろう」と焦っていました。
でもよく考えると、家庭によって収入も支出も生活スタイルもまったく違います。
子どもの人数や年齢、住んでいる場所、親のサポートがあるかどうか――条件が違えば、当然お金の動きも違って当然。
他の人の家計簿を見て「すごいな」と思うことがあっても、それをそのまま自分に当てはめる必要はないんですよね。
そう思えるようになってから、「できてない自分」を責めることが減りました。
むしろ、「今月はちょっと頑張れたな」と小さな達成感を味わえるようになってきたんです。
「見える化」で気持ちもスッキリ
家計簿って、ただの「節約ツール」じゃなくて、“自分の気持ちを整理する鏡”みたいな役割もあるなと感じています。
たとえば…
子どもの急な発熱で病院代や薬代がかさんだとき
週末に疲れて外食が続き、食費が予算オーバーしたとき
誕生日や記念日が重なってプレゼント代が多くなった月
「また赤字か…」と落ち込むこともありましたが、家計簿を見返して、
どんな状況で
何にお金を使って
なぜ予算オーバーしたのか
を“見える化”するだけで、なんとなく気持ちが落ち着くんです。
「そりゃ仕方なかったよね」
「がんばった自分、えらいよ」
って、家計簿がそっと背中を押してくれるような感じ。
お金の使い方って、自分の気持ちや生活そのものが映し出されるものなんですね。
だから私は、「家計簿は反省の道具」じゃなくて、「暮らしを振り返って、前を向くためのツール」だと考えるようになりました。
今では、ちょっとモヤモヤしたときこそ、家計簿を開いて心を整えることもあります。
数字と向き合うことが、心と向き合う時間にもなっている気がします。
家計簿アプリ・手書き・エクセル…どれが自分に合ってる?

私は「手書き+スマホメモ」のハイブリッド派
正直に言うと、私はこれまでに何度も「自分に合う家計簿のつけ方」を探してきました。
雑誌で見かけた「ノート家計簿」に挑戦してみたり、SNSで人気のアプリを使ってみたり、エクセルテンプレートをダウンロードしてみたり…。
でも、どれも数日〜数週間で挫折。
「家計簿って続かないものなんだな…」と諦めかけていたとき、ようやくたどり着いたのが今のスタイルです。
それは、「スマホでメモ → 週末にノートで振り返り」という、ハイブリッドなやり方。
普段はとにかく手間をかけずに、スマホのメモ帳に“使った金額と一言メモ”だけ書いています。
たとえば、「7/10 スーパー 2,300円」「7/12 Amazon おむつ」など。
そして週末、時間があるときにノートを開いて、
- 1週間分の支出をまとめて記録
- 「食費・日用品・その他」にざっくり分けて合計
- 特に使いすぎた項目に色をつけて、ちょっとだけ振り返り
この“ゆる記録+週末のんびり振り返り”が、私にはとても合っていました。
アプリでは細かすぎて疲れてしまった私でも、ノートだと自由に書けるから、気づけばちょっとした日記みたいになっていて、むしろ楽しみにすらなっているんです。
それぞれのメリット・デメリット
家計簿のスタイルは、本当に人それぞれ。
性格や生活リズムによって「合う・合わない」があるので、いろいろ試してみるのもおすすめです。
以下に、3つの代表的な方法の特徴を表にまとめてみました。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| アプリ | 自動連携でラク/グラフ表示が便利 | 項目設定が細かくて挫折しがち |
| 手書き | 記録が記憶に残る/自由に書ける | 手間がかかる/持ち歩けない |
| エクセル | 集計が楽/カスタマイズ自由 | PCを開かないと見られない/手軽さに欠ける |
それぞれ、こんな人におすすめです
- アプリが合う人
→ スマホ操作に慣れていて、数字を見て分析するのが好きなタイプ。
→ 家計の“見える化”をグラフで一目で確認したい人にもおすすめ。 - 手書きが合う人
→ 書くことで気持ちが整理されるタイプ。
→ 自分の言葉で自由に記録したい人。
→ 紙の手帳が好きな人にも向いています。 - エクセルが合う人
→ 計算や表づくりが得意で、集計や分析が苦にならないタイプ。
→ 月単位での比較や、年間収支の把握をしたい人には便利です。
私の場合は、アプリの“項目を選ぶ手間”がストレスになってしまい、
エクセルも「あとでまとめてやろう」が続いて結局開かなくなる…。
そんな経験を経て、「スマホでとにかく簡単にメモ→ノートで自由に振り返り」という形にたどり着きました。
まとめ|「完璧じゃなくていい」から続けられる
家計簿って、最初は“節約のためのツール”だと思っていたけれど、今は「家族の暮らしを見守る鏡」みたいな存在になっています。
気合いを入れて始めても、続かなければ意味がない。
だからこそ、「ざっくり」「ゆるく」「自分に合った形」で続けることが大事なんだと、やっと気づけました。
もし今、家計簿が続かなくて悩んでいるなら、
「1円単位まで正確に」「全部を記録しなきゃ」って考えを、いったん手放してみてください。
今日から“自分にやさしい家計簿”を始めてみませんか?
小さな一歩が、きっと大きな安心につながっていきます。














