九九 覚え方でつまずく子必見!親子で楽しく覚える効果的ステップ完全ガイド
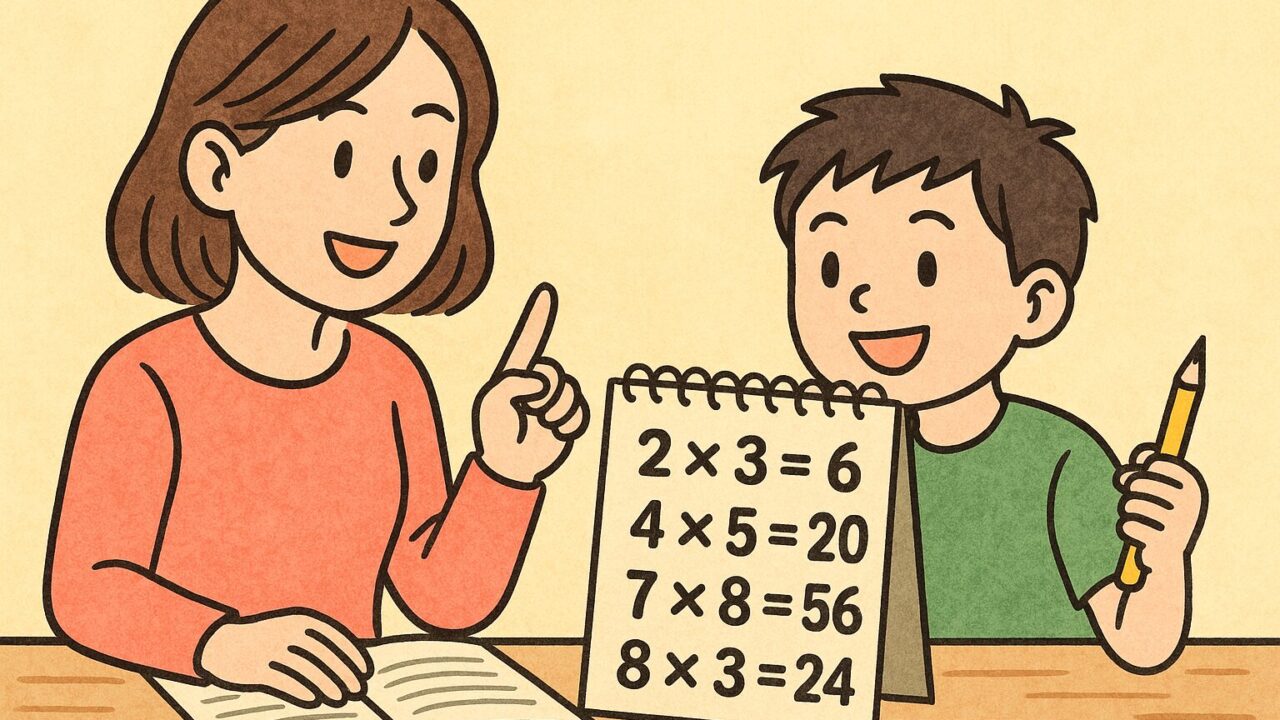
小学校で習う「九九」。覚えられないと算数の授業や日常生活でちょっと不便…とわかってはいるものの、わが子がなかなか覚えられずに困ってしまった経験、ありませんか?
わが家でも小2の娘が九九を習い始めたころ、最初は「楽しい!」と張り切っていたのに、途中から「もうイヤ!」と練習を拒否する日が続きました。
今回は、私が試して効果のあった九九の覚え方や、つまずきやすいポイントの乗り越え方をまとめます。親子で無理なく、そして楽しく覚えられる工夫をお伝えします。
九九を覚える前に知っておきたいこと

九九は「1×1」から「9×9」までの計算を暗記することがゴールではありません。
もちろん丸暗記は必要ですが、それだけでは時間が経つと忘れてしまう子も多いです。そこで、九九を定着させるためには、暗記の裏にある「パターン」に気づかせることが大切です。
たとえば「2の段はすべて偶数になる」「5の段は末尾が0か5になる」など、規則性を発見すると記憶の引き出しが増え、思い出すスピードも上がります。これは理屈がわかることで脳の「理解」と「暗記」が同時に働くからです。
九九は生活の中で使うもの
九九は教科書だけの知識ではなく、日常生活のあらゆる場面に溶け込んでいる計算スキルです。
スーパーでの買い物中、「3個100円のリンゴを2つ買ったらいくら?」という会話が自然に出てくれば、それは九九の活用そのもの。お料理の計量スプーンや材料の倍量計算、工作での寸法計算など、家庭内でも活躍する場面は数え切れません。
私の娘の場合、「九九は算数のテストのためだけのもの」という認識が強く、なかなかやる気が出ませんでした。でも、おやつのチョコを人数分に分けるときや、トランプでカードの合計点を計算するときに九九を使うと、「九九って便利!」と目を輝かせるようになったんです。
こうして「覚えるために九九を使う」のではなく、「使うために九九を覚える」という順序に変えると、学びのモチベーションが大きく変わります。
苦手意識を持たせない環境づくり
九九に限らず、「できない」という気持ちが強くなると学習が止まってしまうことがあります。
私がやってしまった失敗は、「ちゃんと覚えなきゃダメでしょ!」とつい口にしてしまったことでした。これは大人からすると「励まし」のつもりでも、子どもにとっては「責められている」と感じることがあります。
九九に苦手意識を持たせないためには、
間違えてもすぐに直さず、「どこが違ったかな?」と一緒に考える
一度に長時間やらず、短い時間を毎日続ける
成功体験をたくさん積ませ、「できた!」の喜びを増やす
この3つを意識するだけで、九九への取り組み方が前向きになります。
我が家では、正解するたびにハイタッチをするようにしたら、娘のほうから「九九やろう!」と誘ってくれる日も増えました。
覚えやすい順番で進める
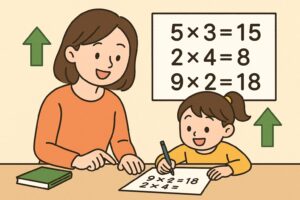
学校では多くの場合、「1の段」から順に覚えていきますが、これは必ずしも全員に合った方法ではありません。
九九の習得は「順番通り」よりも、子どもが覚えやすい順番で進めるほうが効率的で、モチベーションも維持しやすいのです。
たとえば、数字やパターンに興味を持ちやすい子は、最初から難しい段でもスムーズに入れる場合がありますし、逆にコツコツ型の子は簡単な段から積み上げるほうが安心して学べます。
得意な段から始める
うちの娘の場合、最初にマスターしたのは「5の段」でした。理由はとても単純で、「手で数えやすい」からです。
5、10、15…と5ずつ増えていくため、指を折りながら数えると答えにたどり着きやすく、達成感も味わいやすいのです。
この「自分にもできる!」という初期の成功体験はとても大切です。
一度でも「私って九九できるんだ」と感じると、その勢いで他の段にも挑戦しやすくなります。逆に、苦手な段から始めてしまうと、「九九は難しい」という印象が先に残り、やる気が落ちてしまうこともあります。
覚えやすい段の例と理由
2の段
偶数が並び、リズム感が取りやすい段です。数の並びがシンプルなので、繰り返しやすく、初めて九九に触れる子でも覚えやすい特徴があります。5の段
答えの末尾が必ず0か5になるため、答えを推測しやすい段です。日常生活でも「5個単位」「5分刻み」など、身近な感覚に近いのも覚えやすさのポイントです。9の段
少し難しそうに見えますが、実は数字の並びに規則性があります。答えの十の位は1ずつ増え、1の位は1ずつ減る(例:9、18、27、36…)。この法則に気づくと、暗記というより“発見”として覚えられるので、意外と子どもウケが良い段です。
順番を変えるメリット
順番を変えることで、子どもが「できる感覚」を早い段階で持てるのが最大のメリットです。
九九の練習は繰り返しが前提ですが、「もうできない…」という気持ちより「もっとやりたい!」という気持ちを先に育てることが習得の近道になります。
我が家では、まず5の段→2の段→9の段の順で覚え、そのあと1の段や3の段に移りました。結果的に、最初から順番通りにやるより短期間で全段を覚えることができました。
リズムや歌を活用する

九九は単調に暗記しようとすると飽きやすく、覚えたと思っても忘れてしまうことがあります。そこで効果的なのが、メロディーやリズムとセットにして覚える方法です。音楽や体の動きが加わると、脳の記憶の仕組みが活性化し、長く定着しやすくなります。
歌に合わせて覚える
昔からある「九九の歌」はもちろん、今はYouTubeや音楽配信サービスにもさまざまなテンポやアレンジの九九ソングが揃っています。
たとえば、ゆっくりテンポでじっくり練習するバージョンや、アップテンポで楽しく盛り上がるバージョンなど、子どもの好みに合わせて選べるのが魅力です。
私の娘は、朝の支度中や車での移動中に九九ソングを流すことで、無意識のうちに口ずさむようになりました。「勉強するぞ!」と意識しなくても耳から自然に入るのは、歌の大きな強みです。
手拍子やジャンプと組み合わせる
座ってじっと覚えるのが苦手な子には、体を動かしながら覚える方法が効果的です。
手拍子を打ちながらリズムに合わせて九九を言うと、自然とテンポが身につき、つまずきにくくなります。さらに、ジャンプや足踏みを加えると全身を使うので、楽しい運動遊びのような感覚で続けられます。
たとえば、「さんいちがさん!」で1回ジャンプ、「さんにがろく!」で2回手拍子など、ちょっとしたルールを作るとゲーム性が増して飽きません。
リズム学習のメリット
記憶に残りやすい(歌や動きは長期記憶に残りやすい)
練習のハードルが下がる(遊び感覚で取り組める)
集中力が続きやすい(動きがあることで飽きにくい)
九九を覚えるとき、「何回も書く」よりも「何回も口に出すほうが覚えやすい」子もいます。特に聴覚や身体感覚で覚えるタイプの子には、歌とリズムを活用する方法は非常に相性が良いです。
つまずきやすいポイントと克服法

九九の練習をしていると、多くの子が同じような場所で立ち止まります。すべての段を均等に覚えるのではなく、「覚えやすい部分」と「覚えにくい部分」の差があることを前提に、集中的にアプローチすることが大切です。
7の段・8の段の壁
特に多くの子どもが苦手とするのが、7の段と8の段です。
理由はいくつかあります。
数字が大きくなり、暗算の負荷が増える
リズムに規則性を感じにくい
7×8や8×7など、似たような組み合わせで混乱しやすい
我が家の娘も、7×8と8×7がなかなか覚えられず、何度練習しても途中で止まってしまうことがありました。
克服のためにやったこと
覚えにくい式だけカードにして繰り返し練習
全体を通して練習するよりも、苦手な組み合わせだけをピンポイントで集中的に練習するほうが効果的です。
小さなカードに式を書き、家のあちこちに置いておくと、隙間時間にもパッと確認できます。冷蔵庫や洗面所の鏡など、毎日目に入る場所がおすすめです。
1日5問だけ集中してやる
「九九を全部やらなきゃ」と思うと、子どもは負担を感じやすいです。
そこで、1日5問だけに絞り、その代わり集中して取り組む時間を作りました。短時間で終わるため、嫌がらずに続けられます。
正解したら大げさに褒める
正解した瞬間に「おぉー!天才!」と少しオーバーなくらい褒めると、子どもはうれしそうに笑い、その後のやる気が一気に上がります。褒められる経験は「やればできる」という自己肯定感に直結します。
間違いを責めない
九九の練習で一番避けたいのが、間違いを責めることです。
「なんでできないの?」という言葉は、やる気を削ぎ、九九そのものに嫌なイメージを植え付けてしまいます。
間違いは「まだ覚える途中のサイン」だと考え、できなかった式を次の目標に設定するほうが前向きです。
そして、次にできたときにはしっかり認めてあげること。娘の場合、「昨日できなかったのに今日はできたね!」と声をかけたら、自分でも誇らしげな表情を見せてくれました。
親の関わり方が鍵
九九のつまずきは、子どもだけの問題ではありません。親の接し方ひとつで、覚えるスピードや意欲は大きく変わります。
苦手な段は一緒に声に出して練習する
正解・不正解に関わらず「やったね」「頑張ったね」と声をかける
「間違えないこと」よりも「続けること」を重視する
こうした関わり方を意識すると、九九の習得はずっとスムーズになります。
日常の中で九九を使う習慣

九九を覚えるために机に向かって練習する時間も大切ですが、それだけでは「九九=勉強」という枠から抜け出せず、覚えた知識が生活の中で活かされにくくなります。
実は、日常生活に九九を自然に取り入れることで、暗記ではなく「使える知識」として定着させることができます。
お手伝いと九九
お手伝いの中には、九九を使うチャンスがたくさんあります。
料理中なら「卵3パックで何個?」(3×10)、お買い物なら「このお菓子を4人分買うといくら?」(単価×人数)など、計算を必要とする場面が自然と出てきます。
このときのポイントは、「九九をやらせる」というより「計算が必要な状況を作る」こと。
子どもが自分から計算しようとする場面を作ると、「覚えるため」ではなく「使うため」に九九を身につけられるので、記憶への定着が早くなります。
我が家では、スーパーで「今日は○円以内でおやつを買おう」とルールを作り、価格の合計を計算させることがありました。九九がすぐに出てくるようになると、子どもは買い物の主導権を握ったような気分になり、とても嬉しそうでした。
家族でゲーム感覚に
九九は遊びに変えると長続きします。我が家で定番だったのが「九九しりとり」です。
ルールは簡単。たとえば「3×4=12」の12の1の位「2」から始まる九九の式(2×…)を次の人が答える、というものです。
これを家族全員でやると、「次は何が出るかな?」とワクワクしながら自然に九九を口に出すことになります。
間違えても笑い合える雰囲気にしておくと、九九に対するプレッシャーがなくなり、「間違えてもいいから挑戦する」姿勢が育ちます。
生活習慣に組み込むコツ
九九を生活に取り入れるときは、次のポイントを意識すると効果的です。
同じ時間やタイミングで行う(習慣化しやすい)
親も一緒に参加する(子どもだけにやらせない)
正解だけでなく、答えを出そうとする過程も褒める
この方法なら、机の上だけで練習するよりもずっと楽しく、しかも長期的に記憶が残りやすくなります。
まとめ|九九は「覚える」より「楽しく使う」から始めよう
九九の覚え方は、順番や方法に正解があるわけではありません。
子どもの得意な段や好きな方法から始め、リズムや歌、日常生活での活用を取り入れると、覚えるスピードもグッと上がります。
まずは「楽しい!」「できた!」という気持ちを大切にして、親子でゲーム感覚で進めてみてください。














