扇風機とヒーターの季節家電出し入れ完全ガイド

季節が変わるたびにやってくる、「季節家電の出し入れ」問題。
「まだ暑い日があるし扇風機は出しておこうかな」「ヒーターってもう出して大丈夫?」と、毎年なんとなく悩んでしまう私。とくに子どもがいると、体調管理にも関わるから慎重になってしまいますよね。
今回は、わが家の“出し入れの目安”や、収納をラクにする工夫、家族とのやり取りも交えながらご紹介します。同じように迷っている方のヒントになればうれしいです。
季節家電って、なぜ出し入れが面倒?

季節の変わり目になると、「あ、そろそろアレ出さなきゃ…」と気づくものの、腰が重くなるのが季節家電。
わが家でも毎回、「押入れの奥にしまった扇風機、出すの面倒だな…」とつぶやいています。
よく考えると、“すぐに使いたい”気持ちと“準備の手間”が釣り合っていないんですよね。
エアコンのように年中使う家電とは違って、「数ヶ月のためだけに大きなものを出し入れする」のが、なんとなく億劫に感じる原因かもしれません。
子どもがいると判断がむずかしい
体温調節が苦手な子どもにとっては、ちょっとした寒暖差が体調に響きます。
「急に冷え込んだ日」や「予想外の暑さ」があると、タイミングの見極めが難しくなります。
特に、朝晩だけ冷える日や、昼間だけ夏日になるような日が続くと、「もう出す?いや、まだ早い?でも寒がってるし…」と毎日迷う状態に。
その結果、ヒーターと扇風機が“両方リビングにある”という不思議な時期もあって、見た目もちょっとごちゃつきがちです。
子どもが遊んでいるとコードも危ないし、「どっちもあるなら便利だけど、邪魔だな〜」とモヤモヤしながら過ごす日が出てきます。
収納の手間もハードルになる
季節家電って、大きいしパーツが多いし、しまうのもひと苦労ですよね。
「掃除して→分解して→箱に戻して→収納場所へ」…という流れに時間がかかるので、つい後回しにしてしまいがち。
特に扇風機やヒーターは、パーツが多かったり、コードがかさばったり、元の箱にうまく戻せなかったりすることも多く、途中で挫折しかけたこともあります。
それに、収納場所が限られていると、「どこにしまう?」「奥に入れたら、来年出すとき大変そう…」と悩みが増えてしまうんですよね。
収納だけで30分以上かかったこともあり、ますます“億劫スパイラル”にハマりやすくなります。
わが家の出し入れルールと“目安”

いろいろ試した結果、今は「出す日・しまう日」をカレンダーにメモしておくようになりました。
ただし、季節家電はその年の天候や気温の変化に大きく左右されるため、あくまで「柔軟に動かせる目安」として使っています。
“この週末にやる”とざっくり決めておくだけでも、気持ちに余裕が生まれるので、予定を立てるのが億劫だった私には合っていました。
扇風機は「最低気温22℃」がひとつのライン
春から初夏にかけて、最低気温が22℃を超えてくると、寝苦しい夜が増えてきます。
夜の寝かしつけのときに「なんか暑いね〜」という会話が出るようになったら、扇風機の出番が近い合図だと思っています。
本格的に必要になるのは梅雨明け〜9月末ですが、気候の変化は年によってバラバラ。
最近は10月でも夏日が続くことがあるので、「しまうのは早すぎないように」と心がけています。
わが家の扇風機出し入れ目安:
出す時期:5月中旬〜6月初め(梅雨前の蒸し暑さを感じた頃)
しまう時期:10月上旬〜中旬(寝るときに肌寒さを感じ始めた頃)
以前は「9月になったらしまおう」と思っていましたが、一度しまってからまた暑さがぶり返すと、2度手間になることも。
それ以来、「急がず、10日間くらい様子を見てから」に変更しました。
ヒーターは「朝の室温18℃」が目安に
ヒーターは秋が深まると自然と出したくなりますが、わが家では“朝の寒さ”を重視しています。
日中はそこまで寒くなくても、朝の室温が18℃を下回ると、子どもが「寒くて起きたくない」と布団から出てこなくなります。
そんな日が続くと、「そろそろ出すか」と夫婦で相談。
特に年末が近づくと家の中の寒さ対策をしっかりしておきたいので、出し遅れないように気をつけています。
わが家のヒーター出し入れ目安:
出す時期:10月下旬〜11月上旬(朝の室温が18℃を下回った頃)
しまう時期:4月上旬〜中旬(こたつを片付けるタイミングに合わせて)
3月は日中あたたかくても、朝晩は冷える日が続きます。「もういらないかも」と思っても、冷え込みがぶり返すことがあるので、油断しないようにしています。
気温や子どもの様子にあわせて、多少ずらしながら決める。
それが、わが家の“ゆるルール”です。
片付けをラクにする収納アイデア

季節家電の出し入れを少しでもラクにするために、収納まわりの“仕組み”を見直すことにしました。
特に、「しまうときのひと手間」が翌年のストレスを大きく減らしてくれると実感しています。
季節の変わり目は他の家事も増える時期なので、なるべく迷わず、パパッと片付けられる仕組みにしておくと気持ちにも余裕が生まれます。
“掃除・パーツまとめ・収納”をワンセットで済ませる
しまうときに「掃除しないまま放置→来年あけて絶望…」という経験、ありませんか?
私は過去に、ホコリまみれの扇風機を翌年あけて、「うわ…これ拭くのに何十分かかるの?」とひとりで途方に暮れたことがあります。
それ以来、「片付け=掃除・まとめ・収納のセット作業」として固定化しました。
わが家の流れはこんな感じです。
掃除機とウェットシートで本体と羽根部分のホコリをしっかり落とす
パーツを丁寧に分解し、ビニール袋やタオルで包んでまとめておく
小物(リモコン・ネジ・説明書)をまとめた袋を一緒にして収納袋へ
ここまでを“その日のうちに一気にやる”ことをルールにしているので、翌年の出すときは拭き直しも不要なレベル。
「去年の私、ありがとう…!」と毎年心の中でつぶやいてます(笑)
圧縮収納や専用カバーも活用
家電ってかさばるし、収納スペースにも限りがありますよね。
わが家では、“圧縮袋+専用カバー”の組み合わせがすごく便利でした。
とくに便利だと感じたのが以下のような工夫です。
扇風機の羽根やガードを、パーツごとにタオルで包み、圧縮袋でひとまとめに
ヒーターはコードをしっかり巻いて、布製のカバーや専用収納袋にIN
圧縮袋には中身がわかるようにラベルを貼っておく(「扇風機2024春」といったメモ)
このひと工夫で、「出すときに何がどこにあるのか一目瞭然」になり、探す手間も激減しました。
見た目がすっきりするだけでなく、「あれ?どこしまったっけ?」と無駄に探す時間が減ったのが、個人的には一番うれしかったポイントです。
家族と共有しておきたい“タイミングの基準”
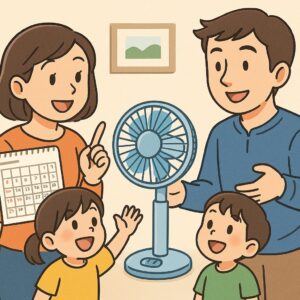
季節家電の出し入れって、なんとなく“気づいた人がやる”という流れになりやすいですよね。
わが家でも、気づいたときにはいつも私が押入れをゴソゴソ…というパターンが定着していました。
でも、それだと「家族みんなのための家電なのに、なんで私だけ?」とモヤモヤする瞬間があるのも事実。
そこで最近は、「いつ出すか」「いつしまうか」を家族みんなで共有するようにしています。
事前に「この週にやろう」と予定に入れておく
「来週末、天気がよければ扇風機出すね」と一言カレンダーで共有するだけで、夫の“手伝う心構え”ができるようになったのは大きな変化でした。
それまでは、「今から出すから押入れ手伝って!」と突然言っていたので、「え、今やるの?」という反応になることも多くて…。
今では、出し入れの週が近づくと自然と「そろそろだね」と声をかけてくれることも。
予定に入っているだけで“自分ごと”になるようで、気持ちの温度差もぐっと減りました。
子どもにも声をかけて“季節の変わり目”を感じてもらう
「今日は暑くなってきたね〜、そろそろ扇風機出そうか」と話すと、子どもも「手伝うー!」と張り切ってくれます。
小さな手で羽根のカバーを持ってきてくれたり、リモコンの掃除をしてくれたり、ちょっとした作業でも楽しそう。
こういったやりとりを通じて、“気温の変化=季節が変わっていく”という感覚を自然と体で覚えてくれる気がしています。
また、「お手伝いできたね」と褒めると満足げな表情になるので、親子のコミュニケーションとしてもいい時間になっています。
季節家電の出し入れを「家事の一部」ではなく、「家族で迎える季節のイベント」にしてしまうことで、ぐっと気持ちがラクになりました。
ちょっとした声かけやスケジューリングで、家庭内の空気も変わるものですね。
やりがちな失敗とその対策

どれだけルールを決めても、季節家電の出し入れって“予想外の気候”に振り回されるもの。
正直、今でも「もう少し早く出せばよかったな…」「しまうの早すぎたかも」ということは毎年のようにあります。
でも、その失敗から学んで、少しずつ“うちに合った出し入れタイミング”がわかってきました。
ここでは、わが家でよくある“うっかり失敗”と、その対策を紹介します。
扇風機しまったのに“夏日が戻った”!
10月上旬に「そろそろ片付けようか」と扇風機をしまった年。
数日後、なんと最高気温28℃という“まさかの夏日”が戻ってきました。
子どもは寝苦しくてグズグズ、私も「また出すの?うそでしょ…」と、半泣きで押入れから出し直す羽目に。
しかも、羽根を分解してしまっていたので、再組み立てにまた時間がかかる…。
「急ぎすぎたかも」と翌年からの反省材料になりました。
→ 対策:しまう直前に10日間予報をチェック!
天気アプリで気温の推移をざっと見て、「最高気温25℃を下回りそうかどうか」をひとつの目安にしています。
予報に“夏日”が1日でもあれば、即収納はやめて保留に。
1週間我慢すれば、「やっぱりしまってなくてよかった」となることも多いです。
ヒーターの片付け前に“寒の戻り”
4月に入り、ポカポカ陽気の日が続いていたある年。
「もう暖房いらないよね〜」と油断してヒーターを片付けた翌週、突然の寒の戻り。
朝の室温が12℃台に下がり、子どもが「寒い…」と泣きそうな顔で布団から出てこない姿に、罪悪感すら覚えました。
「また出すのは面倒…でも出さないと風邪ひきそう…」という葛藤もあり、思った以上に消耗しました。
→ 対策:「1週間様子を見る」猶予期間を置く
こたつを使っていた時期は、それを“保険”にしながら、ヒーターは少し先に片付けるようにしていました。
ただ、今はこたつを使っていないので、「日中20℃超え×朝15℃以上」が安定するまで様子を見るのがわが家の基準です。
寒さがぶり返しても1週間はヒーターが出しっぱなしでもOK、くらいの余裕をもつようにしています。
早く片付けてスッキリしたい気持ちと、また出す手間のしんどさ。
そのバランスを見誤らないためには、少しだけ“予報と余裕”を取り入れるのがポイントでした。
まとめ|季節家電の出し入れ、ゆるく決めればストレス減
季節家電の出し入れって、正解があるようでないもの。
毎年同じように見えて、気温の変化や家族の体調、暮らし方でベストなタイミングは違います。
わが家では「最低気温22℃」「室温18℃」をひとつの目安にしつつ、無理なく出し入れするようになってから、ぐっと気がラクになりました。
収納の流れをパターン化する
カレンダーで家族と共有する
出す前・しまう前に“予報チェック”を忘れない
この3つを心がけるだけで、季節の変わり目もバタバタせずに乗り切れるようになりました。
今年も気候の変化を楽しみながら、少しずつ準備をしていきたいですね。














