暑中見舞いはいつ出すのが正解?時期とマナーを徹底解説!
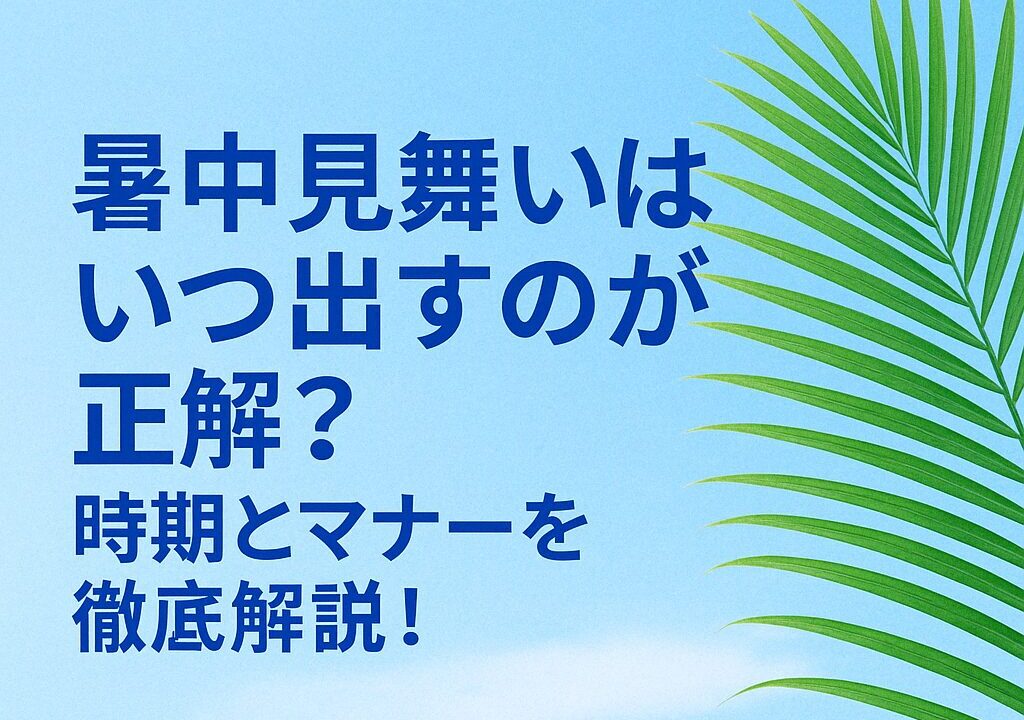
「暑中見舞いはいつ出すのが正しいの?」と迷ったことはありませんか?特にビジネスや目上の方への挨拶では、マナー違反にならないよう注意したいものです。実は、暑中見舞いには適切な期間があり、時期を外すと「残暑見舞い」となってしまうことも。
本記事では、暑中見舞いを送るベストなタイミングとその理由、さらには残暑見舞いとの違いまで丁寧に解説します。季節のご挨拶で信頼関係を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
暑中見舞いを送るべき時期とは

暑中見舞いが送られる時期の概要
暑中見舞いとは、日本独自の季節の挨拶文化のひとつで、夏の盛りに相手の体調を気遣う気持ちを伝えるハガキや手紙のことです。猛暑が続く時期には、体調を崩しやすかったり、外出が困難になったりするため、相手を思いやる一言が喜ばれます。
特に、日頃からお世話になっている方やしばらく連絡を取っていない親戚・友人、仕事関係者などに向けて、気遣いと感謝の気持ちを込めて送るのが一般的です。形式ばった挨拶だけでなく、近況報告や季節の話題を添えることで、相手との心の距離を縮めるきっかけにもなります。
梅雨明けから立秋までの期間
暑中見舞いの送付時期として適切なのは、気象的に本格的な暑さが始まる「梅雨明け」から、暦の上で秋が始まるとされる「立秋の前日(例年8月6日ごろ)」までとされています。
ただし、日本列島は南北に長いため、梅雨明けの時期は地域によって差があります。たとえば九州では6月末〜7月上旬、関東では7月中旬ごろが目安ですが、年によって前後するため、ニュースや気象庁の情報を参考にすると確実です。
また、立秋を過ぎてから暑中見舞いを出すと「残暑見舞い」となるため、出すタイミングに細心の注意を払うことが大切です。タイムラグのある郵便配送も考慮し、できるだけ早めに準備を進めておくと安心です。
暑中見舞いの送信タイミングの重要性
暑中見舞いは、単に「暑いから送る」ものではなく、「暑さが本格化した時期に相手の健康を気遣う」という意味が込められた、日本らしい礼儀のひとつです。だからこそ、送る時期を誤ると相手に違和感を与えたり、場合によってはマナー違反と捉えられることもあります。
特にビジネスシーンでは、暑中見舞いのタイミングはその人の礼儀正しさや信頼度にも関わる要素。立秋を過ぎても暑中見舞いを出してしまうと、形式的なマナーに対する配慮が不足していると見なされる可能性があります。
また、個人間でも「季節感を大切にする心」が伝わるのは、時期にふさわしいタイミングで送ったときです。7月中旬〜下旬に相手の手元に届くように発送することで、相手に気持ちよく受け取ってもらえる確率が高くなります。
残暑見舞いはいつまで?

残暑見舞いの基本的な考え方
残暑見舞いとは、「立秋(例年8月7日ごろ)」を過ぎてから送る季節の挨拶状で、暑さが残る中で相手の健康を気遣う心を伝える手紙やハガキのことです。暑中見舞いと同様に、親しい方やお世話になった人に送ることで、思いやりや感謝の気持ちを表現する日本ならではの習慣です。
残暑見舞いには、「厳しい暑さの中でも無事に夏を過ごされましたか?」という労いの気持ちと、「まだまだ暑さが続く中、お体をご自愛ください」という配慮の意味が込められています。一段落した時期だからこそ、心に残る優しい言葉を添えるのがポイントです。
残暑見舞いを送るタイミング
残暑見舞いを出すタイミングとして最も適切なのは、立秋を過ぎた8月7日ごろから8月31日までの期間とされています。この期間であれば、相手に違和感なく、季節のご挨拶として受け取ってもらえます。
9月に入ると、日によっては涼しさを感じる地域も出てくるため、残暑見舞いとしての「季節感」が薄れてしまい、マナー上ふさわしくないとされることもあります。そのため、残暑見舞いはなるべく8月中旬までには投函し、遅くとも8月末には相手のもとに届くようスケジュールを立てておくと安心です。
郵送の場合は配送日数も考慮し、お盆前後の混雑を避けて早めに準備を始めることをおすすめします。
残暑見舞いの期間についての解説
暦の上での季節の区切りは、気温とは必ずしも一致しません。実際には連日30度を超えるような日が続いていても、立秋(8月7日ごろ)を境に「秋」とみなされます。このため、暑中見舞いは立秋前まで、立秋以降は残暑見舞いに切り替えるのが、正式なマナーとされています。
「暑さが続いているから、まだ暑中見舞いでもいいのでは?」と思いがちですが、手紙文化のルールとしては暦に準じた使い分けが重要です。特に目上の方やビジネス関係者に送る際には、暦を意識した表現に切り替えることで、信頼や礼儀正しさが伝わります。
たとえば文頭の時候の挨拶を、「残暑の候」「晩夏の折」などに変えるだけでも、文面全体に季節感と洗練された印象が生まれます。
暑中見舞いに適した時期の特徴

気候と暑中見舞いの関係
暑中見舞いは、「一年で最も暑さが厳しくなる時期」に送るご挨拶として、日本の四季と深く結びついた文化的な慣習です。特に近年では猛暑日が続くことも多く、体調管理が重要視される時期でもあります。
このような背景から、暑中見舞いには「暑さの中、無事にお過ごしですか?」「体調を崩していませんか?」といった相手を思いやる気持ちを届ける役割があります。熱中症や夏バテ、睡眠不足などが懸念される季節だからこそ、暑中見舞いを通じて健康を気遣うメッセージを伝えることが大切です。
また、単なる形式的な挨拶ではなく、「あなたを気にかけていますよ」という気持ちが伝わることで、人間関係の距離感を縮めるきっかけにもなります。
各地域における暑中見舞いの時期
日本列島は縦に長く、気候の違いが大きいため、暑中見舞いを出す適切なタイミングも地域ごとに異なります。たとえば、沖縄や九州など南の地域では梅雨明けが早く、7月初旬から中旬には本格的な暑さが始まるため、この時期に暑中見舞いを出すのが一般的です。
一方、北海道や東北など比較的涼しい地域では、梅雨明けが遅い、あるいは梅雨そのものがない場合もあり、暑中見舞いを出すのが7月下旬から8月初旬になることもあります。
こうした地域差を踏まえて、暑中見舞いを送る際は、相手が住んでいる地域の気候も考慮に入れるのがスマートな対応です。特に全国に取引先や親戚がいる場合は、送り先に応じたタイミングの調整が信頼感につながるポイントとなります。
近況報告としての役割とタイミング
近年では、暑中見舞いは単なる季節のご挨拶にとどまらず、お互いの近況を伝える手段としても広く活用されています。年賀状ほどフォーマルにならず、かつ柔らかい印象でコミュニケーションを図れる点が、暑中見舞いの魅力のひとつです。
「最近どうしてるかな?」という気持ちに乗せて、転職・引っ越し・家族構成の変化など、プライベートな近況を軽く伝えるツールとしても最適です。また、ビジネスでも「変わらぬご愛顧への感謝」といった言葉を添えることで、関係性をスムーズに維持できます。
理想的なのは、お盆前までに相手の手元に届くように準備を整えること。お盆を過ぎると残暑見舞いのタイミングとなるため、7月中〜8月初旬に送るのがベストです。郵便の混雑や相手の休暇予定を考慮して、できるだけ早めの準備が安心です。
印刷したハガキと手書きハガキの違い

手書きのメリット・デメリット
手書きの暑中見舞いは、何よりも「気持ちが伝わる」という点が最大の魅力です。筆跡には人柄や感情が表れ、パソコンや印刷された文章よりも、一人ひとりに丁寧に向き合った印象を与えることができます。特に家族や親しい友人、恩師など、関係性が深い相手には手書きの方が喜ばれる傾向があります。
一方で、文章を考える時間や、書き間違えた場合の修正の手間など、作成に時間がかかるというデメリットも無視できません。多くの相手に一斉に送る場合や、忙しい時期には負担になることもあります。
そのため、手書きと印刷を使い分けることがポイントです。たとえば、文面は印刷しておき、最後に「お元気ですか?暑さに気をつけてくださいね」などの一言メッセージを手書きで添えるだけでも、相手に誠意が伝わります。
ビジネスシーンでのマナー
ビジネスシーンにおける暑中見舞いでは、形式と丁寧さのバランスが重要です。大量に送ることが多いため、文面は印刷で構いませんが、宛名や一言メッセージを手書きすることで、より丁寧な印象を与えることができます。
とくに目上の方や取引先など、礼儀を重んじる相手に対しては、以下のような配慮が大切です。
宛名の敬称を間違えない(例:「様」「御中」など)
会社名・役職名を正確に書く
差出人情報を明確にする(社名、部署、氏名など)
また、季節柄の挨拶に加えて「平素よりお引き立ていただき、誠にありがとうございます」などの感謝の一言を入れると、よりフォーマルで印象の良い挨拶状になります。
忙しい時期であっても、一言でも手書きを加えると「気にかけてくれている」と感じさせる力があります。それが将来的な信頼関係の強化にもつながります。
暑中見舞いは内容だけでなく、見た目にも季節感や個性を出すことができます。最近では市販のハガキやオンラインサービスを使って、カジュアルでセンスの良いデザインを簡単に作成・印刷できるようになりました。
たとえば、
水彩画風の涼しげなイラスト
金魚や風鈴、朝顔などの夏モチーフ
写真入りハガキ(家族や子ども、旅行先の写真など)
などを取り入れると、受け取った相手の印象にも残りやすく、楽しんでもらえる1枚になります。
また、デジタル時代ならではのサービスを活用すれば、自宅のプリンターやスマホアプリでオリジナルの暑中見舞いを作ることも可能です。特に若い世代やクリエイティブな印象を与えたい方には、テンプレートやフォントのアレンジもおすすめ。
見た目にこだわることで、形式的な挨拶を超えた「ちょっと嬉しい気遣い」として記憶に残る暑中見舞いになります。
暑中見舞いの文章例とポイント
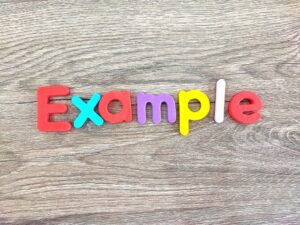
挨拶文の基本構成
暑中見舞いの文章には基本的な型があり、構成に沿って書くことで、相手にとって読みやすく、気持ちが伝わる挨拶状になります。以下が一般的な構成です。
時候の挨拶(冒頭)
→ 例:「猛暑の候」「炎暑の折」「酷暑の候」など、夏の暑さを表す表現を使用。相手の安否を気遣う言葉
→ 「いかがお過ごしでしょうか」「ご健勝のこととお喜び申し上げます」など。自分の近況報告
→ 「おかげさまで私どもは元気に過ごしております」や「新しい職場にも少しずつ慣れてきました」など、さりげなく近況を伝えることで親近感が生まれます。結びの言葉
→ 「暑さ厳しき折、どうぞご自愛ください」「今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます」など、相手を気遣う一言で締めくくります。
この基本構成を押さえておくことで、誰に対しても失礼のない文面を作成することができます。加えて、自分らしさや季節感を織り交ぜることで、より印象に残る文章になります。
相手によって変える文面の工夫
暑中見舞いは相手との関係性やシーンによって、文体や表現のトーンを変えることが大切です。TPOを意識した文面は、マナーだけでなく気遣いとしても評価されます。
親しい友人・家族向け
カジュアルで親しみのある言葉づかいでOK
日常の出来事や旅行・子どもの話題なども織り交ぜると◎
絵文字やイラスト付きのハガキも喜ばれます
例:
「今年も暑い日が続いてるけど、元気にしてる?夏バテしないように、お互い気をつけようね!」
ビジネス関係者・目上の方
丁寧語・敬語を正しく使い、フォーマルな印象を与える文章を心がける
季節の挨拶と感謝の気持ちを盛り込み、業務への配慮を忘れずに
例:
「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。暑さ厳しき折、貴社ますますのご発展と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。」
恩師・目上の親族など
少し柔らかくしつつも、敬意を忘れない表現が望ましい
教育的な話題や家族の報告などを丁寧に盛り込むと好印象です
人気の暑中見舞い文例集
以下はさまざまなシーンに使える、暑中見舞いの定番かつ人気の文例です。
フォーマル系(ビジネス・目上の方に)
「暑さ厳しき折、貴社の皆様のご健康とご発展をお祈り申し上げます。」
「平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。」
カジュアル系(友人・知人に)
「毎日暑いけど、元気にしてる?夏バテしないようにしっかりご飯食べてね!」
「この夏も思い出たくさん作ろうね!落ち着いたらまた会えると嬉しいな。」
季節感を意識した定番文
「連日の猛暑が続いておりますが、お元気でお過ごしでしょうか?」
「暑さも本番となりましたが、どうぞくれぐれもご自愛くださいませ。」
メールでの暑中見舞いの活用

デジタル時代の暑中見舞いの意義
近年では、手書きのハガキに代わって、メールやSNSを活用した暑中見舞いのやりとりが広まりつつあります。特にビジネスシーンでは、郵送よりも迅速かつ効率的に送信できるメールによる暑中見舞いがスタンダードになりつつあります。
また、若い世代の間では、紙の手紙に馴染みが薄くなっていることもあり、LINEやInstagramのDM、X(旧Twitter)のリプライなどを使って季節の挨拶を交わすスタイルも定着しています。気軽に送れる反面、略式になりすぎないよう注意することも必要です。
とはいえ、どんな形式であっても「相手を思いやる気持ち」を表現することが本質。デジタル手段を上手に活用すれば、忙しい現代人でも無理なく心のこもった挨拶ができるという点で、非常に有効なコミュニケーション方法となっています。
SNSとの違いと活用法
暑中見舞いをデジタルで送る場合、「誰に・どう届けるか」を意識したツールの使い分けが大切です。たとえば、
SNS(Instagram、Facebook、Xなど)の特徴
広範囲に一括で挨拶を届けられる
写真付き投稿やストーリーズなどで視覚的に季節感を演出できる
個人的なやりとりには不向きな面もある
メールの特徴
一対一の丁寧なコミュニケーションが可能
ビジネスやフォーマルな場に適している
宛名や署名を明記できるため、正式な印象を与えやすい
このように、SNSは「友達やフォロワー全体への季節の挨拶」、メールは「関係性のある個人に対しての丁寧な連絡」というように使い分けるのが理想です。相手の年齢や立場、普段の関係性を考慮して、どのツールで送るのが適切かを選ぶ視点が求められます。
メールで送信する際のマナー
メールで暑中見舞いを送る場合でも、礼儀や丁寧さを意識した書き方を心がけることが重要です。特にビジネス相手や目上の方に送る際は、以下のポイントを押さえましょう。
1. 件名には挨拶がわかるように明記
例:「暑中お見舞い申し上げます」「【暑中見舞い】季節のご挨拶」など、メールを開かなくても内容が分かる件名が理想です。
2. 冒頭の挨拶
季節に合わせた時候の挨拶(「猛暑の候」など)を用いて始めると丁寧な印象に。
3. 相手の健康を気遣う言葉
例:「酷暑が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。」
4. 自分の近況や一言メッセージ
簡潔に現在の状況を伝えることで、会話のきっかけにもなります。
5. 結びの言葉
「ご多忙の折、くれぐれもご自愛くださいませ。」などで締めると丁寧です。
6. 署名は忘れずに
会社名・氏名・連絡先など、メールの署名欄には最低限の情報を明記しましょう。
暑中見舞いを送る際の注意点

喪中の時期に関する配慮
暑中見舞いを送る際、相手が喪中である場合は特に配慮が必要です。一般的に、喪中の方に対して「お祝い」や「季節の便り」としての意味合いを持つ言葉を用いることは、避けるのがマナーとされています。
たとえば、通常の「暑中お見舞い申し上げます」という言葉は、喪中の方にはふさわしくありません。その代わりに、「お悔やみ申し上げます」や「ご愁傷さまでした」「暑い日が続いておりますが、どうかご自愛くださいませ」といった、控えめで相手を気遣う表現に変更するとよいでしょう。
また、はがきのデザインにも注意が必要です。華やかすぎるイラストや明るすぎる色合いは避け、シンプルで落ち着いたデザインを選ぶのが基本です。白黒である必要はありませんが、全体のトーンを抑えるだけでも十分に配慮が伝わります。
文面でも、亡くなられた方への直接的な言及は避け、「ご家族の皆様が平穏に過ごされますようお祈りいたします」といった間接的な表現に留めるのが適切です。
返事が返ってこない場合の対処法
暑中見舞いを送ったあとに、相手から返事が来ないこともありますが、それを気にする必要はありません。本来の目的は「返事をもらうこと」ではなく、「季節の挨拶と健康への気遣いを伝えること」にあります。
特に年配の方や多忙なビジネスパーソンの場合、返信を控えるケースも多く、それは失礼ではありません。また、喪中や体調不良などで返事を出せない事情があることも想定されます。
返信がなかったとしても、「暑い中、元気で過ごされていればそれで十分」と思えるくらいの気持ちで送るのが理想です。見返りを求めず、思いやりを伝えるという姿勢が、結果として良い印象を残すことにつながります。
どうしても返信が気になる場合は、次に会ったときや電話などで軽く話題に出す程度に留めておきましょう。しつこく確認するのはマナー違反と受け取られる可能性があります。
送信後の挨拶やお礼について
相手から暑中見舞いの返信をもらった場合、感謝の気持ちを込めて軽いお礼の言葉を返すと、より良い関係が築けます。特にプライベートな相手であれば、「お返事ありがとう!とても嬉しかったです」といった自然な表現でOKです。
ビジネスシーンでは、返信が来ること自体がまれですが、もし丁寧な返答をもらった場合は、「お心遣いをいただき、誠にありがとうございました」といったフォーマルな言葉での返信が望まれます。
ただし、ビジネス上では「暑中見舞いの返信に返信を重ねる」ことは必須ではなく、形式的なやりとりが続くことを避けるため、返信不要のケースも多いです。そのため、返信するかどうかは、相手との関係性や業界の慣習に応じて判断しましょう。
また、メールやSNSで暑中見舞いを受け取った場合も、短くても感謝を伝える一言を返すだけで、印象が大きく変わります。小さな気遣いが、信頼関係の維持や向上につながる大切なポイントです。
暑中見舞いを送る相手の選び方

家族や友人への送り方
家族や友人に暑中見舞いを送る際は、かしこまりすぎず、気軽で親しみのある文章を意識しましょう。基本的な構成に沿いつつ、思い出話や最近の出来事などを添えることで、受け取った相手にも笑顔が広がります。
たとえば、
「この間の旅行で撮った写真を同封します!」
「子どもがこんなに大きくなりました」
といった近況報告を交えた文面は、読む側も安心感を覚えるものです。
また、近年では写真入りハガキやイラスト付きのオリジナルデザインも人気。スマホで撮影した家族写真を使った暑中見舞いは、見た目にも楽しく、受け取った人の記憶にも残りやすいです。
文面もカジュアルな表現で問題ありませんが、「暑さに負けず、元気で過ごしてね!」「また近いうちに会いたいね」といったあたたかい言葉を添えると、より心が伝わります。
ビジネス関係者への送り方
ビジネス相手への暑中見舞いは、礼儀と形式を重視したフォーマルな挨拶状が基本です。特に企業間でのやり取りや上司、取引先などに送る場合には、マナーに則った内容とレイアウトが求められます。
以下の点に注意して作成しましょう。
会社名・役職・氏名は正式表記で正確に
時候の挨拶(例:「盛夏の候」「炎暑の候」など)を用いた丁寧な言葉づかい
感謝の気持ち(例:「平素より格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます」など)
結びの言葉には、相手の健康と繁栄を願う一文を
文例:
「暑中お見舞い申し上げます。酷暑の折、貴社ますますのご清祥のこととお喜び申し上げます。今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。」
また、印刷ハガキでも問題ありませんが、差出人の署名を手書きすることで一層丁寧な印象を与えることができます。
恩師や親戚へのメッセージ
恩師や目上の親戚への暑中見舞いでは、敬意を持った丁寧な言葉づかいと、感謝の気持ちが伝わる内容を心がけましょう。
たとえば、学生時代にお世話になった先生へ送る場合は、
「◯◯先生には在学中、大変お世話になりました」
「今でも先生の教えを日々の生活に活かしております」
といった形で、自分の成長や現在の様子を伝えると、読み手にも喜んでもらえるでしょう。
親戚への暑中見舞いには、
「なかなか会えませんが、お元気でお過ごしでしょうか」
「この夏はそちらへ帰省できるかもしれません」など、
家族とのつながりを感じさせるような文面が好まれます。
いずれの場合も、「ご自愛くださいませ」や「皆様のご健康をお祈り申し上げます」など、健康を気遣う言葉で締めくくるのが基本です。
また、手書きにすることで一層温かみが伝わり、形式的ではない、心のこもった挨拶として相手の記憶に残る暑中見舞いになります。
暑中見舞いの歴史と由来

暑中見舞いの起源と発展
暑中見舞いの起源は、江戸時代の「夏の贈答文化」にさかのぼります。お中元と同様に、お世話になっている人へ感謝と健康を気遣う気持ちを込めて贈り物を持って訪問するという習慣がありました。これが、暑さの厳しい時期に「気遣い」を示す行動として定着し、暑中見舞いの原型となりました。
当初は物品を直接届ける形でしたが、人と人との交流が広がるにつれ、訪問が難しい場合には「書状」によって挨拶を送るように変化していきました。特に、暑さが体に堪える時期に相手の無事を願う気持ちを文面で伝えることは、今も昔も変わらない日本人らしい心遣いと言えるでしょう。
このようにして、暑中見舞いは贈答文化から文書文化へと進化し、今では「暑い季節に相手を気遣う挨拶状」としての形式が確立されました。
夏の挨拶文化の変遷
明治時代に入ると、郵便制度の整備とハガキの普及により、それまで口頭や訪問で行っていた挨拶が、手紙やハガキによって届けられるようになります。これが、現代の暑中見舞いのスタイルの始まりです。
特に1900年代初頭には、暑中見舞い用の絵はがきが印刷されるようになり、夏らしいデザインとともに季節の挨拶を楽しむ文化が生まれました。戦後には年賀状とともに、暑中見舞いもハガキ文化として広まり、「年に一度の安否確認や近況報告」の役割を果たす習慣として定着していきました。
昭和の時代には、企業が取引先に向けて大量の暑中見舞いを送ることも一般的になり、ビジネスツールとしても活用されるようになります。このように、時代の変化に合わせて暑中見舞いのスタイルや目的は多様化しつつも、「相手を思う心」を伝える文化として根強く残っています。
現代における位置づけ
現代では、暑中見舞いは年賀状と並ぶ代表的な季節のご挨拶として広く知られています。形式張った印象を持たれがちですが、実際にはビジネスでもプライベートでも使える柔軟なコミュニケーションツールとして見直されてきています。
特に、普段なかなか会えない相手に対して、気軽に近況を伝えられるきっかけとして活用する人が増えており、「暑中見舞い=古い文化」というイメージを払拭しつつあります。
また、デジタル化が進んだ現代においても、ハガキや手書きメッセージでの暑中見舞いには「特別感」があるため、かえって好印象を与えるケースも多いです。企業によっては、メールで暑中見舞いを送る一方で、重要な取引先には印刷ハガキを使うなど、相手との関係性に応じた使い分けがされています。
このように、暑中見舞いは「人と人をつなぐ温かな文化」として、今も息づいている日本の伝統的な風習なのです。
まとめ|暑中見舞いは時期を押さえて丁寧に届けましょう
暑中見舞いは「梅雨明けから立秋の前日」までが基本の送付期間です。時期を逃すと残暑見舞いとなり、季節感やマナーにも影響するため、適切なタイミングで出すことが大切です
相手の立場や関係性に応じて文面を工夫し、思いやりを込めて送りましょう。手書きやメールなど形式はさまざまですが、「心を届ける」ことが何より重要です。今年の夏は、暑中見舞いで丁寧なご挨拶をしてみませんか?














