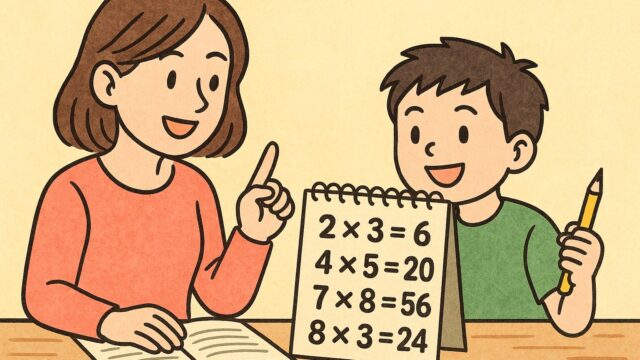叱ると怒るの違いとは?子どもの心を守るしつけと怒り方のバランス

子どもを育てていると、「これは叱らないと」と思う場面が何度もありますよね。
でも、気づけば感情的になって怒ってしまったり、「あの言い方はきつすぎたかな…」と後悔することも。私も何度も同じことを繰り返し、反省と模索の毎日です。
この記事では、私自身の体験を交えながら「しつけ」と「怒り方」の違い、そして感情との向き合い方を整理します。読んだあと、「次はこうしよう」と思えるようなヒントをお届けします。
しつけと怒り方の違いって何だろう?

子育てをしていると、日々の中で「これは叱らなきゃ」という場面は何度もやってきます。
ところが、そのつもりが気づけば声が荒くなり、子どもに感情をぶつけてしまうことも。私自身、「叱ったつもりが怒ってしまった」経験は数え切れないほどあります。
実は、この「叱る」と「怒る」は似ているようでいて、本質的にはまったく違うものです。
違いを知っておくことで、親としての言葉の選び方や、子どもへの向き合い方が変わってきます。
叱る=子どもを導くための行動
私が思う「叱る」とは、子どもの成長のために必要なルールや考え方を、落ち着いて伝える行動のことです。
たとえば、信号のない道路に飛び出そうとしたとき。「止まって!車が来たら危ないよ」とその場で注意する。これは命を守るために必要な行為であり、子どもの将来にとってプラスになる行動です。
叱るときには、単に「ダメ!」と否定するだけではなく、「なぜそれが良くないのか」「どうすればいいのか」をセットで伝えることが重要です。理由や背景がわかれば、子どもは次に同じ場面が来たときに自分で判断できるようになります。
怒る=自分の感情をぶつけること
一方で「怒る」は、親のイライラや焦り、不安などの感情をそのままぶつけてしまう状態を指します。
例えば、忙しい朝に子どもが牛乳をこぼしてしまったとき。最初は「拭こうね」と声をかけるつもりが、「もう!何やってるの!」と大きな声を出してしまう…。これは危険を回避するためではなく、自分の感情が先に立ってしまった結果です。
私もこうした経験は数えきれず、後になってから「もっと落ち着いて言えばよかった」「あの言い方はきつすぎたな…」と反省することがよくあります。怒ってしまうと、子どもは行動の何が悪かったのかよりも、「ママ(パパ)が怖かった」という印象ばかりが残ってしまうことも。
違いを理解することで生まれる変化
「叱る」は子どもを導くための行動、「怒る」は感情を吐き出す行動。この違いを意識しておくと、自分の言葉や態度を選ぶ前に一瞬立ち止まれるようになります。
感情に流されず、必要なことを冷静に伝えるための土台として、この違いを理解しておくことはとても大切です。
私が「叱るつもりが怒ってしまう」瞬間

日常の中で、最初は冷静に注意しようとしていたのに、気づけば声が大きくなっていることがあります。
私の場合、それは決まって同じようなシチュエーションで起きることが多いのです。
朝のバタバタが引き金に
特に多いのが、出かける前の朝。
着替えをなかなかしない、食事に集中しない、歯磨きを嫌がる…。この「小さなつまずきの連続コンボ」が、私の心の中の「我慢メーター」を一気に満タンにしてしまいます。
最初は「急いでね」と優しく声をかけているのに、何度言っても状況が変わらないと、だんだん声が強くなっていきます。
そして5分後には「何回言えばわかるの!」と怒鳴ってしまう。
その瞬間、自分の中でも「あ、またやってしまった…」という後悔の声が響きます。
自分の余裕のなさが関係していた
ある日、少し落ち着いたときに振り返ってみると、怒ってしまう日は不思議なくらい共通点がありました。
それは、私自身が疲れていたり、仕事や家事で時間に追われている日ばかりだったということ。
つまり、子どもの行動そのものが原因ではなく、「自分の心の余裕のなさ」が火種になっていたのです。
余裕があるときは同じ出来事でも笑って受け止められるのに、時間に追われているときは一瞬でイライラが爆発します。
気づきがもたらした変化
このことに気づいてから、「叱る」は子どものため、「怒る」は自分の感情から出ている、と意識するようになりました。
意識するだけでも、行動の選び方が少しずつ変わってきます。
怒りそうになったときに「これは本当にしつけのため?それとも今の私の余裕のなさ?」と一瞬立ち止まると、言葉のトーンがやわらぎ、伝え方も変わります。
自分の状態を整えることが、子どもへの接し方を整える近道だと、今は実感しています。
叱るときに意識している3つのポイント

私が試行錯誤しながら見つけた、感情に振り回されずに叱るための工夫があります。
これを意識するようになってから、同じ注意でも子どもの受け止め方が変わり、私自身も後悔することが減りました。
1. その場で短く、理由も伝える
叱るときは、その場ですぐに、そしてできるだけ短く伝えることを心がけています。
長々と説教をしても、子どもは途中で飽きてしまい、耳から入っているようで実はほとんど残っていません。
例えば、「道路に飛び出したら危ないよ。車が来たらケガをするからね」のように、理由を添えて短く伝えるだけで十分。
そのほうが、子どもも状況と行動のつながりを理解しやすくなりますし、後から「どうしてダメだったの?」と聞き返すことも減ります。
2. 子どもを否定せず、行動を正す
叱るときに一番気をつけているのは、子どもの人格を否定しないことです。
「あなたはダメな子!」という言葉は、行動を正すどころか、子どもの自己肯定感を下げてしまう危険があります。
そこで意識しているのは、「今の行動は危なかったよ」のように、行動そのものに焦点を当てて伝えること。
そうすれば、子どもは「自分はダメな人間だ」と感じるのではなく、「その行動を変えればいいんだ」と前向きに受け止めやすくなります。
3. 感情が高ぶったら一呼吸おく
どうしてもイライラが抑えられないときは、その場を離れて深呼吸します。
ほんの数十秒でもいいので、一呼吸おくことで頭が冷え、言葉のトーンや選び方が柔らかくなります。
私は、一度感情的になってしまった経験から、「すぐに反応しない」という選択肢を持つようになりました。
場合によっては、その場で注意せず、落ち着いたタイミングで話すこともあります。
これだけで、子どもとのやりとりがずっとスムーズになりました。
叱るときの主語は「子ども」ではなく「行動」にすると、感情的になりにくくなります。
この視点を持つだけで、親子のやりとりはぐっと前向きになります。
怒ってしまった後のフォロー方法

どんなに気をつけても、感情が爆発してしまう日もあります。
疲れている日や時間に追われている日ほど、気づけば声が大きくなってしまう…。そんな自分に後から落ち込むこともあります。
でも、ここで諦めずに行う「フォロー」が、意外と子どもとの関係を良くしてくれることに気づきました。
素直に謝る
まず大切なのは、素直に謝ること。
「さっきは大きな声を出してごめんね」と伝えるだけで、子どもの表情が和らぎます。
完璧な親でなくても、間違えたら謝れる姿勢は、子どもにとって大きな学びになります。
私自身、以前は「親が子どもに謝るのは変なのかな?」と思っていた時期もありました。
でも、謝ることで「あなたのことを大切に思っているよ」という気持ちが確かに伝わり、子どもとの距離が近くなるのを感じます。
スキンシップで安心感を
謝った後にぎゅっと抱きしめるだけで、子どもの表情が柔らかくなります。
言葉だけでは届きにくい安心感も、触れることでストレートに伝わります。
とくに幼い子ほど、抱っこや手を握るなどのスキンシップが効果的です。
我が家では、抱きしめたときに「大好きだよ」とひと言添えるようにしています。
その瞬間、子どもは安心したようにため息をつき、私の腕の中で力を抜いてくれます。
フォローは信頼関係を守る時間
フォローの時間は、「親子の信頼関係を守る大事な時間」だと感じます。
叱ったあとや怒ってしまったあとにこそ、気持ちをリセットして次につなげるチャンスがあります。
謝罪やスキンシップは、「叱る=嫌いになった」という誤解を解き、「叱る=あなたを大切に思っているから」というメッセージを残してくれます。
私が取り入れて効果があった怒りのコントロール法

私は、感情を「抑える」ことばかり意識していた時期がありました。
でも、それは結局どこかで限界がきて爆発してしまい、後悔することの繰り返し…。
そこで考え方を変えて、「抑える」よりもうまく流す方法を取り入れるようにしました。
この工夫を始めてから、怒りの爆発が目に見えて減ったのです。
朝の準備を前倒し
以前の私は、ギリギリまで寝てしまい、朝は常に時間との戦い。
そんな中で子どもがのんびりしていると、余裕のない気持ちが一気にあふれてしまっていました。
そこで、思い切って15分だけ早く起きるようにしました。
このわずかな時間が、子どものペースに寄り添える心のスペースを生んでくれます。
「もう急いで!」と焦らせる回数が減り、朝の雰囲気がやわらかくなりました。
自分時間を少しでも確保
怒りやイライラは、心の疲れからも生まれます。
夜にお茶を飲みながら本を読む、昼に好きな音楽を聴く、ほんの5分でもいいから一人の時間を持つようにしました。
自分が満たされると、子どもへの言葉も自然と優しくなることに気づきます。
完璧なリラックスタイムでなくても、「自分のためだけの時間をとった」という事実が、気持ちを軽くしてくれます。
「後で話す」選択肢を持つ
感情が高ぶった状態で注意すると、どうしても言葉が強くなってしまいます。
そこで、「今は話さない」という選択肢を持つようになりました。
たとえば、夕方に子どもが宿題を放って遊んでいたとしても、私が疲れている日は注意せず、その日の夜や翌朝など、落ち着いたタイミングで伝えます。
時間を置くだけで、冷静に、必要なことだけを伝えられるようになります。
この3つの方法は、どれも特別な道具や大きな時間は必要ありません。
でも、続けていくうちに「怒る前に立ち止まれる回数」が確実に増えました。
まとめ|感情に流されない「しつけ」で親子関係を育てよう
子どもをしつけることと、感情的に怒ることは似ているようで違います。
感情に任せた言葉は、時に子どもの心を傷つけてしまうこともあります。
だからこそ、「叱る=子どもを導く」「怒る=感情をぶつける」と分けて考えることが大切です。
私も完璧ではありませんが、この意識を持つようになってから、少しずつ言葉の選び方が変わってきました。
今日から「怒る前に一呼吸」を合言葉に、親子で笑顔の時間を増やしていきませんか?