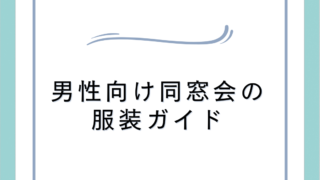お盆の団子をいつ供える?迎え団子・送り団子のしきたり

お盆の時期、ご先祖様にどのような団子をお供えすればよいか迷っていませんか?地域や家庭によって風習が異なるうえ、「迎え団子」や「送り団子」の意味や供える日程、数、形なども意外と知られていません。
適切なお供えを通じて、ご先祖様に感謝と敬意を伝えたいもの。この記事では、お盆の団子供えの基本から丁寧な準備方法まで、分かりやすくご紹介します。お盆行事に初めて参加する方も、安心してお供えの作法を整えられますよ。
迎え団子・送り団子とは?

迎え団子(むかえだんご)
お盆の最初の日に、ご先祖様の魂をお迎えするために供える団子です。古くからの風習の一つであり、あの世からはるばる帰ってきたご先祖様の心身の疲れをねぎらい、安らかにお過ごしいただけるよう願いを込めてお供えします。
特に、帰ってこられたことへの感謝の気持ちを表すとともに、お盆の始まりを家族で意識する大切な役割も果たしています。甘い味付けの団子が多く選ばれるのは、疲れた体に甘味が優しいとされるためです。
送り団子(おくりだんご)
お盆の終わりに、ご先祖様を再びあの世へとお見送りする際に供える団子です。現世での滞在を終えて戻られる旅路の無事を祈り、お土産として持ち帰っていただけるようにという気持ちが込められています。
あえて味付けをせず、ご先祖様が好みに合わせて味わえるよう配慮されることもあります。お見送りの儀式として、送り火とともに供える地域もあります。
加えて、「供え団子」と呼ばれる団子も、一部の地域や家庭では日常的に供えられています。これはお盆の期間中、ご先祖様が家の中で静かに、そして穏やかに過ごされるようにとの願いを込めたもので、毎日または定期的に新しい団子をお供えするのが特徴です。
地域によっては「お供え餅」「落ち着き団子」「ゆっくり餅」など、呼び方にもバリエーションがあり、家庭ごとの温かいおもてなしの心が感じられます。
団子を供える日程(2025年版)

お盆の期間は、地域によって開始時期や風習が異なるため、一律ではありませんが、全国的には7月または8月の中旬に設定されていることが多く、一般的に4日間にわたって行われるのが通例です。
この時期には、家族が集まり、ご先祖様の霊をお迎えし、感謝の気持ちとともに心静かに過ごす時間を大切にします。
7月にお盆を迎える地域
・期間:2025年7月13日(日)〜16日(水) ・団子を供える日:
- 7月13日(日):迎え団子をお供えしてご先祖様をお迎えします。迎え火とともに供える家庭もあります。
- 7月14日(月)・15日(火):供え団子を供え、ご先祖様が滞在中も心地よく過ごせるようにします。
- 7月16日(水):送り団子をお供えし、ご先祖様をあの世へとお見送りします。送り火とあわせて行う場合もあります。
8月にお盆を迎える地域
期間:2025年8月13日(水)〜16日(土)
団子を供える日
- 8月13日(水):迎え団子を用意し、ご先祖様を迎え入れる準備を整えます。地域によっては朝にお供えする風習も。
- 8月14日(木)・15日(金):供え団子を中心に、日々の供え物を工夫しておもてなしの気持ちを表現します。
- 8月16日(土):送り団子を供えて、ご先祖様が安らかに旅立てるよう祈りを込めてお見送りします。
※団子を供える時間帯については、特に厳格な決まりはなく、家庭ごとに都合の良い時間に供えて構いません。朝のお参りと一緒に行う家庭もあれば、夕方の送り火と合わせる場合もあり、柔軟に対応できます。
団子の種類と準備方法
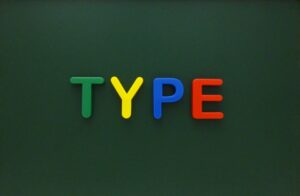
迎え団子
迎え団子は、ご先祖様があの世から戻ってくる際の長旅の疲れを癒し、気持ちよく現世で過ごしていただくために供えるお団子です。一般的には甘い味付けのものが多く、白玉団子にあんこやきなこ、甘辛いタレをかけてお供えします。
甘味には心身を和らげる効果があるとされ、旅路を終えた霊にとっての癒しになるという意味が込められています。また、団子を供える器や配置も大切で、高坏に白紙を敷いた上に美しく並べるのが丁寧とされています。
市販品を使用する際も、あん団子やみたらし団子など、優しい味わいのものを選ぶと良いでしょう。供えるタイミングは、できるだけご先祖様が帰ってくる前に準備を終えておくのが理想です。
供え団子
供え団子は、お盆の期間中に毎日または定期的に供える団子のことで、ご先祖様が家で安らかに滞在できるよう心を込めて用意されます。使用される団子には特に決まりはなく、白玉団子、みたらし団子、あん団子、おはぎなど、家庭ごとの習慣や好みに応じて選ばれます。
供え方も多様で、毎日新しい団子を供える家もあれば、同じものを二日間続けてお供えする家庭もあります。
また、団子に加えて季節の果物や和菓子などを一緒に供えることで、より一層の“おもてなし”の気持ちを表現することができます。団子が傷みやすい夏場は衛生面にも注意が必要で、朝と夕方に入れ替えるなど工夫をしているご家庭もあります。
送り団子
送り団子は、お盆の終わりにあの世へ戻るご先祖様に対し、感謝の気持ちと無事の旅路を祈って供える団子です。特徴としては、味付けをせずに供える白玉団子が一般的で、ご先祖様があの世で自由に味付けして楽しめるようにという思いやりが込められています。
団子の形状や数に決まりはなく、丸く一口大に丸めるのが一般的ですが、地域によっては平たく伸ばしたものや複数を串に刺した形も見られます。お供えのタイミングは16日が多いですが、15日に供える地域や家庭もあり、そのあたりは風習に従って柔軟に対応します。
送り火と一緒にお供えすることで、ご先祖様が迷わずに無事帰れるよう導くという意味合いも含まれています。
団子を下げるタイミング
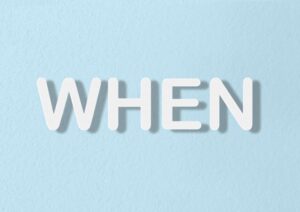
すぐに下げる
お盆の時期は気温と湿度が高く、団子などの供え物が傷みやすいため、供えたらすぐに下げる家庭も多くあります。この場合、お供えの儀式が済んだ直後に団子を片付け、ご先祖様への感謝を込めていただくのが一般的です。
おさがりとして食べる際には、家族で手を合わせてからいただくとより丁寧です。
翌日に下げる
お供えしてから一晩置き、翌朝に下げるという家庭もあります。供え物の状態が良ければ、ご先祖様からのおさがりとして感謝の気持ちを込めていただきます。
もし団子が傷んでいた場合は、白い半紙や清潔な紙で包み、感謝の気持ちを込めて丁寧に処分しましょう。傷んだ供物をそのまま放置するのは不敬とされるため、こまめな確認が大切です。
期間中そのまま
地域によっては、迎え団子をお盆の全期間中ずっとお供えしておく風習がある家庭も存在します。このような場合、団子が傷む可能性が高いため、定期的に状態を確認する必要があります。
もし傷んでいた場合は、できるだけ早く白い紙に包んで感謝を込めて処分するのが望ましいです。迎え団子に限らず、他の供物も同様に注意を払い、ご先祖様への敬意を忘れずに取り扱いましょう。
団子の数や形

形や数に関しては厳密な決まりは設けられていないものの、一般的には丸く一口で食べられるサイズの団子が選ばれることが多く見られます。丸い形には「円満」や「調和」を象徴する意味が込められており、ご先祖様への敬意と感謝を込めて形作られます。
また、団子の形状には地域性や家庭の伝統が色濃く反映されることがあり、平たく押し伸ばしたような形状や、数個を串に刺して並べたもの、さらにピラミッドのように積み上げた形など、見た目にも工夫がこらされた供え方が各地に存在します。
例えば、3段10個や4段20個のように段数と数をそろえて供えることで、ご先祖様をもてなす誠意を表現している家庭もあります。
団子の個数には意味を込めて選ばれることも多く、例えば以下のような例が挙げられます。
- 六道(ろくどう)にちなんで6個(天・人・修羅・畜生・餓鬼・地獄の六つの世界を象徴)
- 十三仏にちなみ13個(故人を導く十三体の仏様に対する祈りを込めて)
- 奇数を縁起良いとし、5個や7個などの数を選ぶ家庭もあります。
お供えの際には「高坏(たかつき)」と呼ばれる、足のついた台が伝統的に使われます。これは供物を清浄な位置に置くためのもので、白い紙を敷いたうえで団子を丁寧に並べるのが作法とされています。
高坏が手元にない場合は、普段使っているお皿を用い、その上に白い紙を敷くことで代用可能です。
お盆の風習は全国的に共通する部分もある一方で、地域ごとに異なる伝統やしきたりが根付いていることも少なくありません。
団子の供え方について不明点や迷いがある場合は、家族や親戚、あるいは近所の年長者などに尋ねてみると、その土地ならではの由来や意味を知る手がかりとなるでしょう。
まとめ|正しい供え方で心を込めたお盆を迎えましょう
お盆に供える迎え団子・送り団子は、ご先祖様への感謝と敬意を表す大切な風習です。地域や家庭によって形や供えるタイミングは異なりますが、意味を理解して丁寧にお供えすることが大切です。
本記事を参考に、今年のお盆はご先祖様に心からのおもてなしをしてみませんか?まずは、ご自身の地域の習わしを確認することから始めてみましょう。