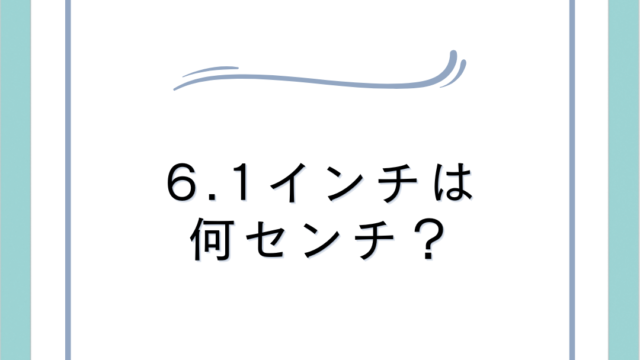再来週の次は何て言う?正しい呼び方とわかりやすい使い分けを解説
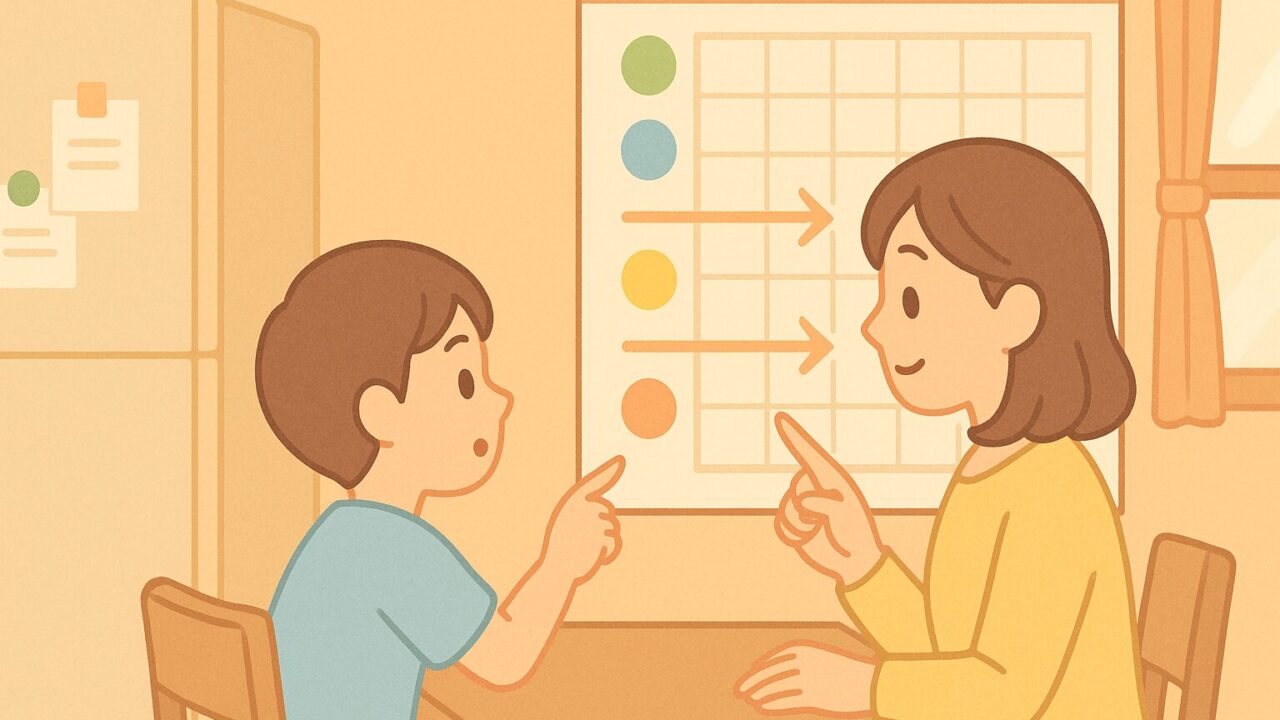
「再来週の次って何て言うの?」と聞かれて、答えに迷ったことはありませんか。私は子どもに予定を説明するときに「来週・再来週」まではスッと出てくるのに、その次になると一瞬言葉に詰まってしまうことがあります。家族での予定や学校行事、旅行の計画を立てるとき、言葉の使い方が曖昧だと混乱してしまいますよね。
この記事では、再来週の次をどう表現すればよいのかをスッキリ整理して解説します。私自身の家庭でのやり取りも交えながら、日常生活ですぐに役立つ表現を紹介していきます。
再来週とはいつのこと?基本の確認

「再来週の次」を考える前に、まず「再来週」とはいつを指すのかを正しく整理しておきたいです。再来週は「来週のさらに次の週」=今日から数えて2週間後に始まる“1週間まるごと”を指します。 ここがブレないと、その先の表現も迷いにくくなります。
来週・再来週の基準をもう一歩ていねいに
一般的に「今週」は、いま自分がいる週の月曜から日曜までをまとめて指します。「来週」はその次の1週間、「再来週」は来週のさらに次の1週間です。
ポイントは2つです。
「◯週間後」は“日付ベース”、一方「来週/再来週」は“週ブロックベース”
例として、今日が水曜日なら「1週間後の水曜日」はちょうど7日後ですが、「来週」は月〜日の“塊”を指します。水曜だけではなく、その週全体を想定しているのが会話上のニュアンスです。週の始まりは家計簿や学校予定では月曜はじまりが多い
カレンダーアプリの設定で日曜はじまりにしていると、家族間で「どこからが来週?」のイメージがズレることがあります。家庭内では「うちは月曜はじまりで数えるね」のようにルールを合わせると便利です。
週の切り方で起きやすい“ズレ”
「再来週」を数えるときのつまずきは、主に週の切り方にあります。
月末と月初をまたぐとき
月が変わると気持ち的に“別もの”に感じますが、週で数える習慣を優先します。「月が変わったから来週?」ではなく、必ず“今週→来週→再来週”の順でブロックをたどるのがコツ。祝日や連休が挟まるとき
連休でカレンダーが短く見えても、1週間のブロックは変わりません。ハッピーマンデーで月曜が祝日でも、その週は“来週1ブロック”として認識します。
カレンダーで確認する具体例
家族カレンダーを月曜はじまりにして、今日が「第1週の水曜」だと仮定します。
今週…第1週(月〜日)
来週…第2週(月〜日)
再来週…第3週(月〜日)
「再来週の次」…第4週(月〜日)
このようにブロックを指でなぞって数えると、子どもにも伝わりやすく、「第3週」「第4週」と週番号で言い換える習慣も身につきます。
「◯週間後」と「再来週」のちがいをもう少し
「2週間後」は“今日から14日後の同じ曜日”をピンポイントで指します
「再来週」は“2週間後に始まる週全体”をゆるやかに指します
例えば、今日が水曜なら「2週間後の水曜」は日にちが1点で決まりますが、「再来週」はその週の月〜日のまとまりを意味します。予定表に書くときは、点かブロックかを意識して表記すると誤解が減ります。
学校・職場・家庭での表現のトーン
学校からのお便りは「第◯週」「◯月◯日週」の表記が多め
仕事のメールは「翌々週(=再来週)」が使われることもありますが、その先は「翌々々週」より「◯月◯日週」「3週間後の週」など具体表現が安全
家庭では「運動会の次の週」「参観日の2週間後が始まる週」のようにイベント基準で言い換えると子どもが理解しやすいです
家庭での会話例をもう少しリアルに
私「運動会は来週の土曜日。その翌週は家でゆっくりしようか」
子ども「じゃあ再来週はのんびり?」
私「うん。再来週はのんびりして、その次の週(第4週)に遠足の準備を始めよう」
夫「カレンダーに“第4週=準備開始”って書いておくね」
この“週番号+できごと”のメモにしておくと、後で「結局いつ?」と聞かれても指差し一発で共有できます。
迷ったときの確認ステップ
家族内の“週の始まり”設定(多くは月曜)を統一する
いま指しているのが“日付の点”なのか“週のブロック”なのかを確認する
カレンダー上で「今週→来週→再来週→再来週の次」と指でブロックを移動する
予定表には「◯月◯日週」や「第◯週」を併記しておく
この4ステップを習慣にすると、「再来週ってどこから?」のモヤモヤがなくなり、学校行事や仕事、家族の準備がスムーズに進みます。
再来週の次をどう呼ぶ?

いよいよ本題、「再来週の次」をどう表現すればよいかを整理します。場面ごとに“誤解の少ない言い方”を選ぶのがコツです。
正式な呼び方はない
結論から言うと、「再来週の次」を一語で示す決まった一般語はありません。
「三来週」「再来々週」などは辞書にもほぼ載らず、口頭で伝えても受け取り手によって解釈が割れがちです。ビジネス文書で見かける「翌々々週」も、読みづらくて会話には不向き。さらに、「次々週」は“再来週”のことなので、その“次”を指す語として使うと必ず混乱します。辞書に定着した単語は存在しないため、意味が一意になる言い換えが原則です。
よく使われる言い方
おすすめは、相手がカレンダーを思い浮かべやすい“具体化”です。
「再来週の次の週」
…週という“塊”を明示。週全体の話(行事・当番・担当)に向いています。「3週間後(の週)」
…“日付の点”ではなく“週の塊”を話すなら「の週」を添えて誤解を防ぐのが安全。「◯月◯日の週」または「第◯週」
…学校プリントや社内共有で強い。週はじめ(多くは月曜)を前提に書くと統一できます。「◯◯(イベント名)の次の週」
…家族の会話で直感的。運動会・発表会・三者面談など、覚えやすい出来事を基準に。
避けたい表現は「三来週」「再来々週」「再々来週」などの造語風の言い回し、そして会話での「翌々々週」。日付や週番号で具体化するのが最も安全です。
私の家庭での使い分け
うちでは、家族カレンダー(月曜はじまり)を冷蔵庫に貼って、場面ごとに言い換えを使い分けています。
子どもに伝えるとき
「運動会の次の週に遠足の準備を始めようね」
イベント基準で“順番”を見せると言葉だけよりスッと入ります。夫婦のタスク調整
「私は3週間後の週にPTA書記、あなたは木曜の送迎お願い」
“週の塊”+具体日で、誰がどの日に動くかを明確に。学校・塾の予定共有(連絡帳・LINE)
「9/16の週に個人面談が入るかも。決まったら日付で送るね」
家庭内ルールも決めています。
1)“週のはじまり=月曜”で統一、2)音声や口頭は「◯月◯日の週」か「イベントの次の週」、3)書き残すときは必ず日付を併記。これだけで、「あれ、それいつの話?」がほぼ消えました。子どもにはイベント基準+週番号の二本立てが特に効果的でした。
似た表現との違い

「再来週の次」をめぐって混乱が起きやすいのは、“日付の点”を指す表現と“週という塊”を指す表現が混在するから。ここでは、よく並べて使われる言葉を丁寧に仕分けします。
三週間後との違い
「3週間後」は“今日から21日後の同じ曜日”という“点”、一方「再来週の次の週」は“週ブロック”を示します。
この違いを意識せずに話すと、1〜数日のズレが発生します。
例1:今日が水曜の場合
・「3週間後」=3週×7日=21日後の水曜をピンポイント
・「再来週の次の週」=その水曜を含む“月〜日”の1週間全体例2:締め日やテスト日など“日付が重要”な予定
→「3週間後の○曜日(=日付)」で指定例3:係当番・持ち物ウィークなど“期間が重要”な予定
→「再来週の次の週」や「◯月◯日の週」で共有
家庭・学校・仕事での使い分けのコツは、
1)“点”なら「◯週間後の◯曜日」
2)“塊”なら「◯月◯日の週/第◯週」
3)口頭では、必ずカレンダーを指差し確認(家族カレンダーがベスト)
翌々週との関係
「翌週=来週」「翌々週=再来週」は定着していますが、その先は一気にわかりにくくなります。
「翌々々週」=“再来週の次の週”に相当。ただし読みづらく、会話では誤解されがち
「次々週」は地域や人によって“来週の次(=再来週)”を指すことが多く、さらにその“次”を表す言葉として使うと混乱のもと
ビジネス文書や学校配布物では、週番号や日付を使うのが無難
例:「9/15の週」「9月第3週」「9/15(月)〜9/21(日)」
現場で迷いをなくす安全策はシンプルです。「翌々々週」や「次々週」のような数え上げ語は避け、必ず「◯月◯日の週」「イベントの次の週」「3週間後の週」のいずれかに“具体化”する。
家庭なら「運動会→(再来週)→その次の週は遠足準備」のようにイベント基準で言い換えると、子どもにも直感的に伝わります。
家族で予定を共有するときの工夫

言葉の定義を理解しても、実際の家庭では「え?それっていつのこと?」が起きがち。予定は“日付+週番号”で具体化し、家庭内の「週は月曜はじまり」を統一するのが最短の近道です。 私の家でうまくいった方法を、すぐ真似できる形でまとめます。
カレンダーに書き込む
我が家では冷蔵庫に家族カレンダー(A3サイズ・月曜はじまり)を貼り、予定は「◯/◯(月)〜◯/◯(日)=第◯週」のように“週の塊”で記入。日付だけでなく週番号を添えると、「再来週の次」が直感的に共有できます。週の上部に色マーカーで横棒を引いて“ブロック化”するのも効果的。子どもには、その週に必要な持ち物を付箋で貼っておくと、自分で剥がしながら準備できます。
会話の工夫
抽象語より、出来事を基準に話すと迷いません。
私「運動会の次の週に、遠足の準備をはじめよう」
子ども「じゃあ“第4週”ね」
夫「木曜は私が送迎担当、カレンダーにも書いておく」
—という具合に、「イベント名→次の週→誰が何をするか」の順で短く伝えると、家族全員が同じイメージを持てます。
色分けとアイコンで“ひと目で”
家族ごとに色(私=青、夫=緑、子ども=オレンジ)を決める
学校行事=旗、保護者会=ペン、通院=ハート、のように手書きアイコンを添える
“週のタスク”は縦線ではなく横ラインで表し、期間であることを強調
視覚的な差をつけると、朝の数秒で全員が予定を把握できます。
紙+デジタルの二刀流
紙:冷蔵庫カレンダー=家族の共通認識を作る場所
デジタル:スマホの共有カレンダー=ピンポイントの時刻・アラーム
たとえば「9/16の週=面談準備」と紙に大きく書き、Googleカレンダーでは「9/18(水)19:00 面談資料印刷」のように“点”の作業にアラームを付けます。紙で俯瞰、デジタルで実行を後押しする分担がうまく働きます。
“家族ルール”を作っておく
週は月曜はじまりで数える
「再来週の次」は“第◯週”か“◯/◯の週”で言い換える
予定は必ず日付と担当者をセットで書く(「誰が」問題を予防)
迷ったらカレンダーの前に集合して“指差し確認”
この4つをキッチンの壁に小さく貼っておくと、ぶれません。
“準備シート”でモレをゼロに
週の左端に「準備チェック欄」を作っておきます(□提出物 □持ち物 □洗濯 □充電)。「第4週=遠足準備」と決めたら、前週の土日にチェックを一気に入れる運用。子どもも自分でチェックできるので、朝の「ハンカチどこ?」が激減します。
朝夕2回の“超短時間ミーティング”
朝:15秒だけ「今日の予定」コール(“点”の確認)
夜:30秒で「今週のやること」共有(“塊”の確認)
長い会議は続きません。秒単位の確認でも、毎日積み上げると行事前の慌てがなくなります。
写真メモと付箋の合わせ技
学校プリントはスマホで撮って、撮影日をファイル名に。大事な一文(提出期限など)は付箋に書いて、プリントのコピーと一緒にカレンダーへ。期限が過ぎた付箋は子どもが自分で剥がす“ご褒美ルール”にすると、主体性が育ちます。
うまくいかなかったときの見直しポイント
「週のブロック」と「◯週間後(同じ曜日)」が混在していないか
週番号を付け忘れていないか
デジタルの通知が“家族全員に届く設定”になっているか
付箋や色分けが増えすぎて、かえって見づらくなっていないか
月末に5分だけ振り返って、翌月の運用ルールを微調整すると、定着が一気に進みます。
この仕組みを回しはじめてから、わが家では「それっていつ?」の質問が目に見えて減りました。カレンダーを中心に、“週の塊”と“日付の点”を行き来できるようになると、「再来週の次」も迷わず伝えられます。
学校や仕事での表現のしかた

家庭だけでなく、学校や職場でも「再来週の次」をどう伝えるかは迷いポイント。場面ごとに“誰に・何を・どの粒度で”伝えるのかを決めておくと、行き違いが減ります。ここでは学校(保護者間/先生⇄家庭)と仕事(社内/社外)に分けて、実例ベースで整理します。
学校のお便りでは?
学校文書は“学年全員に同じ情報を同じ形で届ける”のが大前提。表現は「週番号」か「◯月◯日週」の固定フォーマットが基本です。迷う表現(翌々々週・三来週など)は避け、週の塊を日付で明示するのが鉄則。
よくある表記
・「◯月第3週 保護者面談」
・「9/16の週:授業参観」
・「9/30(月)〜10/6(日)=後期オリエンテーション週」先生⇄保護者の連絡帳での書き方例
・先生:「9/16の週に面談希望日を回収します」
・保護者:「9/16の週は出張のため、面談は9/19(木)17時以降が希望です」プリント作成のコツ
① 週の開始日(多くは月曜)を小さく併記「(週開始:9/16)」
② 期間表現は“日付の範囲”+“目的”:「9/16〜9/22=面談調整」
③ 児童向けにはアイコン(面談=吹き出し、行事=旗)を添えて視覚化
親同士のLINEでも学校の表記を踏襲すると誤解が激減します。
例:「遠足は9/30の週だよね? うちは水曜に弁当2個コースかも」
保護者間の調整(PTA・係・習い事)
PTAや習い事は“人によってカレンダー設定が違う”のが難所。共通の言い方を先に決めてから本文に入るのが安全です。
冒頭の“基準宣言”テンプレ
「本スレでは、週は月曜はじまり、週の表現は『◯月◯日週』で統一します」当番・持ち回りの伝え方
「清掃当番は10/7の週:1年A組/10/14の週:1年B組」
「配布準備は3週間後の週(10/21の週)に実施」変更多発のときの保険文
「※雨天順延時も“週表現”は維持し、具体日だけ差し替えます」
仕事ではどうする?(社内)
社内は“点(締切・会議)”と“塊(開発スプリント・販促週)”が混在します。メールや議事録は必ず日付を併記し、「翌々々週」などの数え上げ語は避ける。
メール件名テンプレ
「【スケジュール確認】9/30の週のレビュー会について」
「【依頼】3週間後の週(10/21の週)にβ版テスト」本文の言い回し
「“再来週の次”に該当する10/21の週でレビュー実施を想定。候補日は10/22(火)15:00です」
「“3週間後”は点の指定になるため、週単位の作業は“◯◯の週”で記載します」会議中の口頭確認
「点の締切は10/23(水)、塊の作業は10/21の週に集約、で合ってますか?」
スプリント運用(2週間サイクルなど)の現場では、「Sprint 14:10/7〜10/20」「Sprint 15:10/21〜11/3」とスプリント名+日付範囲で管理し、「再来週の次」は“次スプリントの前半”など構造で言い換えると共有が速いです。
仕事ではどうする?(社外・取引先)
社外は前提(週の始まり・祝日の扱い)が一致していない前提で書きます。誤解防止のため、日付の範囲+曜日+タイムゾーンをセットに。
オファー例
「御社のレビューご希望タイミング“再来週の次”につき、10/21(月)〜10/25(金)JSTで候補を2枠ご提示します」
「候補① 10/22(火)15:00-15:45 JST/候補② 10/24(木)10:00-10:45 JST」稟議・納期の明記
「納品は3週間後の週(10/21の週)に前倒し可能です。検収締切は10/25(金)でお願いします」
“翌々々週”を使いたくなる場面でも、社外向けは避けたほうが無難。代わりに「10/21の週」「3週間後の週」と書くと、伝達精度が上がります。
カレンダー運用(共通の型)
件名(タイトル):目的+「◯月◯日週」
本文1行目:週の開始日・終了日・曜日(例:10/21(月)〜10/27(日))
次行:点の予定(締切・会議)を箇条書き(例:10/23(水)提出、10/25(金)校了)
備考:週は月曜はじまり、祝日は含む/含まない、の注記
この“型”にしておくと、学校・仕事どちらでもすぐ流用できます。結果、私の家では「再来週の次」を巡る行き違いがほぼゼロに。「週=塊」「◯週間後=点」の違いを踏まえ、どちらも必ず日付で裏づける——これだけで連絡の質が一段上がりました。
まとめ|「再来週の次」は具体的に言い換えて伝えよう
「再来週の次」にあたる言葉には、正式な呼び方が存在しません。だからこそ、「3週間後」「再来週の次の週」「〇月〇日の週」など具体的な表現に置き換えることが大切です。家庭ではカレンダーや出来事を基準に伝えると、子どもにもわかりやすくなります。もし会話で迷ったら、「日付で確認する」習慣を取り入れてみてください。予定がスッキリ整理されて、家族の時間ももっと心地よく過ごせるはずです。