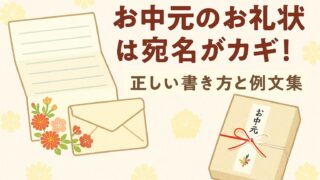土用の丑の日の由来を簡単に解説!なぜうなぎを食べるの?
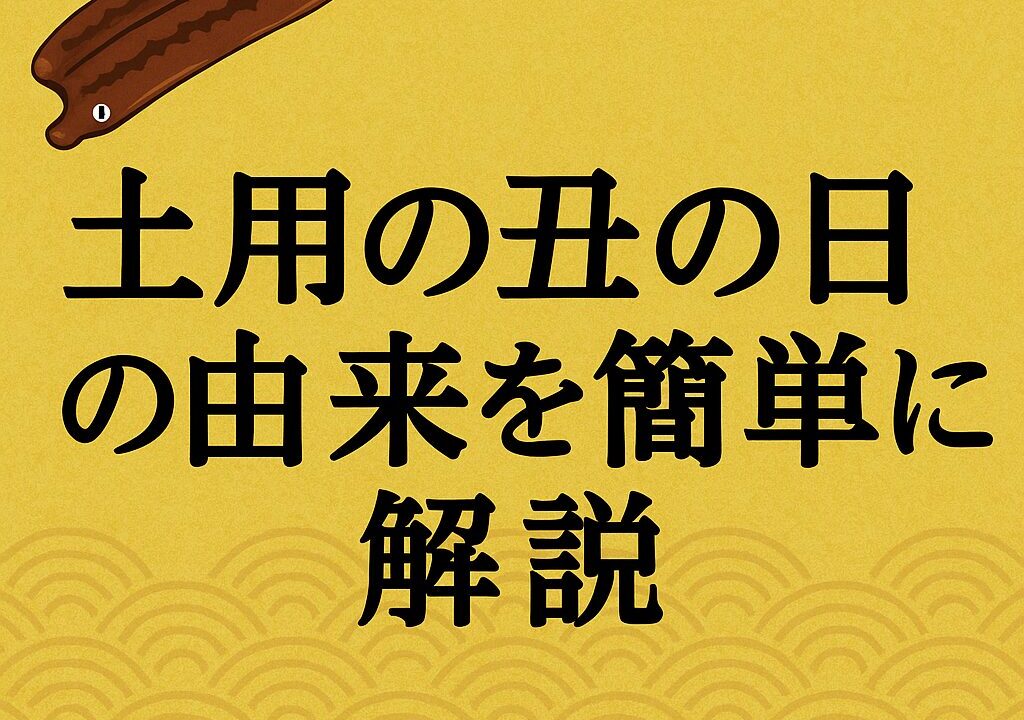
毎年夏になると話題になる「土用の丑の日」。でも、どうしてこの日にうなぎを食べるのか、意外と知らないという方も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、土用の丑の日の由来を簡単に知りたい方へ向けて、その歴史や意味、風習の背景をわかりやすく解説します。
子どもにも話せる豆知識から、現代の食文化とのつながりまで、読むだけで「なるほど」が詰まった内容です。今年の丑の日は、知識も一緒に味わってみませんか?
土用の丑の日の意味

土用とは何か
「土用(どよう)」とは、実は四季それぞれに存在する特別な期間で、立春・立夏・立秋・立冬の直前の約18日間を指します。これは中国の五行思想をもとにした暦の考え方で、春・夏・秋・冬のそれぞれの季節の移り変わりに「土」の気が強くなるとされることから、「土用」と呼ばれています。
つまり、「土用の丑の日」という言葉を聞くと夏を連想しがちですが、実際には春土用・夏土用・秋土用・冬土用と年に4回存在します。その中でも、特に夏土用が重要視されるのは、体力が落ちやすい時期であり、季節の変わり目に健康を意識する生活の知恵が込められているからです。
丑の日の由来
「丑の日」とは、十二支(子・丑・寅…)を日に割り当てた「干支日(えとび)」のひとつで、土用期間中に巡ってくる「丑」に当たる日のことを指します。暦上では約12日に一度「丑の日」が回ってくるため、土用の期間中に2回訪れる年もあり、その場合は「一の丑」「二の丑」と区別されます。
この十二支による日付の表現方法は、古くから日本人の生活リズムや暦文化に深く根ざしており、吉凶を占う目安としても用いられてきました。「土用の丑の日」はその文化の中で、特定の季節に特別な食事を摂るという風習と結びつき、現代まで受け継がれています。
土用の丑の日の季節
「土用の丑の日」といえば、現在では主に夏の土用にあたる丑の日を指すのが一般的です。具体的には、毎年7月20日前後から始まる夏土用の期間中に訪れる丑の日のことをいいます。この時期はちょうど梅雨明けの頃とも重なり、気温と湿度が一気に高まり、体力や食欲が落ちやすい季節です。
こうした季節の変わり目に体調を整えるために、スタミナのつく食べ物を食べるというのが「土用の丑の日」の大きな目的のひとつ。現在では「うなぎ」が代表的な食べ物として知られていますが、他にも“う”のつく食材(うどん、梅干し、うり など)を取り入れる風習もあります。
土用の丑の日の由来

平賀源内と土用の丑の日
「土用の丑の日 由来 簡単」というキーワードの背景には、江戸時代の発明家・平賀源内(ひらがげんない)の逸話が語られることが多くあります。
夏になると売れ行きが落ちて困っていた鰻屋が、源内に相談を持ちかけたのがきっかけです。そこで源内は「丑の日には“う”のつく食べ物を食べると良い」という言い伝えを活かし、「本日、土用の丑の日」という貼り紙を店頭に出すことを提案しました。
この広告が大当たりし、多くの人々が「丑の日にはうなぎを食べよう」と集まるように。これをきっかけに、「土用の丑の日=うなぎを食べる日」というイメージが、江戸庶民の間で一気に広まりました。今でいうマーケティングやブランディングの先駆けともいえるこの施策は、日本の食文化にも大きな影響を与えたとされています。
江戸時代の風習
江戸時代の人々は、今のようにエアコンのない時代を、食事や生活の工夫によって乗り越えていました。とくに夏の暑さは体力を奪い、食欲不振や寝苦しさが日常的に起こる時期。そこで注目されたのが、うなぎをはじめとする栄養価の高い食材です。
当時の人々は経験的に、栄養のあるものを食べて夏を乗り切る知恵を身につけており、**「土用の丑の日に精のつくものを食べる」**という風習が徐々に定着しました。うなぎに限らず、「うり」「うどん」「梅干し」など、“う”のつく食べ物を食べて、暑さを払うという考え方も根強く残っています。
このような民間療法的な食文化の発展が、現代の「夏バテ予防」「スタミナ食」という概念に繋がっているともいえるでしょう。
土用の丑の日にうなぎを食べる理由
現在に至るまで、土用の丑の日にはうなぎを食べる文化が根強く残っていますが、その理由は味だけではありません。うなぎには、ビタミンA、B1、B2、D、E、カルシウム、鉄分、DHA、EPAなど、身体に嬉しい栄養素がたっぷり含まれています。
特に夏は、汗によって失われるミネラルが不足しがち。うなぎにはそれらを補う効果があり、食欲増進・疲労回復・免疫力アップといった機能性が注目されています。まさに、昔の人が理にかなった健康法としてうなぎを選んでいたことが分かります。
また、現代の研究でも、うなぎの脂質には脳の働きをサポートする成分が含まれており、「夏の脳疲労対策」としてもうなぎは有効な食材と言えるでしょう。
土用の丑の日の風習と食文化

日本での土用の丑の日の広がり
「土用の丑の日」の風習は、江戸時代に平賀源内が広めたとされるマーケティング的な発案から始まりましたが、その影響は江戸の町人文化にとどまらず、やがて全国へと広がっていきました。当時の人々は、猛暑の中で食欲や体力が落ちる時期に栄養のあるものを食べることの大切さを実感していたため、この風習は理にかなっており、自然に根付いていったのです。
現在では、全国のスーパーや飲食店、百貨店、さらには道の駅などでも「土用の丑の日フェア」や「うなぎ祭り」が開催され、この行事は夏の風物詩としてすっかり定着しています。特設コーナーや限定メニュー、早割予約など、商業的イベントとしても大きな盛り上がりを見せており、地域経済にもプラスの影響を与えています。
さらに学校や保育園でも、季節行事の一環として紹介されることがあり、食育や伝統文化を学ぶ機会としても活用されるようになっています。このように、「土用の丑の日」は今や全国規模で認知された多層的な文化イベントと言えるでしょう。
うなぎ以外の食べ物
「土用の丑の日」といえばうなぎが代表格ですが、実はそれ以外にも「うのつく食べ物を食べると夏バテしにくい」という風習が古くから伝えられています。これは、語呂合わせによる縁起担ぎであり、バリエーション豊かな食文化として現代にも引き継がれています。
代表的な“う”のつく食材には以下のようなものがあります:
うどん:消化が良く、暑い日でも食べやすい。冷やしうどんは特に人気。
梅干し:クエン酸が疲労回復や殺菌作用に優れ、熱中症予防にも効果的。
瓜(うり)類:きゅうりや冬瓜など。体の熱を冷まし、水分補給に最適。
牛肉・馬肉(うま):地方によっては、スタミナ源として食べられることも。
また、最近ではベジタリアン・ヴィーガンの方にも対応した「うなぎもどき」食品(豆腐やこんにゃく製)も人気です。食べるものに制限がある方も、こうした“う”のつく代替食材を選ぶことで、風習の意味を取り入れながら健康的に楽しむことが可能になっています。
土用の丑の日の人気
近年、SNSの普及によって「土用の丑の日」はさらに注目度を増しています。InstagramやX(旧Twitter)などでは、「#土用の丑の日」「#うなぎの日」「#スタミナ飯」などのハッシュタグとともに、美味しそうなうなぎの写真や食卓の投稿が毎年トレンド入りするほどです。
また、うなぎ弁当や限定スイーツなど、“映える”ビジュアルの商品が続々と登場することで、若年層にも広く受け入れられています。各地の飲食店でも、「丑の日限定メニュー」や「土用のうなぎ御膳」などが提供され、予約がすぐに埋まる人気ぶりを見せています。
飲食業界では、この時期を夏の最重要イベントと位置づけており、売上全体の大きな割合を占める「商機」としても非常に重要です。
このように、「土用の丑の日」は今や食文化・マーケティング・SNSのトレンドが融合した、季節感と話題性を兼ね備えた日本独自の文化行事となっています。
土用の丑の日に食べる料理

日本での土用の丑の日の広がり
「土用の丑の日 由来 簡単」というテーマを語るうえで欠かせないのが、この風習の広がりです。江戸時代に平賀源内が火付け役となって広まった「丑の日にうなぎを食べる」という習慣は、庶民の間で急速に定着していきました。
明治・大正時代を経て、やがてこの風習は全国へと波及。現代では、夏の訪れを知らせる風物詩のような存在として、全国のスーパーや百貨店、コンビニでも「土用の丑の日フェア」が開催されるようになりました。
特に飲食業界においては、この時期のうなぎ関連商品の売上が1年のうちでもトップクラスを記録するなど、一大イベントとして経済的な影響力も持つようになっています。
このように「土用の丑の日」は、単なる食習慣にとどまらず、文化・経済・観光などにも関わる日本の夏の重要な行事として発展してきたのです。
うなぎ以外の食べ物
「土用の丑の日」といえばうなぎが定番ですが、実はうなぎ以外にも、「う」のつく食べ物を食べるとよいとされる伝統があります。これは昔から「“う”がつくものを食べると暑さに負けない」という言い伝えがあり、夏の土用に取り入れられてきた知恵のひとつです。
代表的なものには、以下のような食材があります:
うどん:消化に優れ、暑い日でも食べやすい
梅干し:殺菌作用と疲労回復効果がある
瓜(うり)類:水分が豊富で体を冷やす働きがある
特に梅干しは、古来から薬用としても用いられてきた食材で、暑さで弱った胃腸を整え、熱中症予防にも効果的だといわれています。うなぎが苦手な方や食生活の選択肢を広げたい方にとって、「うのつく食べ物で夏を乗り切る」という考え方は、非常に柔軟で現代的とも言えるでしょう。
土用の丑の日の人気
現代においても「土用の丑の日」の人気は衰えることなく、むしろ年々注目が高まっています。SNSでは「#うなぎの日」などのハッシュタグが毎年トレンド入りし、うな重やひつまぶしの写真が多数投稿されるなど、ビジュアル的にも“映える”夏の食文化として親しまれています。
また、企業や自治体もこの日に合わせてキャンペーンや特集企画を展開し、土用の丑の日はマーケティング的にも重要なシーズンとなっています。特に暑さが厳しくなる7月下旬というタイミングと相まって、「スタミナ食を楽しむ日」として多くの人に意識されているのです。
日本の四季や暦に根差したこの風習は、今後も新しい形で進化しつつ、多くの人々に受け継がれていくことでしょう。
土用の丑の日の時期

2025年の土用の丑の日
2025年の夏の「土用の丑の日」は、7月24日(木)に当たります。これは夏の土用期間(2025年は7月19日〜8月6日)のうち、十二支が「丑」にあたる日です。毎年この日は、全国のスーパーや百貨店、飲食店でうなぎの特売セールやフェアが開催され、うなぎ料理が注目を集めます。
「土用の丑の日 由来 簡単」という観点から見ても、現代の人々が土用の丑の日をどのように楽しんでいるかを知ることは大切です。特に2025年は木曜日という平日にあたるため、仕事帰りにうなぎ弁当を購入したり、外食で味わったりする人も多くなると予想されます。
毎年の変わり目
土用の丑の日は毎年決まった日ではなく、年ごとに日付が変わるのが特徴です。これは、旧暦(太陰太陽暦)と干支(十二支)の暦の組み合わせによるもの。具体的には、土用の約18日間の期間中に「丑」にあたる日を探し、その日が「土用の丑の日」となります。
そのため、土用の開始日や丑の日の巡りによって、毎年1〜2日のズレが生じます。この変化も、季節を感じる日本ならではの暦文化の一部です。「土用の丑の日 由来 簡単」と検索する方にとっても、「なぜ毎年日付が違うのか?」という疑問に対する納得感ある答えになるでしょう。
二の丑とその重要性
土用の期間が18〜19日とやや長いため、年によってはその間に丑の日が2回巡ってくることがあります。その場合、1回目を「一の丑」、2回目を「二の丑」と呼びます。
2025年には「二の丑」は該当しませんが、年によっては7月下旬と8月初旬に2回うなぎを食べる機会が訪れることになります。
「二の丑」も「一の丑」と同様に、うなぎを食べて夏バテを防ぐ日として定着しており、飲食業界でも再びキャンペーンが行われるなど、夏の商戦が延長されるタイミングでもあります。
また、「二の丑」にちなんでうなぎ以外の“う”のつく食べ物を楽しむ家庭もあり、現代ではより自由に、柔軟にこの行事を楽しむスタイルが広がってきています。
土用の丑の日に関する習慣

地域ごとの違い
「土用の丑の日=うなぎ」というイメージは全国的に定着していますが、地域によっては必ずしも“うなぎ一択”ではありません。例えば、長野県や山形県では“鯉”や“どじょう”を食べる風習がある地域も存在します。これらの魚もスタミナ源として親しまれ、地域の食文化に根ざした選択肢となっています。
また、九州ではうなぎの蒲焼だけでなく「白焼き」や「せいろ蒸し」が主流の地域もあり、調理法や味付けにも土地柄が表れています。地域特有の気候、食材の流通、宗教・歴史的背景が反映されているのも興味深いポイントです。
このように、「土用の丑の日の由来を簡単に知る」ことは、その土地ごとの文化や生活の知恵を知るきっかけにもなります。
関東と関西の風習
「うなぎの捌き方」にも地域による違いがあります。代表的なのが、関東では背開き、関西では腹開きというスタイルの違いです。
これは単なる調理法の違いではなく、江戸時代の文化的背景が影響しています。関東では「腹を割く=切腹」を連想させることから、武士の多い江戸では背開きが主流になりました。一方で、商人文化の根付いた関西では、そうしたイメージを気にする風習が薄く、調理しやすい腹開きが好まれていたとされています。
また、蒸してから焼く関東風、直火焼きの関西風という違いもあり、うなぎの食感や風味が異なるのも魅力のひとつ。こうした調理法の違いも「土用の丑の日」の地域性を感じさせる文化です。
土いじりと農作業との関係
「土用」の語源に由来する通り、この期間には「土にまつわる作業を避けるべき」とする風習も根強く残っています。これは、「土公神(どこうしん)」と呼ばれる土の神様がこの時期に土の中に宿っているとされ、穴を掘る・畑を耕す・庭木を植えるといった“土を動かす行為”は神様を怒らせると考えられていたためです。
現代においては科学的根拠こそ薄いものの、建築や造園、農業などを営む方の中には、今もこの時期を避けてスケジュールを組む方もいます。
また、土を休ませるという考え方には、「自然との調和」や「休養を取り入れる生活の知恵」という側面もあり、持続可能な暮らし方のヒントにもなっています。
土用の丑の日の活動とイベント

地域の行事やイベント
「土用の丑の日」は、ただうなぎを食べるだけのイベントではありません。全国各地では、この時期にあわせてうなぎ祭りやスタミナ食フェア、地域の特産品を活かした観光イベントなどが盛んに開催されています。
例えば、静岡県浜松市や鹿児島県大隅地域では、うなぎの産地として知られ、毎年「うなぎまつり」や試食会、直売イベントなどが行われています。これらのイベントは、地域経済の活性化だけでなく、地元食文化の発信にもつながっており、観光誘致にも一役買っています。
また、道の駅や観光施設でも「土用の丑の日限定メニュー」や「ご当地うなぎ弁当」が販売され、夏の風物詩として地元の人々や観光客に親しまれています。
このように、土用の丑の日は地域文化の一部としても活用され、年々その存在感を増しているのです。
土用の丑の日の効果
「土用の丑の日」は、単なる伝統的な風習としてだけでなく、季節の変わり目に自分の健康と向き合う“節目の日”としての役割も担っています。
特に夏の土用は、梅雨明け直後の蒸し暑さや、夏バテ・食欲不振が起こりやすいタイミング。この時期に栄養価の高い食べ物を意識して摂ることで、体調を整え、秋への備えを始めるという日本古来の生活の知恵が根底にあります。
さらに「う」のつく食べ物を食べるという言い伝えには、言霊や縁起担ぎ的な意味合いもあり、「運気を呼び込む」「邪気を払う」といった考え方ともリンクしています。
このように、土用の丑の日には、身体面だけでなく精神的なリセットの意味も含まれているのです。
健康促進のための工夫
土用の丑の日は、「今日はうなぎを食べる日」としてだけでなく、健康を意識するきっかけになる日として注目されています。この日を機に、普段の生活習慣を見直す人も少なくありません。
例えば:
食生活:うなぎに含まれるビタミンやミネラルで栄養補給をし、バランスのよい食事を意識
睡眠習慣:夏バテ予防のため、早寝早起きや睡眠時間の確保を見直す
適度な運動:気温の高い日でも無理せず、室内でのストレッチや軽い運動を取り入れる
また、現代では「うなぎを食べられない人向けの代替食(豆腐、山芋、玄米など)」や「ベジタリアン対応の“うなぎ風メニュー”」も登場し、より多様な健康志向に対応した楽しみ方も広がっています。
土用の丑の日は、昔ながらの知恵と現代的なライフスタイルが交差する、健康づくりの節目として今後さらに注目されていくでしょう。
土用の丑の日についての情報発信

Webでの広報活動
近年では、「土用の丑の日」をテーマにしたWeb上でのプロモーション活動が活発に行われています。特にスーパーや飲食店、うなぎ専門店などは、公式サイトやSNS(Instagram、X〈旧Twitter〉、Facebookなど)を活用してキャンペーンを展開。
たとえば、「うなぎ弁当の予約受付中」「土用の丑の日限定メニュー」「早期予約割引」など、特別感を演出する情報発信が多く見られます。
また、SNSではハッシュタグ「#土用の丑の日」「#うなぎの日」などがトレンド入りすることもあり、写真や動画を活用した“映える”投稿が購買意欲を刺激します。
企業にとっては、この機会を「夏の集客チャンス」として最大限に活かしており、LINEクーポンの配布やメルマガでの告知など、多面的なデジタル戦略が組まれています。
こうしたWebプロモーションは、リアルな来店・購買行動に直結する効果的な広報手段として定着しています。
エディトリアルな視点
「土用の丑の日 由来 簡単」という切り口は、単なる食の話題にとどまらず、日本の文化・歴史・季節行事を語るうえで非常に魅力的なテーマです。そのため、新聞社・雑誌・Webメディアなどでは、毎年この時期に特集記事やコラムが組まれています。
たとえば、「平賀源内が仕掛けたマーケティングのルーツ」「うなぎ文化の地域差」「夏の行事としての意味」など、教養・知識・食文化を組み合わせた読み物コンテンツとしても人気があります。
近年では、エディトリアル記事に加えて、インフォグラフィックや図解によるわかりやすい解説記事も増加傾向にあり、学校教育・自由研究の参考資料としても活用される場面が増えています。
こうした情報発信は、単なるグルメ情報にとどまらず、日本の季節感や伝統行事を再発見するきっかけにもなっています。
メディアでの取り上げ
「土用の丑の日」は、毎年テレビやラジオ、新聞などのマスメディアでも定番の季節ネタとして取り上げられる話題です。
ニュース番組では、うなぎの仕入れ状況や価格の変動、人気店の行列、予約状況などを紹介し、季節の風物詩として映像で伝えることが多くあります。
また、バラエティ番組や情報番組では、「うなぎの名店ランキング」や「コンビニのうなぎ弁当食べ比べ企画」など、視聴者の関心を引くコンテンツとしてアレンジされることも。これにより、「土用の丑の日=夏の大イベント」というイメージがより一層強まっています。
さらには、YouTubeやTikTokといった動画メディアでもうなぎ調理の様子や食レポがアップされ、若年層にもアプローチが広がってきています。
こうしたメディアの多角的な取り上げにより、土用の丑の日はあらゆる世代に浸透し、文化として深く根付いていることがわかります。
土用の丑の日の使用と販売

うなぎ屋の経済効果
「土用の丑の日」は、うなぎ業界にとって年間最大の繁忙期です。この日を迎えると、全国のうなぎ店や和食店、テイクアウト専門店の売上が一気に跳ね上がります。一部の老舗店では、1日の売上が普段の10倍以上に達することもあるほどです。
飲食店だけでなく、水産卸業者や流通業界、包装資材メーカーなどもこの時期に向けて準備を進めるため、まさに業界全体が“書き入れ時”となるのがこのタイミング。また、スーパーや百貨店では予約販売や数量限定商品を用意し、事前のプロモーションにも力を入れます。
このように、土用の丑の日は季節行事でありながら、大きな経済効果をもたらす日本の商習慣の一部として確固たる地位を築いているのです。
関連商品とギフト文化
うなぎ料理の需要が高まるこの時期には、蒲焼きや白焼き、ひつまぶしセットなどの加工品が各地で販売され、家庭用・贈答用の両方で人気を集めています。特に真空パックされたうなぎセットは、日持ちがよく全国発送もしやすいため、夏のギフト商品として重宝されています。
また、健康志向の高まりを背景に、栄養ドリンクやスタミナ系サプリメント、夏バテ防止食品とのセット販売も増えており、企業やブランドは「健康×季節行事」をテーマにした商品展開を行っています。
「土用の丑の日 由来 簡単」と調べる方にとっても、贈り物としてのうなぎの選び方や、地域の特産品との組み合わせ方などの情報は実用的で価値の高い内容となります。
このような食とギフトの融合文化は、現代のライフスタイルにもマッチし、年々その市場規模を拡大させています。
食文化の選択と活用
「土用の丑の日」は、単なるグルメイベントではなく、**暑さを乗り切るための“食の知恵”としての役割も果たしています。**伝統的なうなぎだけでなく、牛肉、豚肉、山芋、納豆、にんにく、しじみなどのスタミナ食材を取り入れる動きも広がっています。
特に最近では、ヴィーガンやベジタリアン向けの“うなぎ風”食品(豆腐やこんにゃくで作った蒲焼風など)の需要も高まり、食の選択肢がますます多様化。健康志向やアレルギーへの配慮も進み、より多くの人が自分に合った形で「土用の丑の日」を楽しめるようになっています。
このように、伝統行事を柔軟にアレンジし、現代の食生活に取り入れる文化は、季節を意識するライフスタイルの一環としても注目されています。
「土用の丑の日 由来 簡単」という入り口から、自分や家族に合ったスタイルで夏を乗り切る食の工夫を学べることも、この行事の魅力のひとつです。
まとめ|今年の土用の丑の日は由来を知って楽しもう
「土用の丑の日 由来 簡単」という視点から見ていくと、うなぎを食べる風習には、歴史や健康への配慮といった深い意味があることがわかります。
単なる季節のイベントとしてだけでなく、日本の風土や知恵が詰まった伝統文化として、今一度その背景に目を向けてみるのもおすすめです。
2025年の土用の丑の日には、ぜひ由来を知ったうえで、うなぎや旬の食材を味わいながら、夏のパワーチャージをしてみてください。