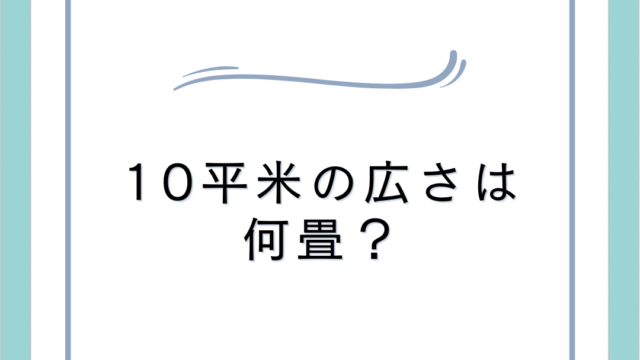感謝を伝える一筆箋:親戚への贈り物の必需品
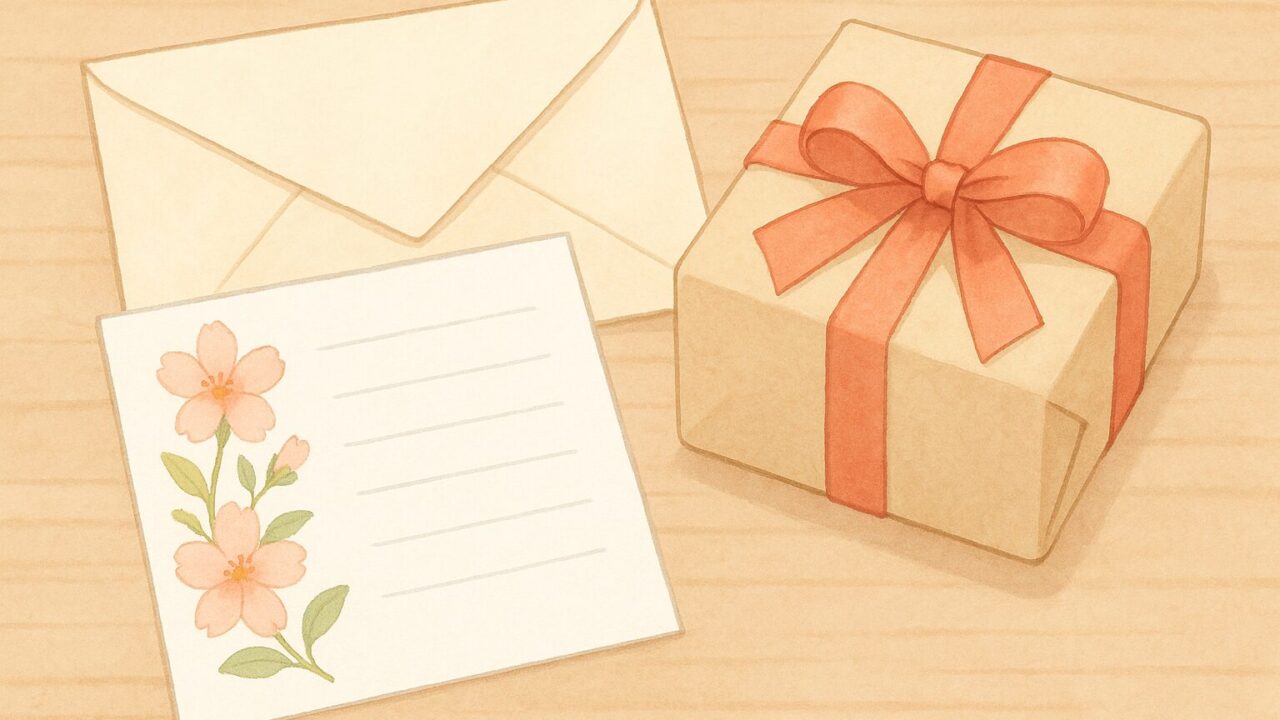
贈り物を送るとき、「何かひと言添えたいな」と思うこと、ありますよね。とくに親戚への贈り物は、日頃の感謝や近況を伝える良い機会。でも、手紙ほど長い文章は書きづらい…そんなときに頼りになるのが「一筆箋」です。
たった数行でも心を込めれば、相手の印象はぐっと良くなります。この記事では、親戚への贈り物に添える一筆箋の基本マナーや文例、選び方のポイントを、私の体験を交えながらご紹介します。形式ばらずに、あたたかい気持ちを伝えたい方にぴったりの内容です。
感謝を伝える一筆箋の魅力
一筆箋とは?その基本と特徴
一筆箋(いっぴつせん)とは、贈り物やお礼などに添える短いメッセージ専用の便箋のことです。わずか数行でも想いをしっかりと伝えられるため、手紙ほど堅苦しくなく、気軽に使えるのが魅力です。
「わざわざ手紙を書くほどでもないけれど、感謝は伝えたい」──そんなとき、一筆箋はまさにぴったりの存在です。
私も最初の頃は、「数行で本当に伝わるかな?」と少し不安でした。けれど、贈り物に一筆箋を添えたところ、親戚から「丁寧に書いてくれて嬉しかった」と言ってもらえたことがありました。それ以来、贈り物には必ず一筆箋を添えるようにしています。
特別な表現や難しい言葉を使う必要はありません。むしろ、“自分の言葉でまっすぐに書く”ことこそ、一筆箋の魅力です。
形式にとらわれず、素直な感謝の気持ちを数行に込めるだけで、相手に温かさが伝わります。
また、一筆箋にはサイズ感のメリットもあります。封筒や贈答品の箱にもすっと収まり、見た目にもスマート。受け取る側も負担に感じないちょうど良さがあります。忙しい現代では、この「気軽さと誠実さのバランス」が多くの人に支持されている理由です。
贈り物に添える手紙文例の重要性
贈り物は「モノ」ですが、そこに心を添えるのが本当の思いやりです。どんなに小さなプレゼントでも、ひと言添えるだけで、ぐっと印象が変わります。
特に親戚への贈り物は、久しぶりのやりとりになることも多いため、「元気にしているかな」「喜んでくれるかな」といった気持ちを込めることが大切です。
たとえば、
「季節のご挨拶としてお送りいたします。お身体に気をつけてお過ごしください。」
「いつも温かく見守ってくださり、ありがとうございます。ささやかですが、お好きなものを選びました。」
など、季節感や感謝を交えた表現を取り入れると、言葉に奥行きが出ます。
また、相手の好みや近況を知っている場合は、それを踏まえた一言を加えるのもおすすめです。
「以前お好きだとお話しされていたお菓子を見つけました。お口に合えば嬉しいです。」
といったように、相手のことを思い出しながら選んだことが伝わると、心に響くメッセージになります。
贈り物と一筆箋は、セットで「心遣い」を表すもの。だからこそ、言葉選びは丁寧に、短くてもあたたかい一文を添える意識を持ちましょう。
一筆箋の書き方とマナー
一筆箋は短文だからこそ、書き方の基本を押さえることで、印象が大きく変わります。ポイントは3つのステップです。
季節の挨拶
季節感を取り入れた一文を最初に入れると、やわらかい雰囲気になります。
例:「朝晩の冷え込みが感じられるようになりましたね。」本題(贈り物について)
贈り物を贈る理由や、相手への思いを添えます。
例:「ささやかですが、感謝の気持ちを込めてお送りいたします。」結びの言葉
健康や幸せを願う一言で締めくくると、印象がより丁寧になります。
例:「お身体に気をつけてお過ごしくださいませ。」
この流れを守るだけで、読みやすく、誠実な文章になります。
特に重要なのは、「感謝」と「気遣い」の言葉を欠かさないこと。形式的な挨拶だけで終わらせず、「あなたのことを思っています」という気持ちを込めるのがコツです。
また、筆記具にもマナーがあります。黒や濃い青のボールペン・万年筆を使いましょう。色ペンや鉛筆はカジュアルすぎる印象になり、フォーマルな贈り物には不向きです。
書き損じた場合は、修正ペンではなく新しい用紙に書き直すのが基本です。小さな紙だからこそ、一枚一枚に丁寧さが伝わります。
私は、書く前に一度下書きをして、伝えたい言葉を整理するようにしています。「感謝」と「季節のひとこと」をセットで入れると、自然な流れになるのでおすすめです。
親戚への贈り物に最適な一筆箋
贈り物に適した一筆箋の選び方
親戚への贈り物には、落ち着いた色味や季節感のあるデザインが安心です。桜・若葉・朝顔・紅葉・雪の結晶など、季節のモチーフは上品にまとまり、年配の方にも受け入れられやすい印象になります。和紙風やコットン紙など、指先でわずかに凹凸を感じる質感は、短い言葉でも存在感が出ます。
私が選ぶときの基準は三つです。
相手基準の雰囲気(年齢・好み・関係性)
季節のモチーフと色の調和(濃色は控えめ、淡色で清潔感)
文字が映える余白と罫幅(小さめの字なら細罫、ゆったり書くなら無罫)
さらに、縦書きベースならより改まった印象に、横書きベースなら親しみやすさが出ます。香り付きや派手な箔押しは好みが分かれるため控えめに。インクがにじみにくい紙かどうか、試し書きで確認しておくと安心です。
迷ったら「相手基準」──デザインよりも相手が受け取りやすい落ち着きと書きやすさを優先します。
親戚へのメッセージ例
関係性や場面に合わせて、最初の一文で要件、二文目で配慮、最後に体調や生活を気づかう言葉を添えると自然にまとまります。
定番のお礼
「いつも気にかけてくださり、ありがとうございます。ささやかですが、皆さまで召し上がっていただける品をお贈りします。お変わりなくお過ごしください。」近況をひとさじ
「こちらは朝晩ひんやりしてきました。季節の味を少しお送りしましたので、温かいお茶のおともにどうぞ。」年配の親戚へ配慮を込めて
「日頃のご厚情に感謝しております。柔らかい口当たりのものを選びました。どうぞ無理なさらずご自愛ください。」子育て世帯のいとこへ
「忙しい毎日に少しでも楽してもらえたらと思い、すぐ使える日用品を送ります。みんなで使ってくださいね。」お世話になったお礼(やや改まって)
「先日は温かいお心遣いを賜り、誠にありがとうございました。心ばかりの品ではございますが、お納めいただければ幸いです。」親しい間柄のカジュアル
「みんなで楽しんでくださいね。また近いうちに顔を見せます。」
型は「一文目で意図、二文目で配慮、三文目で結び」を意識すると、短くても温度が伝わります。
封筒の選び方と印象を良くするポイント
一筆箋は封筒に入れるときちんと感が上がります。便箋のトーンと合わせた白〜生成り、または淡い季節色が無難です。サイズは中身に対して余白が出すぎないものを。和紙封筒や内紙付きの不透明封筒なら、内容が透けず上品です。
三つ折りにして、開いたときに最初の一行が読みやすい向きで入れます。封はのりや丸シールを軽く。シーリングワックスは好みが分かれるため親戚向けでは控えめに。宛名はフルネーム、差出人は裏面左下か封の綴じ目付近に小さく書くと整います。香り移りを避けるため、強い芳香は付けないのが安心です。
仕上げのコツは「便箋と封筒のトーンを統一」して清潔感を出すこと。それだけで受け取ったときの第一印象が変わります。
感謝の気持ちを伝えるためのアイデア
心ばかりの贈り物であることを伝える文例
「高価ではないけれど、気持ちはたっぷり」を自然に伝えるコツは、控えめな前置き+感謝+相手への配慮の三点セットです。
大げさにせず、等身大の言葉で“気持ちが主役”だと伝えるのがいちばん効果的。
使いやすい文例
「ほんの気持ちですが、日頃の感謝を込めてお送りします。お口に合えばうれしいです」
「ささやかではありますが、いつもお気にかけいただいているお礼です。ご笑納ください」
「季節のご挨拶をかねて、小さな品を送りました。お体に気をつけてお過ごしください」
「気に入っていただけると良いのですが、無理のない範囲でお納めください」
近しい親戚向け(カジュアル)
「気持ちばかりの詰め合わせです。みんなでわいわい食べてくださいね」年配の親戚向け(やや丁寧)
「心ばかりの品にて失礼いたします。お加減の良いときにお召し上がりください」
ワンポイント
「つまらないものですが」は今は避ける人も多め。代わりに「ささやかですが」「気持ちばかりで恐縮ですが」を。
相手の好みを一言添えると温度が上がります。「以前お好きだと伺った○○を選びました」など。
具体的な贈り物とそのメッセージ
贈り物の種類に合わせて“使う場面”を想像させると、短い一筆でも印象に残ります。
品名+配慮(食べやすさ・使いやすさ・家族構成)+ひとこと感謝の順でまとめると自然です。
品別メッセージ例
和菓子
「季節の和菓子を少し送ります。お茶の時間のおともにしていただければ幸いです」焼き菓子・詰め合わせ
「日持ちのする焼き菓子にしました。お時間のあるときに、皆さまでどうぞ」コーヒー・紅茶
「休憩のひとときに楽しんでいただける豆(茶葉)を選びました。香りでほっとしてもらえたら」調味料・だし・オイル
「普段の食卓で使いやすいものを詰めました。いつもの料理が少し楽になるとうれしいです」タオル・日用品
「肌ざわりのやさしいタオルをお送りします。毎日の暮らしでお役立てください」地元の特産品
「こちらの名物を見つけました。懐かしく感じていただけたら何よりです」フルーツ
「食べごろを選びました。冷やしてお召し上がりください」
配慮メモ
アレルギーや固いものが苦手な方には、食感や原材料に一言添える。
冷蔵・冷凍品は到着日や保存方法を明記。「冷蔵でお届けします。到着後は早めにお召し上がりください」
お礼の品物を送る際の送り状の書き方
送り状は一筆箋より一段丁寧に、構成を決めてから短く整えます。
基本は「前文(時候)→お礼→品の案内→結び→署名・日付」の順。
使い回せるひな形
拝啓 〇〇の候、皆さまお変わりなくお過ごしのことと存じます。
先日は温かいお心遣いを賜り、誠にありがとうございました。
心ばかりではございますが、別便にて〇〇をお送りいたしました。お口に合いましたら幸いです。
朝夕冷え込む折、どうぞご自愛ください。 敬具
令和〇年〇月〇日
〒・住所/氏名
実務のコツ
到着方法を明記「クール便で明日午後着の予定です」
同梱物が複数なら箇条書きで品名・数量を簡潔に
送り主の連絡先を小さく添えると受取連絡がしやすい
忌み言葉は避ける(壊れる、切れる、消える など)
香りの強い便箋や派手な封かんは控えめに
フォロー
到着連絡が来たら、ひと言のお礼を返すと関係がより滑らかに。
例「無事お届けできて安心しました。どうぞご無理なくお召し上がりください」
季節ごとの贈り物と一筆箋の使い方
お歳暮・お中元におすすめの例文
季節のご挨拶として贈るお中元やお歳暮は、「日頃の感謝」を形にする絶好の機会です。贈り物とともに一筆箋を添えることで、より丁寧で温かな印象を与えられます。
季節の挨拶を最初に入れることで、形式ばらずに誠実さを伝えるのがポイントです。
たとえば、
「梅雨明けの暑さが続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。日頃の感謝を込めて、ささやかな品をお送りいたします。」
「今年もお世話になり、心よりお礼申し上げます。ご多忙の折、どうぞお体にお気をつけくださいませ。」
「暑い日が続きますが、どうぞご自愛ください。涼を感じていただければ幸いです。」
「一年の感謝の気持ちを込めて、お歳暮の品をお送りいたします。ご家族皆さまのご健康をお祈り申し上げます。」
お中元は「7月上旬〜15日頃まで」、お歳暮は「12月上旬〜20日頃まで」が目安です。遅れる場合は「寒中御見舞」「残暑御見舞」など時期に合わせた表現に変えるのがマナー。
“季節の言葉+感謝+体調を気づかう一言”を入れると、やわらかく心のこもった印象になります。
お祝い事や内祝いにおける一筆箋の役割
お祝い事では「ありがとう」と「うれしい気持ち」を一緒に伝えることが大切です。贈る側・贈られる側のどちらであっても、気持ちを添えることで関係がより深まります。
お祝いをいただいたときは、内祝いの品に一筆箋を添えましょう。
「このたびは温かいお心遣いをいただき、誠にありがとうございました。ささやかではございますが、お礼のしるしに心ばかりの品をお送りいたします。」
「お祝いのお言葉をいただき、感謝申し上げます。無事に新生活を迎えることができました。」
「おかげさまで元気に過ごしております。感謝の気持ちを込めて、内祝いの品をお贈りいたします。」
また、出産・結婚・入学・長寿などのお祝いを贈る場合は、祝意を素直に表し、相手の喜びを一緒に喜ぶ気持ちを添えると印象的です。
「お子さまのご入学、誠におめでとうございます。新しい門出を心よりお祝い申し上げます。」
「ご結婚おめでとうございます。末永いお幸せをお祈りしております。」
「感謝」と「喜びの共有」をセットに書くのが一筆箋の基本。 丁寧さを意識しつつも、長くなりすぎず簡潔にまとめましょう。
時期に応じたマナーと注意点
季節の贈り物や行事ごとのやりとりには、時期や状況に応じたマナーがあります。特に年末年始・お盆などは郵送・配送が混み合うため、早めの準備が肝心です。
早めの送付が信頼感につながる
年末年始の贈り物は「12月20日頃まで」に届くよう手配
お中元は「7月中旬まで」に到着するように
お盆や敬老の日などの贈り物も、行事の1週間前を目安に
デザイン・言葉選びにも季節感と配慮を
弔事後の贈り物(お供え・お返し)では、華やかな柄や明るすぎる色味は避け、落ち着いたトーンと控えめな文面にすることが大切です。
例:「このたびはご厚情を賜り、誠にありがとうございました。ささやかではございますが、お礼の品をお送り申し上げます。」
避けたい表現
忌み言葉(切る・終わる・消えるなど)
重ね言葉(二重・重ね重ね)
大げさすぎる表現(心より御礼申し上げまする、など)
また、暑中見舞いや寒中見舞いなど、季節の挨拶として一筆箋を使うのもおすすめです。
「残暑お見舞い申し上げます。厳しい暑さが続きますが、お身体に気をつけてお過ごしください。」
など、季節の風情を感じさせる言葉を添えることで、心に残るメッセージになります。
まとめのポイント
季節の挨拶+感謝+体調を気づかう言葉を基本構成に
送付時期は早めを意識
華美すぎず、相手の立場や状況に合わせた表現を
一筆箋の柄・色味も季節と相手に合わせて選ぶ
季節の節目に交わすひと言が、関係を温め、次のご縁へとつながります。
ビジネスシーンでも使える一筆箋
取引先への挨拶状としての一筆箋
取引先に贈り物を送る際や、初めての取引が始まるタイミング、または契約更新時など、節目に一筆添えることで、信頼感と誠実さを印象づけることができます。
ビジネスでは長文よりも、簡潔で端的な表現が好まれます。「お世話になっております」「今後ともよろしくお願いいたします」といった基本のフレーズを押さえつつ、丁寧な言葉選びを心がけましょう。
たとえば、
「このたびはお取引いただき、誠にありがとうございます。心ばかりの品をお送りいたします。今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。」
「平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。ささやかではございますが、日頃の感謝の気持ちを込めてお送りいたします。」
「このたびはお世話になり、誠にありがとうございました。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。」
重要なのは、相手への感謝と今後の良好な関係を願う気持ちをセットで伝えること。
形式的になりすぎず、相手の立場を思いやる言葉を添えることで、温かみのある挨拶状になります。
また、季節のご挨拶として使用する場合は、冒頭に時候の挨拶を一言入れると、より丁寧な印象に。
「春寒の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。」
「師走の折、ご多忙のことと存じますが、今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。」
紙面の余白を多めにとり、読みやすい字で書くこともマナーの一つ。文字の美しさよりも、丁寧に書かれていることが信頼感につながります。
上司や同僚に贈る際のポイント
社内の人に贈り物をする際も、一筆箋は活躍します。お世話になった上司や、日々助け合う同僚への感謝を伝える場面では、関係性に応じたトーンを選ぶのが大切です。
上司に対しては、かしこまった表現で敬意を示します。
「日頃よりご指導を賜り、心より感謝申し上げます。」
「いつも温かく見守ってくださり、ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」
同僚やチームメンバーに対しては、もう少し柔らかい表現でも構いません。
「いつもサポートしてくれてありがとう。これからも一緒に頑張ろうね。」
「忙しい中いつも助けてくれてありがとう。感謝の気持ちを込めてお渡しします。」
親しき仲でも礼儀を忘れず、「感謝の気持ち」と「相手への配慮」を一言添えるのが大人のマナーです。
特にビジネスの場では、フランクすぎる表現(例:「お疲れさまです!」「また飲みに行きましょう!」など)は控え、カジュアルでも品のある言葉を選びましょう。
一般的なビジネス一筆箋の文例
シンプルなメッセージでも、言葉遣いを整えれば十分丁寧に伝わります。短くても誠実さが伝わる例をいくつか紹介します。
「いつもお力添えいただき、ありがとうございます。感謝の気持ちを込めてお送りいたします。」
「日頃よりお世話になっております。ささやかですが、お礼の品をお贈りいたします。」
「平素のご厚情に感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。」
「業務のサポートをいただき、誠にありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。」
「ご支援に心より感謝申し上げます。引き続きご指導のほどお願い申し上げます。」
ビジネス一筆箋では、感情を強く出すよりも、落ち着いたトーンで感謝と敬意を伝えることが最も大切です。
堅すぎず、しかし軽くなりすぎない言葉選びを心がけ、相手の立場や関係性に合わせて表現を調整しましょう。
一筆箋は、ビジネスの中で信頼を築く「小さな誠意のかたち」です。短い一文でも、心を込めて書くことで、あなたの印象はより温かく、丁寧に伝わります。
一筆箋の種類と選び方
印刷タイプと手書きの違い
印刷タイプ(PCやプリンターで整えた文面/既成メッセージ入り)は、見た目が揃い誤字もなく、短時間で数を用意できるのが強みです。法人の挨拶や法要後の返礼など、同趣旨の文面を複数送る場面に向いています。一方で温度感はやや控えめ。最後に一行だけ直筆を添える(結びと署名を手書きにする)“ハイブリッド”にすると、事務的になりすぎません。
手書きは行間の呼吸や字の揺らぎに人柄が宿り、親戚やお世話になった方にはいちばん届きます。下書きのキーワード(「感謝」「季節」「結び」)だけ決めて3〜5行に収めると、端正で読みやすい印象に。ペンは濃い黒/ブルーブラックのゲルインク0.5〜0.7mmが滲みにくく万能です。
迷ったら“手書きが基本、必要に応じて印刷で補助”と考えると失敗しません。
和紙と便箋の使い方
和紙(楮・三椏系の風合い/和紙風含む)は、やわらかな質感と品の良さが出るため、目上への贈り物や改まった場面に最適です。にじみを抑えるため、速乾のゲルインクや細字の万年筆(F〜M)を。書いた直後は数秒置いてから重ねると汚れません。縦書きにすると、より丁寧な印象になります。
洋紙(コットン紙・上質紙)の一筆箋は表面がなめらかで、ボールペンでも線がクリア。カジュアルな贈り物や同世代の親戚向けに使いやすく、横書きとも相性が良いです。無罫は自由度が高い反面、字が流れやすいので下敷きに薄罫を敷くか、行頭を揃える意識を。
封筒は紙質を合わせると統一感が増します(和紙→和紙封筒、洋紙→洋封筒)。紙質×筆記具×書式(縦横)の相性を揃えると、短文でもきちんと見えます。
好きなデザインを選ぶ際の注意点
好みで選ぶ前に、「相手の年代・関係性・季節」を小さくメモして照らし合わせるのがコツ。年配の方には無地〜控えめな草花、同世代には淡色の北欧風、子育て世帯には明るい色味でも線画ベースなど、“落ち着き×親しみ”のバランスを取ります。
避けたいのは、文字スペースを圧迫する大柄のイラスト、強い金箔・ラメ、濃色地(黒・濃紺)での細字。読みづらく、品物よりデザインが前に出がちです。香り付きは好みが分かれるので原則オフ。弔事関連や快気見舞いの周辺では赤・金・賑やかな動物モチーフを避け、寒色〜ニュートラルを選びます。
“誰に送るか”を起点に、余白がしっかり取れるデザインを選ぶと、文章の温度がそのまま届きます。
まとめ|一筆箋で“心を伝える贈り物”を始めてみよう
一筆箋は、たった数行でも「あなたの想い」を伝えられる便利なツールです。
とくに親戚への贈り物には、感謝や近況を添えるだけで、心の距離がぐっと近づきます。
今日紹介した文例やマナーを参考に、あなたらしい言葉で一筆箋を活用してみてください。小さな紙一枚が、贈り物以上の“ぬくもり”を届けてくれます。