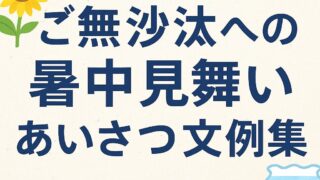親戚に贈る暑中見舞い文例集|印象に残る文章のコツ
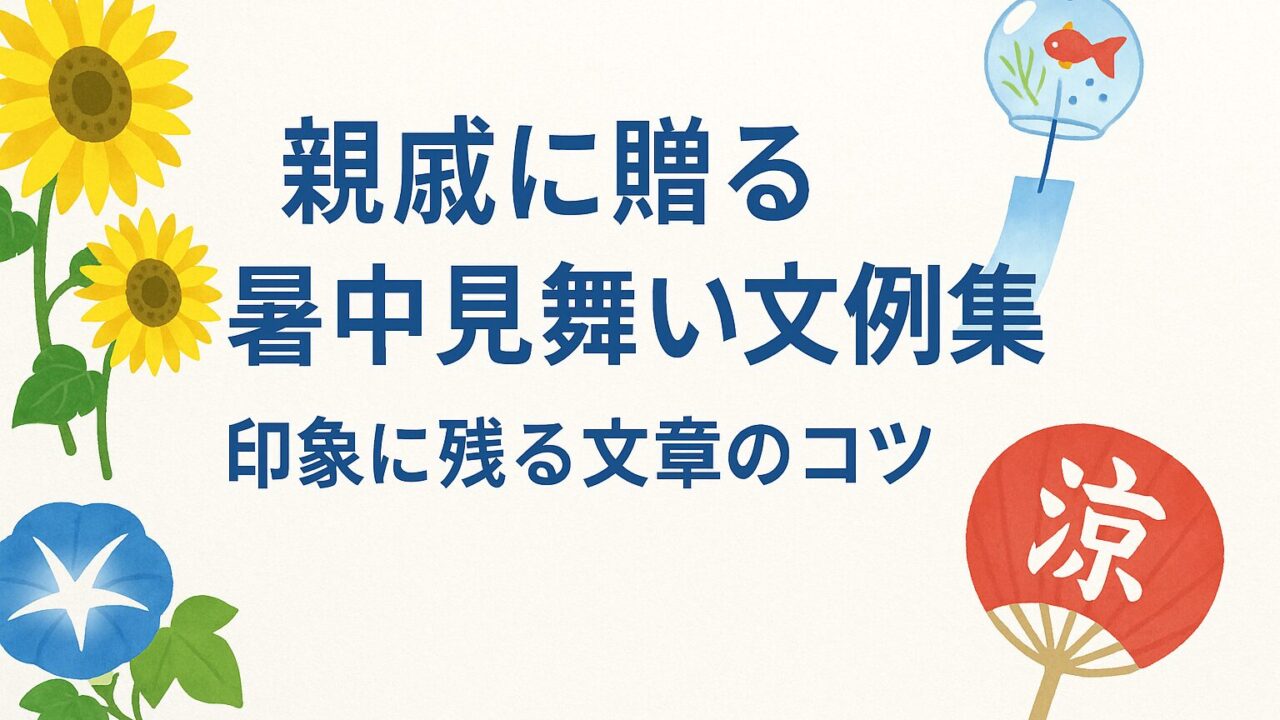
親戚への暑中見舞い、いざ書こうとすると「どんな言葉を選べばいいのか」「形式が合っているか」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。特に年配の親戚や久しぶりに連絡する相手には、失礼のない文面で心を込めて届けたいものですよね。
本記事では、親戚に喜ばれる暑中見舞いの書き方や、気の利いた文例を多数ご紹介。相手との関係性に応じた言葉選びのコツから、送る時期や形式のマナーまで網羅しています。2025年の夏は、あなたの気遣いがしっかり伝わる一枚を届けてみませんか?
暑中見舞いの基本知識

暑中見舞いとは何か
暑中見舞いとは、梅雨明けから立秋(例年8月7日ごろ)までの間に送る、夏の季節の挨拶状です。もともとは、暑さが厳しい時期に相手の健康を気遣う思いやりの文化から生まれたもので、日本では古くから親しまれてきました。
近年では手紙やハガキだけでなく、メールやLINEなどで気軽に送る方も増えていますが、やはり手書きの暑中見舞いには特別な温かみがあります。お中元と合わせて送ることで、より丁寧な印象を与えることもできます。日頃なかなか会えない人への「元気にしていますか?」というメッセージとしても重宝される、夏の風物詩的な習慣です。
親戚に送る暑中見舞いの意義
親戚への暑中見舞いは、形式的な挨拶にとどまらず、家族ぐるみの関係性を再確認できる良い機会です。特にお盆前後には親戚同士の交流が増えるため、その前に近況報告を兼ねて暑中見舞いを送っておくと、再会時の会話のきっかけにもなります。
高齢の親戚には「元気に過ごしていることが分かって安心した」と喜ばれることも多く、体調を気遣う一言やお礼の気持ちを添えることで、より心に残るご挨拶となります。また、お中元をいただいた際のお礼として暑中見舞いを送るのも、丁寧なマナーとして好印象です。
暑中見舞いと残暑見舞いの違い
暑中見舞いと残暑見舞いは、ともに夏に送る季節のご挨拶ですが、送る時期と文面が異なる点に注意が必要です。
「暑中見舞い」は、梅雨明けから立秋の前日(2025年は8月6日)までに送るのが一般的。これに対して「残暑見舞い」は、立秋(2025年8月7日)以降から8月末頃までに送ります。
文面にも違いがあり、「暑中お見舞い申し上げます」から、「残暑お見舞い申し上げます」へと表現を変えるのがマナーです。送る時期を過ぎてしまった場合でも、無理に暑中見舞いとして送らず、残暑見舞いとして丁寧に気持ちを伝えることが大切です。
親戚のおばさんへの挨拶文例

おばさんへの暑中見舞いの文例
暑中お見舞い申し上げます。
厳しい暑さが続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
いつも私たち家族のことを気にかけてくださり、本当にありがとうございます。
おばさんの優しいお心遣いに、いつも励まされております。
暑さが厳しい折、どうかお身体にはくれぐれもお気をつけて、元気にお過ごしくださいませ。
近況報告を含めた例文
こちらは家族一同、元気に過ごしております。
○○(子どもの名前)も無事に夏休みに入り、朝から晩まで元気いっぱいに遊んでおります。
この暑さのなかでも食欲旺盛で、見ていてこちらが元気をもらうほどです。
私自身も仕事に家事にと慌ただしい日々ですが、毎日充実しています。
暑さに負けず、皆で元気にこの夏を乗り越えたいと思っております。
お礼やお願いを添えた文面
先日は素敵なお中元をありがとうございました。
おばさんのお心遣いがとても嬉しく、家族皆で美味しくいただきました。
いつも変わらぬご厚情をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
なかなか直接お会いできる機会が減っておりますが、また落ち着いたらぜひ遊びに行かせてください。
その日を心待ちにしながら、暑い夏を元気に過ごしたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
暑中見舞いの書き方

書き出しのポイント
暑中見舞いの文章は、まず冒頭の「書き出し」で第一印象が決まります。最も基本的で格式ある表現が「暑中お見舞い申し上げます。」という定型文です。
これは、どのような相手にも通用する万能なフレーズであり、親戚や年配の方に対しても違和感なく使えます。
また、少し柔らかく表現したい場合は、以下のようなバリエーションもおすすめです:
「暑さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか。」
「本格的な夏の訪れを感じる今日この頃、皆様お元気でいらっしゃいますか。」
手紙の構成と流れ
暑中見舞いの手紙は、形式に沿って書くことで読みやすく、また誤解のない礼儀正しい印象を与えられます。以下の5つの要素を意識して構成しましょう。
挨拶(定型文)
例:「暑中お見舞い申し上げます。」相手の健康を気遣う言葉
例:「毎日厳しい暑さが続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。」自分の近況報告
例:「私どもはおかげさまで元気に過ごしております。○○も夏休みに入り、毎日楽しそうにしています。」お礼やお願い・次の機会への期待
例:「先日はお中元をいただき、誠にありがとうございました。近いうちにご挨拶に伺えればと思っております。」結びの言葉
例:「暑さ厳しき折、くれぐれもご自愛くださいませ。」
このように構成することで、自然な流れで読み手に想いが伝わりやすくなります。
結びの言葉の選び方
最後の「結び」は、暑中見舞いの余韻を決める重要なフレーズです。特に年配の親戚に対しては、礼儀正しく、思いやりが感じられる言葉選びを意識しましょう。
代表的な結びの言葉には以下のようなものがあります。
「暑さ厳しき折、どうかご自愛くださいませ。」
「くれぐれもお身体にはお気をつけてお過ごしください。」
「またお会いできる日を楽しみにしております。」
「今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます。」
時期と送るタイミング

暑中見舞いを送る時期
「暑中見舞い」は、梅雨明けから立秋の前日まで(例年7月15日頃~8月6日頃)に送るのが一般的とされています。具体的な目安としては、二十四節気の「小暑」(2025年は7月7日)から立秋の前日(8月6日)までが適切です。
特に注意したいのが「立秋」の日付。毎年変動するため、送る前にはカレンダーを確認しておくのが安心です。2025年の立秋は8月7日(木)ですので、それまでに投函することで「暑中見舞い」として正しく届きます。
なお、8月上旬は郵便物が混み合う時期です。なるべく7月中~月末までの投函を心がけると、より確実に「暑中見舞い」として届くでしょう。
立秋を意識した残暑見舞いの重要性
立秋(2025年は8月7日)を過ぎてから暑中見舞いを送るのは、マナーとしては誤りになります。その場合はすぐに切り替えて、「残暑お見舞い申し上げます」という表現で送るのが正しい対応です。
残暑見舞いは、猛暑がまだ続いている時期に「暑さが残る中での体調を気遣う」という意味合いを持ちます。形式を守ることで、受け取る側に丁寧な印象を与えると同時に、季節感もしっかり伝えることができます。
たとえば、8月10日に送る場合は「暑中見舞い」ではなく、「残暑見舞い」に。文面もそれに合わせて変更するようにしましょう。
お中元との関連性
お中元と暑中見舞いは、どちらも夏に贈る季節のご挨拶であり、同時期に重なる場合が多いため、併せて贈るケースも少なくありません。
たとえば、親戚やお世話になった方にお中元の品物を贈る際、一筆添えて暑中見舞いのメッセージを入れることで、より丁寧で温かみのある印象を与えることができます。
以下のような一文を加えるのがおすすめです。
「暑中お見舞い申し上げます。ささやかではございますが、感謝の気持ちを込めて季節の品をお贈りいたします。」
また、お中元をいただいた後に暑中見舞いを送る場合には、お礼の言葉を中心に文面を構成すると、丁寧で礼儀正しい印象になります。
「先日はお中元をありがとうございました。お心遣いがとても嬉しく、家族で美味しくいただきました。」
このように、暑中見舞いはお中元の「お礼状」としても活用可能です。タイミングや相手との関係性に応じて、上手に使い分けましょう。
暑中見舞いの文例集
一般的な挨拶文の参考
暑中お見舞い申し上げます。
日ごとに暑さが増してまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
暑さ厳しき折、どうかお身体を大切に、無理なさらずお過ごしください。
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
このような文面は、幅広い相手に使える万能な挨拶文です。親戚・友人・ご近所・仕事関係者など、関係性を問わず活用できます。文章のトーンもやわらかく、気遣いが自然に伝わるのが特徴です。
多様なシーンに適した文例
● 受験生がいる家庭へ
暑中お見舞い申し上げます。
お子様の受験勉強もいよいよ本格化する時期かと存じます。
この暑さに負けることなく、体調に気をつけながら日々努力を続けられるよう、陰ながら応援しております。
ご家族の皆様もどうぞご自愛ください。
● 高齢の親戚へ
暑中お見舞い申し上げます。
連日の猛暑により体調を崩しやすい季節ですが、お変わりございませんでしょうか。
どうか無理をなさらず、涼しいお部屋でお過ごしくださいませ。
お元気なお顔をまた拝見できる日を楽しみにしております。
● 小さなお子様がいる家庭へ
暑中お見舞い申し上げます。
にぎやかな夏休みが始まったことと存じます。
お子様にとって楽しい思い出がたくさんできる夏になりますように。
ご家族皆様、どうぞお元気にお過ごしください。
夏の健康を気遣う一言
暑中見舞いには、「相手の体調を気遣う一言」を添えることで、より心のこもった印象を与えることができます。以下のような表現を、結びや本文の途中に自然に入れてみましょう。
「熱中症や夏風邪には、くれぐれもご注意ください。」
「こまめな水分補給と休息を忘れずにお過ごしください。」
「日中の外出は無理なさらず、涼しい時間帯の活動をおすすめいたします。」
「ご自宅でも冷房などを上手に使って、快適にお過ごしくださいね。」
ちょっとした気配りの言葉が、相手の心を和ませる効果もあります。特に高齢の方や小さなお子様のいる家庭には、健康面への配慮が伝わると喜ばれます。
ビジネスマナーとしての暑中見舞い

親戚へのビジネス文としての配慮
親戚であっても、ビジネス上のつながりがある場合や公的な立場の方に送る場合は、礼儀を重んじた丁寧な文面を心がける必要があります。
親しみがあるからといって私的な雰囲気を出しすぎると、公私混同と取られてしまう可能性もあるため注意が必要です。
例文(ビジネス寄りの丁寧表現)
拝啓 盛夏の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年の夏も厳しい暑さが続いておりますが、貴社ますますのご発展と、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
敬具
このように、冒頭に季語を用いた時候の挨拶や、「貴社」などのビジネス敬語を含めることで、親戚であってもビジネスパートナーとしての敬意をしっかりと伝えることができます。
取引先への暑中見舞いの違い
ビジネスにおける暑中見舞いは、単なる季節のあいさつ以上に、「日頃の感謝」と「今後の関係強化」を意識した内容が求められます。特に取引先に送る場合は、格式を大切にした定型的な文章構成を基本とし、個人的な情報や軽い話題は控えるのがマナーです。
ポイント
会社宛てなら「貴社」、個人宛てなら「○○様」と記載
「暑さに負けず頑張りましょう」といったカジュアルな表現よりも、安定感のある敬語を使用
会社全体への配慮を示す文面が望ましい(例:「皆様のご健康と貴社のご発展をお祈り申し上げます」)
NG例
×「今年の夏はとにかく暑いですね〜」
×「最近仕事が忙しくてバテ気味です(笑)」
あくまで信頼と安心を与えるトーンを維持することが、ビジネスにおける暑中見舞いの役割です。
ビジネスシーンにおける暑中見舞いの重要性
暑中見舞いは、年賀状と並ぶ「年中行事としてのビジネス礼状」と位置づけられています。特に年賀状が減少傾向にある現代においては、夏の時期にあらためて挨拶を交わすことで、他社との差別化を図る有効な機会にもなります。
また、メールやチャットでは伝えきれない「思いやり」や「人との距離感」を、はがきや手紙を通じて表現することで、信頼関係の構築や維持にもつながります。
特に長期の取引先や、しばらくやり取りのなかった顧客に対しては、関係の再接続を図る絶好のタイミングとも言えるでしょう。
メールとハガキ、どちらが良い?

暑中見舞いのハガキの利点
ハガキによる暑中見舞いは、形として残る季節のご挨拶であり、メールやLINEにはない「特別感」を伝えることができます。
特に、手書きの文字や季節感のあるイラスト、絵はがきなどを用いることで、視覚的な印象も強く、もらった側の心に残りやすいのが大きな魅力です。
ハガキには以下のようなメリットがあります。
手間をかけたことが伝わり、誠意が感じられる
高齢の親戚やアナログ派の方に親しみやすい
飾ったり保管したりできるので、長く楽しんでもらえる
写真付きハガキやオリジナルデザインで季節感を演出できる
特にご年配の親戚にとっては、「文字を読む楽しみ」「はがきを受け取る嬉しさ」そのものが、暑中見舞いの魅力になります。日頃なかなか会えない相手だからこそ、こうした温もりあるやり取りが、関係性を深めてくれます。
メールでの挨拶状のポイント
現代では、暑中見舞いをメールやLINEなどのデジタルツールで送るケースも増えています。メールでの暑中見舞いは、以下のような利点があります。
相手がすぐに読めて、リアクションももらいやすい
画像や動画、リンクなどを添えて視覚的に演出できる
宛先が複数ある場合でも一括送信が可能で手軽
ただし、注意すべき点としては、カジュアルになりすぎないようにすること。特にビジネス関係者や年配の親戚にメールで送る場合は、以下のポイントを意識しましょう。
冒頭で「暑中お見舞い申し上げます」ときちんとご挨拶
文体は敬語を中心に、丁寧で落ち着いたトーンにする
顔文字や絵文字の多用、スラングは避ける
丁寧な言葉選びをすることで、「メール=手軽すぎる」と感じさせる印象を和らげ、誠実さや思いやりを感じてもらえる暑中見舞いになります。
親戚との関係性に応じた選択
暑中見舞いを送る際に、「ハガキが良いか、メールでよいか」は、相手との関係性によって使い分けるのが最も自然です。
ハガキが向いている相手
高齢の親戚や年賀状文化に親しみのある方
しばらく会っておらず、あらたまってご挨拶したい相手
お中元や贈り物の「お礼状」として兼ねたい場合
メールが向いている相手
普段からメールやSNSでやり取りしている親戚
若い世代や遠方に住んでいる親戚
堅苦しくなく、軽い近況報告をしたい場合
正式な印象を与えたい、特別な節目としての挨拶にはハガキを、気軽な連絡やカジュアルな報告にはメールを選ぶと、相手に合わせた配慮がしっかり伝わります。
健康を気遣う文面の考え方

暑さによる体調不良への配慮
暑中見舞いは単なる季節の挨拶ではなく、暑さが厳しい時期に相手の健康を気遣うという、日本ならではの思いやりの文化です。特に近年の夏は猛暑日が続き、高齢者や持病を抱える方、小さなお子様がいる家庭では、体調管理が難しくなりがちです。
そのため、文面の中で次のような一言を添えるだけでも、受け取る側に安心感と優しさを伝えることができます。
「気温の変化が激しい時期ですので、体調にはくれぐれもお気をつけください。」
「無理をなさらず、ゆったりとした時間をお過ごしくださいね。」
「どうか涼しい場所で、体を大切にされてください。」
相手の状況に少しでも思いを馳せた文章は、形式的な挨拶とは違い、本当に相手を気遣っている気持ちが伝わるのです。
自愛を促す言葉の選び方
文末に用いる「結びの言葉」は、手紙やはがきの印象を決定づける大切な要素です。中でも「ご自愛ください」という表現は、相手の健康と日々の生活を大切にしてほしいという心遣いがこもった、日本語ならではの美しい表現です。
以下のようにバリエーションを加えることで、文調や相手との関係性に応じた柔軟な表現が可能です。
「くれぐれもご自愛くださいませ。」(丁寧でフォーマルな印象)
「暑さが続きますので、どうぞご自愛のうえお過ごしください。」
「お身体に気をつけて、素敵な夏をお迎えくださいね。」(親しい相手向け)
「これからも健康第一で、毎日をお元気にお過ごしください。」
言葉ひとつで、文面の印象が格段にやさしく、親しみやすくなります。相手の性格や年齢に合わせて、自然に使える言葉を選びましょう。
心のこもった言葉の大切さ
どんなに形式通りで美しい文章でも、本当に相手を思う気持ちがこもっていなければ、それはただの“文例の引用”で終わってしまいます。
暑中見舞いを送るときは、相手の顔を思い浮かべながら、自分の言葉で一言を添えるようにしましょう。
たとえば――
「昨年の夏にいただいた冷菓、とても美味しかったですね。今年も暑くなりそうです。」
「○○さんの元気なお声を、また電話ででも聞かせてくださいね。」
「お体の調子はいかがでしょうか?無理なさらず、どうか穏やかにお過ごしください。」
このような、“あなたを想って書いています”という気配のある言葉こそが、真の暑中見舞いの本質です。
メールやSNSが主流になった現代だからこそ、手紙やはがきで届ける言葉の重みは、より一層大きな意味を持つのです。
暑中見舞いのデザインと形式
ハガキのレイアウトのポイント
暑中見舞いのハガキを作成する際は、全体のバランスと読みやすさを意識したレイアウトが大切です。基本的な構成は以下のとおりです。
上部:挨拶文(見出し)
「暑中お見舞い申し上げます」などの定型文を、大きめの文字や縦書きにして配置することで、視覚的にメリハリがつきます。筆文字風や毛筆体フォントを使うとより季節感が演出できます。中央:本文
相手への気遣いや近況報告など、本文を読みやすい行間で記載します。ハガキサイズに合わせて、4〜6行程度が目安です。文章は横書きでも縦書きでも構いませんが、和風の雰囲気を出したい場合は縦書きが人気です。下部:日付と署名
送付日や季節の表現(例:「令和五年 盛夏」)を左側に、送り主の氏名や住所を右下に配置するのが一般的です。個人なら「○月吉日」、法人なら正式な日付を入れるとよいでしょう。
レイアウトの整ったハガキは、受け取る側にも安心感と誠実な印象を与えます。
イラストや装飾の活用法
文章だけの暑中見舞いも丁寧ですが、イラストや季節のモチーフを加えることで、より印象に残る1枚になります。特に親戚や子どもがいる家庭、高齢の方へのハガキでは、見た目にも楽しい工夫が喜ばれます。
定番のイラストモチーフ
ひまわり・朝顔:夏の象徴として定番。明るく元気な印象に。
金魚・水風船:涼しげな雰囲気を演出。
風鈴・うちわ・スイカ:日本らしい夏の風情を感じさせる。
花火・夕焼け・入道雲:ノスタルジックな夏の空気感。
これらをワンポイントとして余白に添えたり、背景にうっすらとあしらうだけでも、デザイン性が高まります。最近では無料で使える和風イラスト素材やテンプレートも豊富なので、オリジナル性も出しやすくなっています。
手書きの温かみを加える方法
印刷されたハガキであっても、一言だけでも手書きのメッセージを添えることで、ぐっと心のこもった印象になります。
たとえば、
「○○さん、いつも本当にありがとうございます」
「暑さに気をつけて、元気にお過ごしください」
「またお会いできる日を楽しみにしています」
このような手書きのひと言は、フォントでは伝えきれない温もりや人柄を届ける力があります。文字に自信がなくても構いません。丁寧に書かれた字であれば、その思いはきちんと伝わります。
また、宛名面だけでも手書きにする、差出人の名前を手書きにするなど、小さな工夫でも印象は大きく変わります。
まとめ|親戚に想いを届ける暑中見舞いを今すぐ準備しよう
暑中見舞いは、親戚とのつながりを深める大切な夏の挨拶です。特に年配の方には、季節の気遣いや近況報告が何より嬉しい贈り物になります。
文例やマナーを参考に、相手に合わせた心のこもった一枚を選びましょう。手書きやハガキの工夫を加えることで、より印象的なご挨拶になります。暑さが本格化する前に、あたたかな言葉を添えた暑中見舞いの準備を始めてみてください。