子供向け七夕飾りの作り方|簡単&かわいい手作りアイデア集

もうすぐ七夕。でも「子供でも作れる飾りってあるの?」「どうやって教えたらいいの?」と悩んでいませんか?実は、身近な材料で安全に楽しめる七夕飾りの作り方がたくさんあるんです!
この記事では、保育士おすすめの簡単レシピから、年齢別の工作アイデアまで、子供向けに特化した情報を分かりやすくご紹介。親子で一緒に、楽しく季節行事を体験しましょう。初めてでも安心のポイントも解説していますので、ぜひ最後までご覧ください!
子供と一緒に作る七夕飾りの身近なアイデア

七夕飾りを楽しむ基本情報
七夕(たなばた)は、毎年7月7日に織姫と彦星が天の川を越えて一年に一度だけ出会えるという、ロマンチックで幻想的な物語に基づく日本の伝統的な行事です。この風習は、中国から伝わり、日本独自の文化と融合して現在の形になりました。
この日に向けて、多くの家庭では笹に色とりどりの飾りや短冊を吊るし、それぞれの願いを込めて楽しみます。特に子供にとっては、七夕の準備を通して、日本の文化や四季の移ろいを自然に学ぶ貴重な機会となります。
短冊に願いを書いたり、飾りを作ったりする体験は、想像力を育むだけでなく、季節行事の意味や価値を親子で共有することにもつながります。
最近では、昔ながらの伝統的な飾りに加え、現代風のおしゃれなデザインが注目を集めています。たとえば、カラフルなペーパー、リボン、ラメ入りのシール、グリッター素材などを取り入れることで、子供たちも思わず笑顔になるような華やかな飾りに仕上がります。
星型のオーナメントや、光沢のある紙で作った流れ星、透明感のあるセロファンを使った飾りなど、写真映えするデザインはインテリアとしても楽しめます。
最近ではSNSに投稿して家族や友人とシェアする家庭も増え、おしゃれな飾り作りは新たな楽しみ方として広がっています。
手作りの楽しさ:製作の魅力
手作りの七夕飾りは、親子の絆を深める最高のアクティビティです。子供たちが自らの手で飾りを作ることで、ものづくりの楽しさや工夫する喜びを実感できます。
完成した時の達成感や「自分で作った」という誇らしい気持ちは、自信にもつながり、積極性を育てるきっかけにもなります。さらに、自由な発想で色や形を考えながらデザインすることで、創造力や表現力を伸ばすことができます。
親が少しサポートしながら、子供のアイデアを尊重して一緒に作る時間は、心に残る思い出になるでしょう。
七夕飾りの簡単な作り方

基本的な七夕飾りの折り方
七夕飾りには、「輪つなぎ」「貝飾り」「網飾り」など定番の折り方があります。これらはどれもシンプルな折り紙テクニックで作れるため、小さなお子さんでも楽しく挑戦できます。
たとえば「輪つなぎ」は、折り紙を細長く切って輪をつなげるだけなので、はさみとのりの練習にもぴったり。「網飾り」は、折り紙に切り込みを入れるだけで繊細なデザインが完成し、達成感を味わえます。どれも短時間で完成するので、飽きずに続けられる点も魅力です。
折り紙を使ったかわいい飾り
色とりどりの折り紙を使えば、星やハート、流れ星、リボン型などのかわいいモチーフも簡単に作れます。例えば、折り紙を星型にカットして真ん中に顔を描けば、表情豊かで個性的な飾りが完成します。
さらに、色の組み合わせを工夫することで、季節感やテーマに合わせた雰囲気を演出できます。和柄の折り紙を使えば、少し大人っぽい上品な仕上がりにもなりますし、蛍光色を取り入れれば、ポップで楽しい印象になります。
保育士おすすめの簡単レシピ
保育士さんに人気の飾りレシピには、「短冊付きの輪つなぎ」や「ストローを使った吹き流し」「紙コップで作るちょうちん」など、安全性が高くて扱いやすい素材を使ったものが多くあります。
短冊に名前や願い事を書いたものを一緒に吊るすことで、飾りに意味を持たせることができ、子供たちのやる気や関心も高まります。
ストローや毛糸など、家庭にある材料で代用できるのも魅力のひとつ。年齢や発達段階に応じて、少しずつ難易度を調整することで、無理なく楽しく取り組むことができます。
七夕飾りアイデア集

定番の笹飾りを作ってみよう
笹の葉に色とりどりの飾りを吊るすのが七夕の定番です。この伝統的な飾りつけは、見た目も華やかで七夕の雰囲気をぐっと盛り上げてくれます。
おうちに本物の笹がない場合でも、緑の画用紙を使って笹の葉を切り出したり、クラフトペーパーを丸めて茎を表現したりすることで、十分に代用できます。
また、ラッピング用のリボンやモールで笹の枝を装飾するのも、子供たちにとって創造的で楽しい体験になります。
飾り付けには、短冊や折り紙の飾り、星の形をしたオーナメントなどを吊るすと、さらに華やかさが増します。親子で話しながら、願いごとを短冊に書いて吊るす時間は、思い出に残るひとときとなるでしょう。
吹き流しの魅力と作り方
風に揺れる「吹き流し」は、視覚的にも涼やかで、七夕の風情を一層引き立ててくれる人気の飾りです。作り方はとてもシンプルで、色とりどりの紙テープや細長く切った折り紙を使い、ひとつの土台に放射状に貼り付けていくだけ。
ストローや割り箸を使えば、軸がしっかりするため飾りやすくなります。配色を工夫することで、カラフルで個性的な作品に仕上がり、子供たちも自分のセンスを発揮できます。
また、風に揺れる様子を見て「風っておもしろいね」と自然への興味を引き出すこともできるなど、教育的な要素も含まれています。
三角ちょうちんのアレンジ方法
三角形の折り紙をいくつもつなげて作る「三角ちょうちん」は、空間に立体感と動きを加えることができるおしゃれな飾りです。作り方は、三角に折った折り紙を順に貼り合わせ、ちょうちんのような形に立体的に仕上げていきます。
色のバリエーションを変えることで、グラデーション効果を出すことも可能。さらに、画用紙に加えてカラーセロファンや透明フィルムを使えば、光を通して幻想的な雰囲気に。LEDライトを中に入れて、ほんのり光らせるのも人気のアレンジです。
子供たちのアイデアを取り入れて、オリジナルのちょうちんを作ることで、作品への愛着もより一層深まります。
七夕の意味と由来

織姫と彦星のストーリー
七夕の主役である織姫と彦星の物語は、中国の「乞巧奠(きっこうでん)」という行事が起源とされています。織姫は機織りの名手、彦星はまじめな牛飼いとして知られ、天帝により結婚が許されました。
しかし、結婚後に二人が仕事を怠けたため、怒った天帝によって天の川を挟んで引き離され、年に一度の七夕の日だけ再会が許されるようになったとされています。
この美しい伝説は、日本に伝来し、やがて七夕という行事として定着しました。切なさと希望を感じさせるストーリーは、多くの人々の心を惹きつけ、今もなお語り継がれています。子供たちにも伝えることで、物語への興味や情緒的な感性を育むことができます。
短冊に込める願い事
七夕の風習の中でも特に人気があるのが、自分の願いを短冊に書いて笹に吊るすことです。
もともとは、織姫のように裁縫や手芸が上手になりますようにと願ったのが始まりとされ、今では子供から大人まで、将来の夢や健康、家族の幸せなど、さまざまな願いが込められています。
子供たちにとって、自分の夢や希望を文字にして表現することは、自己肯定感や言葉の力を養う素晴らしい学びの機会です。親子で願いごとについて語り合うことで、日常では見えづらい子供の気持ちを知るきっかけにもなります。
天の川のロマンを感じる飾り
天の川は、織姫と彦星を隔てる広大な銀河を象徴しており、七夕の夜空を飾るロマンあふれるモチーフです。この天の川を表現した飾りには、キラキラと光るラメ入りの紙や、星の形をした折り紙、銀色やブルー系のリボンなどがぴったりです。
紙を細く切って編み込んだり、流れるように配置したりすることで、夜空に光が広がるような幻想的な空間を演出できます。
また、暗い部屋でライトアップして飾ると、天の川が輝いているように見え、子供たちの想像力を刺激します。飾りを作る際に、天の川の意味や物語を一緒に伝えることで、行事への理解も深まります。
年齢別の七夕飾り製作ガイド
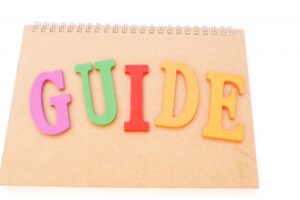
幼児向けの安全な製作方法
幼児と一緒に七夕飾りを作る際は、安全性を最優先に考えましょう。はさみやのりの使い方に注意しつつ、安全な素材(折り紙、セロテープ、クレヨンなど)を中心に使用すると安心です。
誤飲の危険がある小さなパーツは避け、手に持ちやすく、大きくて扱いやすい材料を選ぶのがポイントです。のりやシールの使用時も手がベタつきにくい製品を選ぶと、子供が不快感なく作業できます。
また、親がそばで見守りながら、一緒に手を動かすことで、作る楽しさと安心感を同時に提供できます。製作の合間に、完成品を使った遊びやお話を加えることで、子供の集中力を切らさずに楽しく続けられます。
小学低学年向けの難易度
小学低学年の子供には、簡単な折り紙だけでなく、少し工夫が必要な切り絵や貼り絵なども取り入れることで、より創造性を発揮させることができます。
例えば、複雑な模様を描いてから切り取る工程を加えると、細かい作業の練習にもなり、達成感を得やすくなります。製作前に手順をイラストや図解で説明したり、サンプルを見せたりすると、子供たちの理解も深まります。
また、自分で色や形を選ぶ工程を増やすことで、より主体的に製作に取り組めるようになり、思考力や判断力も育てられます。失敗しても「どうしたらうまくいくかな?」と考えさせる時間を持つことも、学びにつながります。
お子さんと一緒に楽しめる活動
製作そのものの楽しさに加えて、完成した飾りを使った遊びや演出を取り入れると、七夕の思い出がさらに深まります。
たとえば、飾りを使って部屋をデコレーションするだけでなく、手作りの短冊を読み上げて「願いごとの時間」を作ったり、完成した飾りの前で記念撮影をしたりと、活動の幅を広げることで満足感が高まります。
また、兄弟姉妹や友達と一緒に製作を行うと、協力する楽しさや、他の子のアイデアから学ぶ機会も生まれます。飾った後に「どれがいちばんのお気に入り?」とお話しする時間を持つことで、作品への愛着も深まり、より一層思い出に残る七夕体験になるでしょう。
七夕飾りのための材料リスト

必需品と便利な道具
- 折り紙、画用紙:色や柄を工夫することで表現の幅が広がります。季節感のある和柄やキャラクター柄など、子供が喜ぶデザインも多数あります。
- のり、セロテープ:紙同士の接着には欠かせないアイテム。液体のりやスティックのりなど、用途に合わせて選びましょう。セロテープは装飾の補強にも活躍します。
- はさみ、安全はさみ:年齢に応じて安全な道具を選びましょう。グリップが握りやすいタイプや先が丸い設計のものが幼児に適しています。
- ひもや糸、モール:飾りを吊るしたり立体的な装飾を作るのに便利です。ラメ入りのモールやカラフルな毛糸を使えば華やかさもアップします。
- クレヨンや色鉛筆:短冊や装飾に色をつける際に使えます。自由に描くことで、子供の想像力や表現力を育てます。
- ホチキス、パンチ、シール:飾りの組み立てや留め具としても活躍。好きなキャラクターのシールを貼れば、子供たちのテンションも上がります。
画用紙やおりがみの活用法
画用紙は厚みがあり丈夫なので、ちょうちんのベースや短冊の土台など、しっかりしたパーツ作りに最適です。カラーバリエーションも豊富で、テーマカラーに合わせた演出がしやすくなります。
また、切ったり貼ったりしても破れにくいのも魅力です。一方、折り紙は扱いやすく、細かい装飾や立体的なモチーフ作りに向いています。おりがみを折るだけでなく、カットしたり組み合わせたりすることで、星や動物など多彩なデザインが生まれます。
和柄や金銀の折り紙など特別感のある種類を取り入れることで、より印象的な作品に仕上がります。
簡単に手に入る材料について
七夕飾りに使う材料は、ほとんどが100円ショップや文房具店、ホームセンターなどで簡単に手に入ります。最近では季節コーナーに専用の手作りキットも販売されており、初めての人にも便利です。
加えて、家庭で不要になった包装紙、紙袋、新聞紙、雑誌の切れ端なども再利用可能です。これらを上手に活用することで、エコでコストパフォーマンスの高い工作が楽しめます。
段ボールや空き箱などを使えば、立体的な飾りの土台としても活用でき、工夫次第で表現は無限大。限られた材料の中で創意工夫することが、子供たちの発想力を伸ばすきっかけにもなります。
七夕飾りをもっと楽しくするアレンジ
カラフルなおもちゃの活用
キーホルダーや小さなおもちゃを飾りに加えることで、子供たちのテンションもアップ!キャラクター付きのアイテムや音が鳴るおもちゃを使えば、さらに盛り上がります。おもちゃを吊るすことで立体感や動きが加わり、より楽しい印象になります。
使用する際は、軽量で安全なものを選ぶようにしましょう。また、不要になったおもちゃの再利用にもつながるため、エコな取り組みとしてもおすすめです。子供が自分のお気に入りを飾りに加えることで、より一層作品に愛着を持つようになります。
セロハンテープの巧みな使い方
透明なセロハンテープは、見た目がすっきりして目立ちにくく、仕上がりが綺麗にまとまるのが魅力です。貼る位置や重ね方を工夫することで、色や光の効果を加える演出も可能になります。
例えば、カラーセロファンと組み合わせることで、光を通してキラキラとした印象を演出できます。セロハンテープでパーツ同士をつなげるだけでなく、補強の役割も果たしてくれるため、飾りが壊れにくくなるのもポイントです。
指先の器用さを育てるためにも、子供にテープの使い方を丁寧に教えてあげるとよいでしょう。
ハサミで切り込む!工夫の方法
ハサミを使って飾りに切り込みを入れることで、簡単に華やかで立体的な装飾ができます。たとえば、紙の端を波状やギザギザに切るだけでも印象が大きく変わります。紙を折った状態で連続した模様を切り抜けば、レースのような繊細なデザインも表現可能です。
安全な子供用ハサミを使うことで、安心してチャレンジできますし、手先の器用さや集中力の向上にもつながります。複数の紙を重ねて一度にカットするテクニックを使えば、時短にもなり、量産が必要なときにも便利です。子供が自由に形を作る過程を通じて、創造性もぐんぐん育ちます。
七夕イベントにぴったりの飾り
家庭での七夕飾りの取り入れ方
窓辺やリビングの一角に飾りコーナーを作ると、季節感あふれる空間に早変わりします。特にリビングやダイニングの目立つ場所に設置すると、家族みんなが自然と七夕の雰囲気を感じられるようになります。
壁に星型の飾りや天の川をモチーフにした装飾を追加すると、空間がより華やかになります。さらに、照明を落としてLEDライトなどで演出すれば、幻想的な雰囲気を作り出すことも可能です。
飾りつけを家族みんなで行えば、コミュニケーションも深まり、子供たちにとっても楽しい思い出になります。短冊には家族それぞれの願いごとを記入して、一緒に吊るすことで、日常にはない特別な体験が生まれます。
幼稚園や保育所での活用事例
七夕の時期になると、多くの幼稚園や保育所ではイベントとして七夕飾り作りが行われます。グループ製作で大きな笹飾りを作る活動では、協力してひとつの作品を完成させる達成感が得られます。
短冊に書いた願いごとを読み上げる「願い事発表会」や、飾りの意味を学ぶ時間を取り入れることで、子供たちの理解や関心も深まります。
また、保護者を招いて一緒に製作する親子参加型のイベントにすることで、家庭とのつながりも強化されます。製作を通じて、手先の器用さだけでなく、発表力や協調性などの社会性を育むことができるのも大きなメリットです。
友達と一緒に作る楽しさ
友達同士で七夕飾りを作る時間は、子供たちにとって創造的でわくわくする体験です。アイデアを出し合いながら進めることで、互いに刺激を受け、自然とコミュニケーション力や表現力が育まれます。
特にグループでテーマを決めて、星空や宇宙などの世界観を表現する活動は人気があります。自分の作品を仲間に見せたり、相手の作品をほめたりすることで、達成感と自己肯定感も得られます。
また、完成した飾りを並べてミニ展示会のようにして発表すれば、イベントとしての盛り上がりも倍増します。みんなで作ったという思い出は、季節行事をより楽しく特別なものにしてくれるでしょう。
七夕飾りの保管と保存方法

できあがり後の管理方法
完成した飾りは、丁寧に収納することで長くきれいな状態を保つことができます。飾りごとにジップ付きの袋やチャック付きポーチに入れると、型崩れやホコリの付着を防げます。
収納する際は、折り目や接着部分が剥がれないように注意し、やわらかい紙や布で包んで保護するとさらに安心です。
また、収納箱に「七夕飾り○年」といったラベルを貼り、作品ごとに名前や日付、願い事を記録しておくと、後で見返したときに楽しい思い出になります。子供自身に名前や飾りの意味を記入させることで、作品への愛着や記憶も深まります。
次の年への活用法
しっかり作った七夕飾りは、翌年にも十分に使い回すことができます。使う前に点検して、傷んでいる部分は修復したり補強したりすれば、見た目もきれいに保てます。
また、前年の飾りをベースに新しいパーツを追加したり、色や素材を変えてリメイクすることで、新鮮さを感じながら再利用できます。子供と一緒に「今年はどうアレンジしようか?」と話しながら改良する作業も、楽しい共同作業になります。
再利用することで、資源の無駄を減らす意識や、物を大切にする心も自然と育まれます。
飾りの劣化を防ぐポイント
飾りを長持ちさせるためには、保管場所の環境にも気をつけましょう。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所は避け、風通しのよい棚や収納ボックスなどに保管するのが理想的です。
特に湿気が多い季節には、乾燥剤や防虫剤を一緒に入れておくと、カビや虫食いから守ることができます。紙素材の飾りには、あらかじめ厚紙で裏打ちして補強しておくことで破れにくくなり、長期保存にも対応できます。
こうしたひと手間を加えることで、毎年飾りを見返す楽しみが広がり、家族の思い出としても大切に残すことができます。
まとめ|子供と一緒に楽しく七夕飾りを作ってみよう!
七夕は、子供と一緒に季節のイベントを楽しむ絶好のチャンスです。簡単に作れる飾りや年齢別のアイデアを取り入れれば、工作が初めてでも安心。親子で過ごす時間は、学びと笑顔にあふれた特別なひとときになります。
この記事を参考に、今年の七夕はオリジナルの飾りで家族の思い出を彩ってみませんか?今すぐ材料をそろえて、楽しい制作時間を始めましょう!














